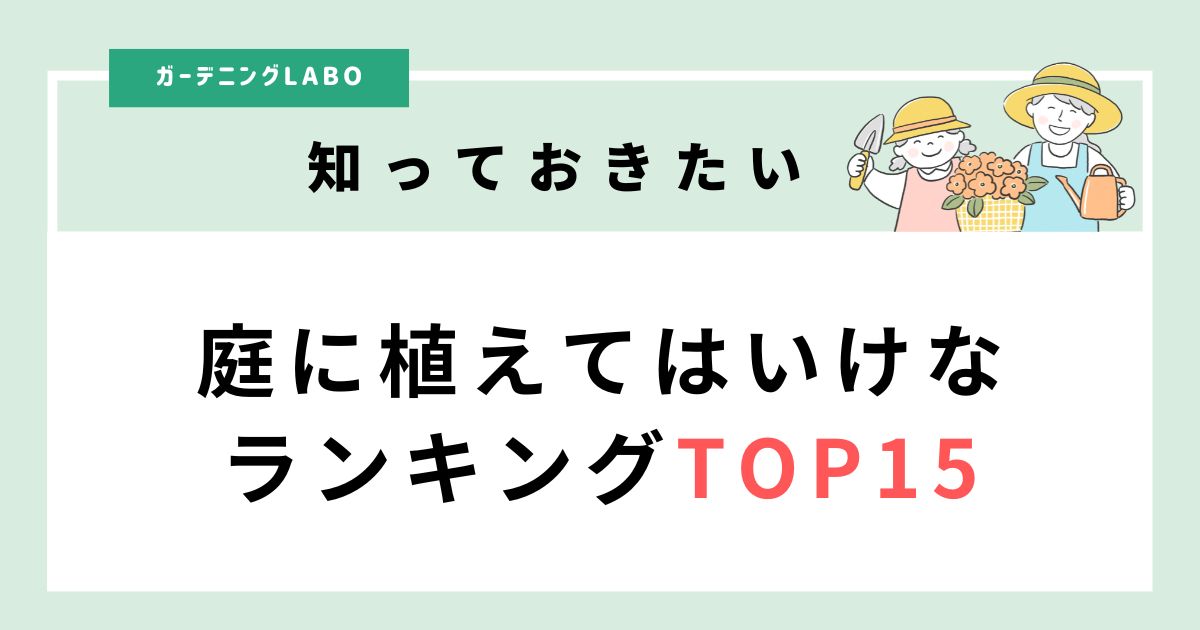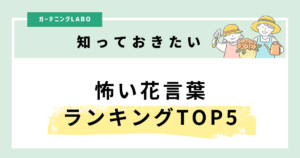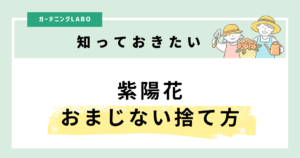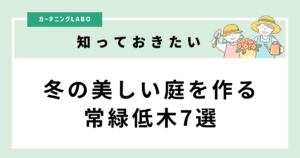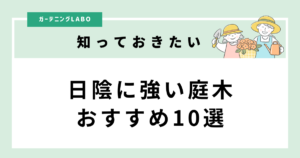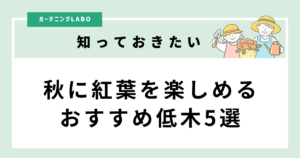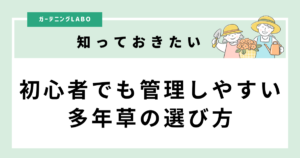理想の庭づくりを始める際、どんな植物を選ぶかは非常に重要な決断です。庭に植えてはいけない植物を知らずに選んでしまうと、後々大きな後悔につながることがあります。繁殖力が強すぎて庭を侵食してしまうハーブ、根が建物の基礎を傷める樹木、近隣トラブルの原因となる花など、注意が必要な植物は実は数多く存在します。
一方で、庭に植えるといい木や目隠しに適した樹木、風水的に縁起が良いとされる植物を選べば、快適で運気の上がる理想的な庭を実現できます。特に、紫陽花はなぜ庭に植えてはいけないのかという疑問や、家の周りに植えてはいけない花について気になる方も多いでしょう。
この記事では、実際に植えてよかった木の情報も含めて、庭に植えてはいけない植物はどれか、そして庭に植えるといい木や目隠しに最適な樹木まで、ランキング形式で徹底的に解説していきます。
- 繁殖力が強すぎて後悔する植物ワースト5と対処法
- 根が強く家の基礎を傷める危険な樹木ランキング
- 風水的にNGとされる植物の真相と科学的根拠
- 目隠しや運気アップに最適な植えてよかった木ベスト5
【理由別】庭に植えてはいけない植物ランキングTOP15

庭に植える植物を選ぶ際、見た目の美しさだけで判断すると後々大変な思いをすることがあります。ここでは、実際に多くの方が後悔した庭に植えてはいけない植物をランキング形式で詳しく解説していきます。
成長しすぎて後悔!繁殖力が強すぎる植物ワースト5

庭に植えてはいけない植物の中でも、特に注意が必要なのが繁殖力の強い植物です。最初は小さくて可愛らしかったのに、気づけば庭中を覆い尽くし、駆除に何年もかかってしまうケースは珍しくありません。
1位:ミント類(庭に植えてはいけないハーブの代表格)
ミントは庭に植えてはいけないハーブの筆頭として知られています。その繁殖力は凄まじく、地下茎で爆発的に増殖します。ペパーミント、スペアミント、アップルミントなど、どの種類も同様の特性を持っています。
ミントを一度地植えすると、完全に駆除するのはほぼ不可能です。根が少しでも残っていると、そこからまた増殖を始めます。
実際の被害例としては、最初に30cm四方に植えたミントが、たった1年で庭全体に広がり、他の植物を駆逐してしまったというケースが多数報告されています。隣家の庭にまで侵入し、トラブルになることもあります。
どうしてもミントを育てたい場合は、必ず鉢植えで管理しましょう。深さ30cm以上の鉢を選び、鉢底から根が出ないよう定期的にチェックすることが重要です。

2位:竹・笹類
竹や笹は和の雰囲気を演出できる魅力的な植物ですが、地下茎の成長速度と範囲が予想をはるかに超えるため、一般家庭の庭には不向きです。
竹の地下茎は1日で数十センチも伸びることがあり、数年で隣家の庭や駐車場のアスファルトを突き破ることも珍しくありません。駆除費用が数十万円から100万円以上かかるケースも報告されています。
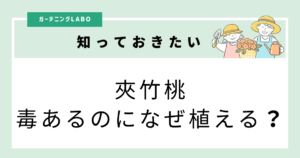
3位:ドクダミ
ドクダミは薬草として知られていますが、庭に植えると手に負えなくなる植物の代表例です。地下茎で増殖し、独特の臭いを放つため、近隣への配慮も必要になります。
ドクダミの駆除が困難な理由は、地下茎が深く広がり、少しでも残っていると再生する点にあります。除草剤を使っても完全に枯らすのは難しく、数年がかりの作業になることが一般的です。
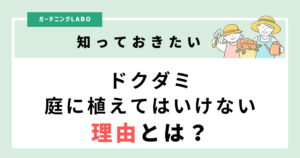
4位:ツルニチニチソウ
青や白の可愛らしい花を咲かせるツルニチニチソウですが、つる性で地面を這うように広がり、他の植物の成長を妨げます。節から根を出して増殖するため、管理が非常に困難です。
グラウンドカバーとして人気がありますが、想定以上に広がり、芝生や他の花壇に侵入してしまうトラブルが頻発しています。
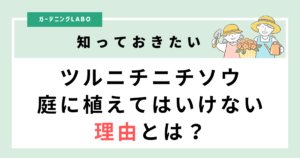
5位:オキザリス(カタバミ類)
小さな花が可愛らしいオキザリスですが、球根で増殖し、一度広がると完全駆除が困難です。特に芝生の中に入り込むと、手作業での除去が必要になり、膨大な時間がかかります。
| 植物名 | 繁殖方法 | 駆除難易度 | 主な被害 |
|---|---|---|---|
| ミント類 | 地下茎 | ★★★★★ | 庭全体への侵食、隣家への侵入 |
| 竹・笹 | 地下茎 | ★★★★★ | アスファルト破損、建物への影響 |
| ドクダミ | 地下茎 | ★★★★☆ | 庭全体への広がり、臭い |
| ツルニチニチソウ | 節から発根 | ★★★★☆ | 他の植物の成長阻害 |
| オキザリス | 球根 | ★★★★☆ | 芝生への侵入、景観の悪化 |
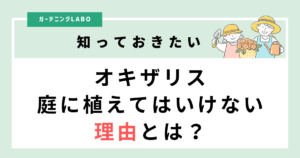
根が強すぎて家にダメージ!避けるべき樹木ランキング
庭に植えてはいけない樹木の中でも、特に建物への影響が深刻なのが根の張りが強い樹木です。植栽時は小さな苗木でも、成長すると予想以上に根が広がり、建物の基礎や配管にダメージを与えることがあります。
1位:イチジク
イチジクは絶対に植えてはいけない木の筆頭として多くの造園業者が警鐘を鳴らしています。根が非常に強く、水を求めて広範囲に伸びていくため、建物の基礎や排水管を破壊する事例が後を絶ちません。
イチジクの根は水分を求めて配管の継ぎ目から侵入し、内部で成長して詰まらせてしまいます。修理費用は数十万円に及ぶことも珍しくありません。また、基礎のひび割れに入り込み、建物の構造に影響を与えるケースも報告されています。
建物から最低でも10m以上離れた場所でなければ、イチジクの植栽は避けるべきです。
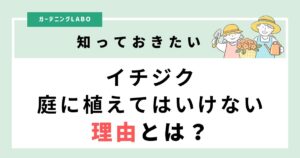
2位:桜
日本人に愛される桜ですが、一般家庭の庭に植えるには多くの問題があります。根が浅く広く張るため、建物の基礎や駐車場のコンクリートを持ち上げてしまうことがあります。
さらに、桜は樹高が10m以上になる品種も多く、落葉や花びらの掃除が大変です。虫がつきやすく、特に毛虫が大量発生することがあり、近隣からの苦情につながるケースも少なくありません。
3位:柳
柳は水辺に植えられることが多い樹木で、その根は水を求めて縦横無尽に伸びていきます。排水管や浄化槽に侵入し、詰まりや破損を引き起こす原因となります。
また、柳は成長が非常に早く、樹高も20m近くになることがあるため、一般家庭の庭には不向きです。風で折れやすく、台風時に近隣の家や車に被害を与えるリスクもあります。
4位:ポプラ
ポプラは成長が早く、まっすぐ伸びる美しい樹形が魅力ですが、根の張り方が非常に強く、地面を持ち上げる力があります。歩道のブロックや駐車場のアスファルトが盛り上がってしまう被害が多数報告されています。
5位:クスノキ
クスノキは神社やお寺でよく見かける大木で、樹齢数百年のものもあります。しかし、これは一般家庭の庭には全く適さないということを意味しています。
成長すると樹高30m以上、幹回り10m以上になることも珍しくなく、根も同様に巨大化します。植えてから数年で想定以上に成長し、伐採せざるを得なくなるケースが多発しています。
| 樹木名 | 根の特徴 | 主なリスク | 建物からの推奨距離 |
|---|---|---|---|
| イチジク | 水を求めて侵入 | 配管破損、基礎損傷 | 10m以上 |
| 桜 | 浅く広範囲に広がる | 基礎の持ち上がり、落葉 | 8m以上 |
| 柳 | 水を求めて深く伸びる | 排水管侵入、浄化槽破損 | 10m以上 |
| ポプラ | 強く地面を持ち上げる | 舗装の破損 | 8m以上 |
| クスノキ | 巨大化する | 建物全体への影響 | 15m以上 |
風水的にNGとされる植物とその理由
庭に植えてはいけない木として風水の観点から語られることも多くあります。風水は中国の伝統的な環境学で、気の流れを重視する考え方です。科学的根拠の有無はさておき、多くの人が気にする要素でもあるため、知っておくと役立ちます。
陰の気が強いとされる植物
風水では、暗く湿った場所を好む植物は陰の気を持つとされています。代表的なものに、シダ類、苔類、ドクダミなどがあります。
これらの植物が庭に多いと、家全体に陰の気が充満し、住む人の運気を下げるという考え方です。科学的には、これらの植物が繁茂する環境は湿気が多く、カビやダニが発生しやすいという実用的な問題があります。
棘のある植物
バラ、サボテン、ピラカンサなど、棘を持つ植物は風水的に好ましくないとされることがあります。特に玄関付近に植えると、良い気の流れを妨げると考えられています。
ただし、これには実用的な理由もあります。玄関付近に棘のある植物があると、通行の際にケガをするリスクがありますし、特に小さな子供やペットがいる家庭では注意が必要です。
毒を持つ植物
毒性のある植物も風水的にはNGとされることがあります。トリカブト、キョウチクトウ、チョウセンアサガオなどが該当します。
これは風水以前に、実際の安全性の問題です。特にペットや小さな子供がいる家庭では、誤食による中毒事故のリスクがあるため、植えるべきではありません。
死を連想させる植物
彼岸花(曼珠沙華)は、墓地や田んぼの畦道に植えられることが多いため、死を連想させる花として敬遠されることがあります。風水的には縁起が悪いとされることがあります。
しかし、彼岸花には球根に毒があり、これがモグラやネズミを寄せ付けない効果があるため、農地に植えられてきた歴史があります。迷信と実用性の両面から考えることが大切です。
| 植物の分類 | 代表例 | 風水的理由 | 実用的な理由 |
|---|---|---|---|
| 陰の気が強い | シダ類、苔、ドクダミ | 運気を下げる | 湿気が多い環境を作る |
| 棘がある | バラ、サボテン、ピラカンサ | 良い気を妨げる | ケガのリスク |
| 毒がある | キョウチクトウ、トリカブト | 負のエネルギー | 誤食による中毒 |
| 死を連想 | 彼岸花 | 縁起が悪い | 特になし(迷信的要素が強い) |
風水を信じるかどうかは個人の自由ですが、実用的なリスクも併せて考慮することで、より安全で快適な庭づくりができます。
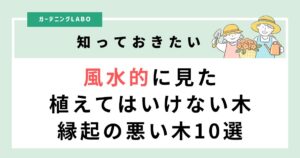
意外と危険!庭や玄関周りに植えてはいけない花
花は庭を彩る素敵な存在ですが、中には家の周りに植えてはいけない花も存在します。見た目の美しさに惹かれて植えてしまい、後悔するケースも少なくありません。
毒性のある花は要注意
最も注意が必要なのは毒性を持つ花です。スイセン、スズラン、福寿草、トリカブト、キョウチクトウなどは、美しい花を咲かせますが、全草に毒があります。
特にスイセンは、球根がニラや玉ねぎと似ているため、誤って食べてしまう事故が毎年発生しています。厚生労働省の統計によると、自然毒による食中毒の中でも、有毒植物による事故は重症化しやすいとされています。
小さな子供やペットがいる家庭では、毒性のある花は絶対に植えないことをおすすめします。万が一誤食した場合は、すぐに医療機関を受診してください。
アレルギーを引き起こす花
キク科の植物(マリーゴールド、ヒマワリなど)は、人によってはアレルギー反応を引き起こすことがあります。特にブタクサは、秋の花粉症の原因として有名で、庭に植えると自分だけでなく近隣にも影響を与える可能性があります。
ユリも強い香りが特徴ですが、花粉が服につくと取れにくく、ペット(特に猫)には毒性があるため注意が必要です。
害虫を呼び寄せる花
バラは美しい花の代表格ですが、アブラムシやチュウレンジハバチなど、多くの害虫を引き寄せます。無農薬で育てるのは非常に難しく、定期的な薬剤散布が必要になることがほとんどです。
また、ハイビスカスやムクゲはアオドウガネやハマキムシの被害を受けやすく、気づいたときには葉が穴だらけになっていることもあります。
手入れが大変な花
パンジーやビオラは秋から春にかけて長く楽しめる人気の花ですが、花がらをこまめに摘まないと見栄えが悪くなります。また、こぼれ種で増えすぎることもあります。
ペチュニアも同様に花がらつみが必須で、怠ると病気にかかりやすくなります。忙しくて手入れする時間がない方には不向きな花と言えるでしょう。
| 花の名前 | リスク分類 | 具体的な問題 | 注意すべき家庭 |
|---|---|---|---|
| スイセン | 毒性 | 全草に毒、誤食事故多発 | 子供・ペットがいる家庭 |
| スズラン | 毒性 | 水に浸けただけで毒性 | 子供・ペットがいる家庭 |
| キョウチクトウ | 毒性 | 強い毒性、燃やした煙も危険 | 全ての家庭 |
| ブタクサ | アレルギー | 花粉症の原因 | アレルギー体質の家族がいる |
| ユリ | 毒性・アレルギー | 猫に毒性、花粉が服につく | 猫を飼っている家庭 |
| バラ | 害虫 | 多くの害虫、管理が大変 | 手入れ時間が取れない家庭 |
【特集】紫陽花は本当に植えてはいけないの?真相を徹底解説
紫陽花はなぜ庭に植えてはいけないのか、という疑問を持つ方は非常に多いです。梅雨時期を彩る美しい花として人気がある一方で、植えない方が良いという意見も耳にします。ここでは、その真相を詳しく解説します。
紫陽花がNGと言われる主な理由
紫陽花が庭に植えてはいけないと言われる理由は、主に風水的な観点からです。以下のような説があります。
風水的な理由1:花の色が変わることの意味
紫陽花は土壌の酸性度によって花の色が変わります。この「変化」が、家庭内の人間関係や運気の変動を招くとする説があります。
風水的な理由2:水分を吸い上げる力が強い
紫陽花は水を好む植物で、吸水力が強いことから、家の金運を吸い取ってしまうという解釈があります。
風水的な理由3:陰の気が強い
紫陽花は日陰でも育つため、陰の気を持つ植物とされ、家の陽の気を弱めるという考え方があります。
実際には問題ない理由
結論から言えば、紫陽花を庭に植えること自体に実害はほとんどありません。上記の風水的な理由はあくまで迷信の範疇であり、科学的な根拠はありません。
実際、日本全国の多くの家庭や公園、寺社で紫陽花は植えられており、それによって問題が生じているわけではありません。むしろ、以下のようなメリットがあります。
- 比較的育てやすく、管理が簡単
- 日陰でも美しく咲くため、植える場所を選ばない
- 梅雨時期の庭を華やかに彩る
- 剪定によってコンパクトに管理できる
植えても良い条件と場所
もし風水を気にするのであれば、以下のような条件で植えることで、気になる点を軽減できます。
ただし、最も重要なのは、あなた自身が紫陽花を美しいと感じ、育てたいと思うかという点です。風水はあくまで参考程度にとどめ、自分の価値観を大切にすることをおすすめします。
紫陽花には毒性がありますが、誤って大量に食べない限り重篤な症状は出ません。小さな子供やペットがいる場合は、手の届かない場所に植えるなどの配慮があれば問題ありません。
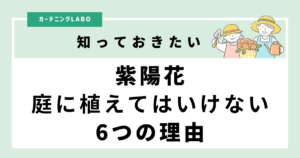
近隣トラブルの原因になる植物
庭に植える植物を選ぶ際、自分の庭だけでなく、近隣への影響も考慮することが重要です。植物が原因で近隣トラブルになるケースは決して珍しくありません。
落ち葉が多い木
イチョウ、桜、ケヤキなどの落葉樹は、秋に大量の落ち葉が発生します。これが隣家の庭や道路に散乱し、掃除の負担を強いることになります。
特にイチョウは、銀杏の実が落ちると独特の臭いを放つため、近隣から苦情が来るケースが多いです。マンションや住宅密集地では、植える際に十分な配慮が必要です。
虫がつきやすい植物
前述のバラのほか、ハナミズキやサルスベリも虫がつきやすい樹木です。特にアブラムシは、排泄物(甘露)で車や洗濯物を汚すため、近隣トラブルの火種になります。
桜につく毛虫も大量発生することがあり、隣家に飛んでいって苦情になることがあります。虫がつきやすい植物を植える場合は、定期的な薬剤散布など、適切な管理が不可欠です。
匂いが強い植物
キンモクセイは良い香りとして人気がありますが、香りに敏感な人にとっては不快に感じることもあります。特に窓の近くに植えると、隣家の部屋に香りが入り込んでしまう可能性があります。
クチナシも強い香りを放ちますし、ドクダミは独特の臭いがあるため、境界線付近に植えるのは避けた方が無難です。
境界を越えて侵入する植物
つる性植物(藤、つるバラ、ノウゼンカズラなど)は、放置すると隣家のフェンスや壁面に絡みつきます。見た目は美しくても、隣家にとっては迷惑な存在になりかねません。
また、前述の竹や笹、ミントなどの地下茎で増える植物も、境界を越えて隣地に侵入し、深刻なトラブルに発展することがあります。
植物を植える前に、隣家への影響を考慮し、境界線から十分な距離を取ることが大切です。また、植えた後も定期的な剪定や管理を怠らないようにしましょう。
| トラブルの種類 | 原因となる植物 | 対策 |
|---|---|---|
| 落ち葉・実 | イチョウ、桜、ケヤキ | こまめな掃除、境界から距離を取る |
| 害虫 | バラ、桜、ハナミズキ | 定期的な薬剤散布、早期発見 |
| 強い香り | キンモクセイ、クチナシ、ドクダミ | 境界から離れた場所に植える |
| 境界越え | 藤、つるバラ、竹、ミント | 定期的な剪定、地下茎の遮断 |
庭に植えるといい木や植物ランキング

ここまで庭に植えてはいけない植物について解説してきましたが、逆に庭に植えるといい木や植物も数多く存在します。管理がしやすく、目隠しにもなり、運気を上げると言われる植物を紹介していきます。
目隠しに最適!おすすめの木ベスト5
庭に植えるといい木として、特に人気が高いのが目隠し効果のある常緑樹です。プライバシーを守りながら、美しい景観を作り出すことができます。
| 樹木名 | 樹高 | 成長速度 | 特徴 | 適した場所 |
|---|---|---|---|---|
| シマトネリコ | 5〜10m | 早い | 美しい樹形、管理しやすい | 日向〜半日陰 |
| ソヨゴ | 3〜5m | 遅い | 赤い実、病害虫に強い | 半日陰 |
| ヤマボウシ | 3〜8m | 普通 | 四季を楽しめる、花と実 | 日向〜半日陰 |
| オリーブ | 3〜10m | 普通 | 地中海風、果実が楽しめる | 日向 |
| ハイノキ | 3〜5m | 遅い | 和モダン、剪定が楽 | 半日陰 |
目隠し用の木を選ぶ際は、成長後のサイズと管理のしやすさを必ず確認しましょう。狭い庭では、成長の遅い樹木を選ぶことで、剪定の手間を減らせます。
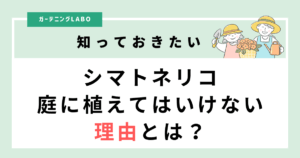
玄関や庭に植えると運気アップ!縁起の良い植物
風水的に縁起が良いとされる植物は、玄関に植えると縁起の良い木として古くから親しまれてきました。科学的根拠はありませんが、気持ちよく暮らすための一つの指針として参考にできます。
南天(ナンテン)
玄関に植えると縁起の良い木の代表格です。「難を転じる」という語呂合わせから、厄除けの木として昔から植えられてきました。赤い実が美しく、常緑で管理もしやすいため、実用的にもおすすめです。玄関脇や鬼門の方角に植えると良いとされています。
千両・万両
名前から金運を招く縁起物として知られています。赤い実が美しく、お正月の縁起物としても使われます。半日陰でも育つため、北側の庭にも適しています。庭に植えると運気が上がる花として、多くの家庭で愛されています。
松
「祝いの木」として、おめでたい場面で使われる松は、長寿や不老不死の象徴です。常緑で一年中緑を保つことから、「永遠」や「不変」を意味し、家の繁栄を願う木として植えられてきました。ただし、管理には手間がかかるため、剪定などの知識が必要です。
桃
魔除けの木として知られる桃は、風水でも邪気を払う力があるとされています。ひな祭りにも使われるように、女性や子供を守る木とも言われています。春には美しい花が咲き、実も楽しめるため、観賞価値も高い樹木です。
梅
早春に花を咲かせる梅は、「高潔」「忍耐」「美」を象徴する縁起の良い木です。厳しい寒さの中で花を咲かせることから、困難に打ち勝つ力を表すとされています。コンパクトに管理できる品種も多く、狭い庭でも楽しめます。
よくある質問Q&A
庭に植えてはいけない植物や、逆に植えると良い植物について、よく寄せられる質問をまとめました。
Q1: 絶対に植えてはいけない木は何ですか?
A: 建物の近くに植える場合、根が強く建物や配管に損傷を与える可能性のあるイチジク、桜、柳、竹は避けるべきです。また、一般家庭の庭のサイズを考えると、クスノキやポプラなど巨大化する樹木も不適切です。ただし、十分な広さがあり、建物から10m以上離れた場所であれば、これらの樹木も問題なく育てられます。
Q2: 玄関に植えると縁起の良い木は?
A: 南天が最も代表的な縁起の良い木です。「難を転じる」という意味から、厄除けとして玄関脇に植えられることが多いです。その他、千両や万両も金運を招くとされ、松は長寿と繁栄の象徴として好まれます。これらの樹木は管理もしやすく、実用的にもおすすめです。
Q3: 縁起の悪い植物は?
A: 風水的には、棘のある植物(バラ、サボテンなど)、陰の気が強い植物(シダ類、苔類)、死を連想させる植物(彼岸花)などが縁起が悪いとされることがあります。ただし、これらはあくまで風水上の解釈であり、科学的根拠はありません。バラなどは世界中で愛されている花ですし、適切な場所に植えれば何も問題ありません。
Q4: 庭に植えると運気が上がる花は?
A: 風水では、明るく鮮やかな色の花が運気を上げるとされています。特に、玄関周りには黄色やオレンジ色の花(マリーゴールド、ガザニアなど)が金運アップに良いとされ、ピンクや赤の花(バラ、ペチュニアなど)は人間関係運を高めると言われています。ただし、最も大切なのは、自分が気に入った花を育て、日々手入れをして大切にすることです。
Q5: 小さな庭でも安心して植えられる木は?
A: 成長が遅く、樹高が3〜5m程度に収まる樹木がおすすめです。具体的には、ソヨゴ、ハイノキ、ヒメシャラ、エゴノキなどが適しています。これらは根の張りも穏やかで、建物への影響も少ないです。また、鉢植えで管理できるシマトネリコやオリーブを選び、定期的に剪定することで、小さな庭でも十分楽しめます。
庭に植えてはいけないランキングまとめ
庭に植えてはいけない植物のランキングと、逆に植えるといい木について詳しく解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。
- ミントや竹など繁殖力の強い植物は地植えを避け、鉢植えで管理する
- イチジクや桜など根が強い樹木は建物から10m以上離して植える
- 風水的にNGとされる植物も実害がないものが多く、気にしすぎる必要はない
- 毒性のある花は子供やペットがいる家庭では避けるべき
- 紫陽花を庭に植えること自体に問題はなく、風水は迷信の範疇
- 落ち葉や害虫が多い植物は近隣トラブルの原因になるため配慮が必要
- 目隠しにはシマトネリコやソヨゴなど管理しやすい常緑樹がおすすめ
- ヤマボウシやオリーブは植えてよかったという声が多い人気の樹木
- 玄関に植えると縁起の良い木は南天が代表的で実用性も高い
- 千両や万両は金運を招く縁起物として人気がある
- 運気が上がる花は風水上の解釈であり、自分が好きな花を育てることが最も大切
- 小さな庭にはソヨゴやハイノキなど成長の遅い樹木が適している
- 植物を選ぶ際は成長後のサイズと管理のしやすさを必ず確認する
- 近隣への配慮として境界線から十分な距離を取って植栽する
- 最も重要なのは自分のライフスタイルと家族構成に合った植物を選ぶこと
理想の庭づくりは、植物選びから始まります。この記事で紹介した情報を参考に、後悔しない植栽計画を立てて、長く愛せる庭を実現してください。