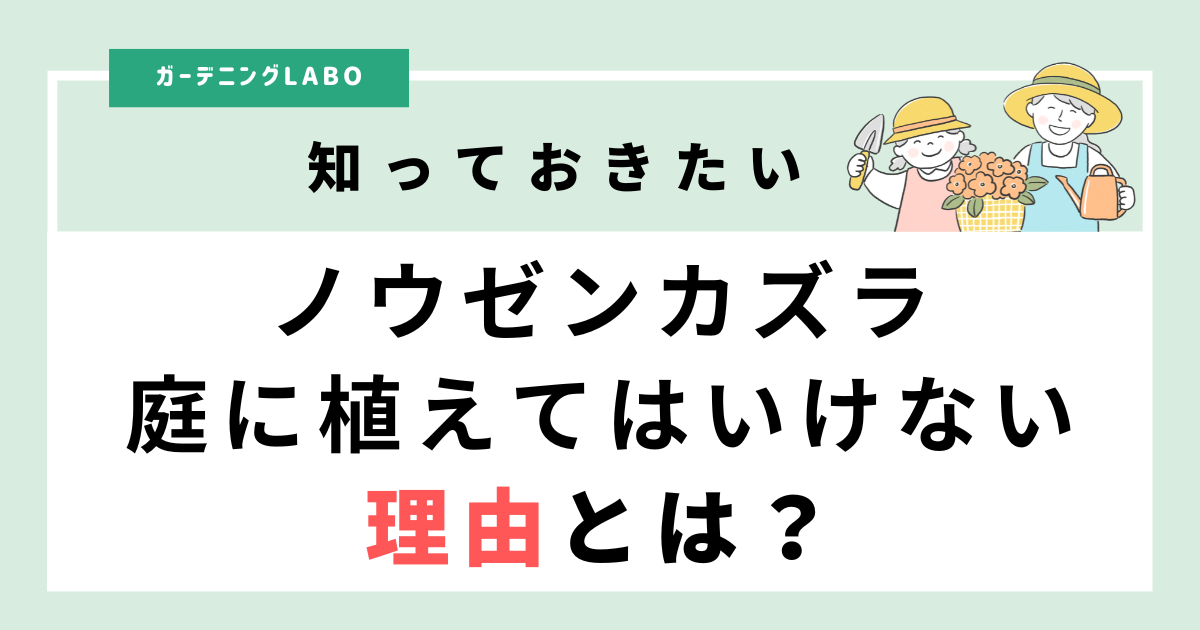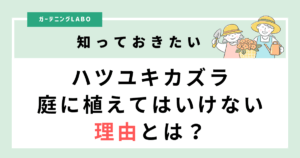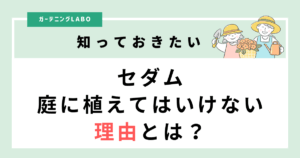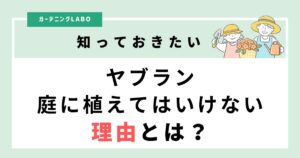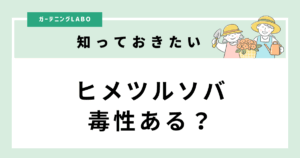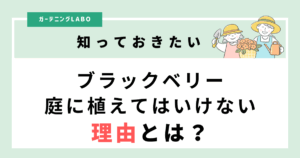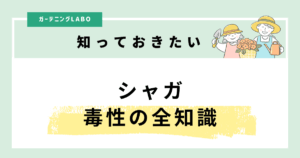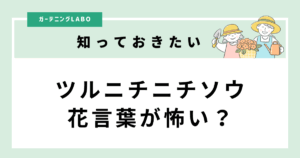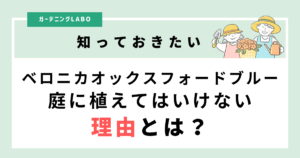真夏に鮮やかなオレンジ色の花を咲かせるノウゼンカズラ。その華やかな姿に魅力を感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、実際に庭に植えようと調べてみると、ノウゼンカズラ 植えては いけないという情報を目にすることがあります。毒性があるのではないか、縁起が悪いと聞くけれど本当なのか、鉢植えでなら安全に育てられるのか、もし植えてしまった場合の駆除方法はどうすればよいのかなど、不安に感じることも多いでしょう。
ノウゼンカズラには確かに注意が必要な特徴があります。花言葉に怖い意味があると誤解されたり、地下茎で勝手に生えるほど繁殖力が強かったり、剪定の時期を逃すと手がつけられなくなったりすることもあります。支柱 立て方を工夫したり、挿し木や切り花として楽しんだり、種や葉っぱの状態をチェックしながら育て方を学ぶことで、似た花との違いも理解できるでしょう。ノウゼンカズラには複数の種類があり、それぞれに特徴があります。
この記事では、ノウゼンカズラを植えてはいけないと言われる理由を詳しく解説するとともに、安全に楽しむための対策方法もご紹介します。正しい知識を身につければ、ノウゼンカズラの美しさを安心して楽しむことができるはずです。
- ノウゼンカズラを植えてはいけないと言われる5つの具体的な理由がわかる
- 毒性や縁起に関する誤解と正しい知識が理解できる
- 繁殖力の強さによる被害を防ぐ対策方法が学べる
- 鉢植えでの安全な育て方や駆除方法など実践的な知識が得られる
ノウゼンカズラを植えてはいけないと言われる5つの理由

理由①:毒が含まれている可能性がある
ノウゼンカズラにはラパコールという成分が含まれており、特に花の蜜に多く存在するとされています。この成分については古くから毒性があるという説が広まっていました。
毒性に関する誤解と真実
江戸時代の学者である貝原益軒の著書には、花の汁が目に入ると失明するという記載があり、長年にわたって強い毒性があると信じられてきました。実際、Wikipediaの記述によると、かつては植物図鑑にも有毒植物として記載されていた時期があったようです。
しかし現在では、実際には弱毒であり、失明するような強い毒性はないという見解が一般的です。とはいえ、人によっては花の蜜や樹液に触れることでかぶれやアレルギー反応を起こす可能性があります。
実際に起こりうる症状
| 接触部位 | 起こりうる症状 | 対処法 |
|---|---|---|
| 皮膚 | かぶれ、発疹、かゆみ | すぐに水で洗い流す |
| 目 | 炎症を起こす可能性 | 大量の水で洗い流し、医療機関を受診 |
| 口 | 嘔吐、めまいなど | 口をゆすぎ、症状が続く場合は受診 |
特に小さなお子様やペットがいる家庭では注意が必要です。花や蜜を直接触らないように、剪定や手入れの際は必ず手袋を着用しましょう。
高齢者との認識の違いに注意
昔の情報を信じている年配の方の中には、ノウゼンカズラは非常に危険な植物だと考えている方もいらっしゃいます。実際、ご近所から「毒があるから切ってほしい」と苦情を受けるケースも報告されています。
このようなトラブルを避けるためにも、植える前に家族や近隣の方に相談することをおすすめします。
理由②:縁起が悪いという言い伝えがある
ノウゼンカズラには、古くから縁起が悪いとされる言い伝えがいくつか存在します。これらは科学的根拠のない迷信ですが、文化的背景を理解しておくことは大切です。
花の色が火事を連想させる
ノウゼンカズラの燃えるようなオレンジ色の花は、見方によっては炎を思わせます。このため、庭に植えると家が火事になるという迷信が生まれました。
日本では古来より、赤系統の花は火や災厄を象徴するとされることがあり、特に東南の方角に植えることを避ける風習もあります。気になる方は、黄色やピンク色の品種を選ぶという選択肢もあります。
花の落ち方が打ち首を連想させる
ノウゼンカズラの花は、花びらが一枚ずつ散るのではなく、花全体がボトッと落ちるのが特徴です。この落ち方が、江戸時代の打ち首を連想させるため、縁起が悪いとされてきました。
同じように花全体が落ちる椿も縁起が悪いとされることがありますが、サザンカは花びらが一枚ずつ散るため、このような言い伝えはありません。
つる性植物に対する不吉なイメージ
日本では昔から、つる植物が他のものに巻き付く様子が、家の主の首を締め付けるように見えるとして、不吉な象徴とされてきました。
このような考え方は現代では迷信とされていますが、同居している家族や近隣に気にされる方がいる場合は、事前に相談しておくとトラブルを避けられます。
花言葉は実はポジティブ
花言葉が怖いという噂もありますが、実際にはそのようなことはありません。ノウゼンカズラの花言葉は以下のように、むしろポジティブな意味を持っています。
| 花言葉 | 由来 |
|---|---|
| 名声・名誉・栄光 | ラッパ状の花が、英雄を祝うファンファーレを連想させるため |
| 豊富な愛情 | 松の木とノウゼンカズラの恋物語の伝説から |
| 華のある人生 | 鮮やかな花姿から |
風水的な見解
風水的には、ノウゼンカズラは人気運を上昇させる効果があるとされています。つる性植物が上に伸びていく様子は、運気の上昇を象徴するという解釈もあります。
ただし、植える場所や方角については、気になる方は風水の専門家に相談するのもよいでしょう。
理由③:地下茎で勝手に増えてしまう
ノウゼンカズラが植えてはいけないと言われる大きな理由の一つが、地下茎による旺盛な繁殖力です。
地下茎の繁殖メカニズム
ノウゼンカズラは、地上部のつるだけでなく、地下でも茎を伸ばして繁殖します。この地下茎は目に見えないため、どこまで広がっているのか把握することが困難です。
地下茎からは新しい芽が次々と出てくるため、気がつくと思わぬ場所から芽が出ていることがあります。根の成長が非常に旺盛で、境界を越えて隣家の庭に侵入することもあるほどです。
勝手に生える具体的なケース
種による繁殖も侮れない
ノウゼンカズラは花が終わると、エンドウ豆のような実をつけます。この実が割れると、多くの小さな種が周囲に散らばります。
こぼれ種から自然に発芽することもあり、地下茎だけでなく種からも増殖するため、コントロールが非常に難しい植物といえます。
気根による這い上がり
ノウゼンカズラの茎や幹からは気根と呼ばれる特殊な根が生えます。この気根は空気中に伸び、壁面や他の樹木に吸い付くように張り付きます。
通常、植物の根は土の中で成長しますが、ノウゼンカズラの気根は地上に現れ、建物の外壁に直接付着する特性を持っています。一度張り付くと、ブラシのような気根がしっかりと絡みつき、剥がすことが非常に困難になります。
地植えにする場合は、地下茎が広がる範囲を想定し、十分なスペースを確保することが重要です。狭い庭や他の植物との距離が近い場所には植えないようにしましょう。
理由④:繁殖力が強すぎて駆除が困難
一度植えてしまったノウゼンカズラを完全に取り除くことは、想像以上に大変な作業です。駆除の難しさが、植えてはいけないと言われる理由の一つになっています。
地上部を切るだけでは不十分
多くの植物は、地上部をすべて切れば根も自然と枯れていきます。しかしノウゼンカズラの場合、地下茎が生きている限り、そこから新しい芽が次々と出てくるため、地上部を切っただけでは駆除できません。
具体的な駆除方法
ノウゼンカズラを完全に駆除したい場合は、以下の方法を繰り返し実施する必要があります。
| 方法 | 手順 | 注意点 |
|---|---|---|
| 除草剤を使う | 根や地下茎が残っている場所に除草剤を散布する 根の切り口に除草剤の原液を直接塗布する | 周辺の植物にかからないよう注意 何度も繰り返す必要がある |
| 熱湯をかける | 地下茎がありそうな場所に熱湯を注ぐ | やけどに注意 効果が限定的な場合もある |
| 根を掘り起こす | 可能な限り深く掘って根を取り除く | 完全に取り除くのは困難 重労働になる |
建物への被害
ノウゼンカズラを家の近くに植えていると、つるが伸びて気根が外壁に吸い付くように成長します。繁殖力が強いため、あっという間に外壁を広範囲で覆ってしまうこともあります。
問題なのは、気根が壁にしっかりと絡みついているため、つるを取り除いても跡が外壁に残ってしまうことです。この跡はなかなか取れず、ひどい場合は外壁を削るか、上から塗装し直す必要が出てきます。
ネット上では、樹勢が強すぎて家の外壁を破壊してしまったという報告も見られます。外壁のひび割れや変形など、修復が困難な被害を引き起こす可能性があるため、建物の近くには植えないことが賢明です。
他の植物への影響
ノウゼンカズラのつるは、周囲の樹木や塀に絡みつきながら成長していきます。つるが樹木に絡みつくと光を遮ってしまうため、絡まれた樹木が健康を損ね、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。
また、地下茎が他の植物の根元に広がることで、栄養を奪い、他の植物の成長を妨げる可能性もあります。小さな庭や限られたスペースでは、ノウゼンカズラが他の植物を圧迫し、庭の多様性が低下することが懸念されます。
電線や電柱への危険性
放置すると、つるが隣の庭や家の屋根を越えて、電信柱や電線にまで伸びることもあります。電線に絡みついてしまうと大きな事故につながる可能性があり、電力会社から撤去を求められることもあります。
管理が非常に大変で、手間がかかる点も考慮して、植えるかどうか慎重に判断することが大切です。
理由⑤:剪定などの手入れに手間がかかる
ノウゼンカズラは生命力が非常に強く、放置すると収拾がつかなくなります。美しい花を楽しむためには、定期的な剪定と管理が欠かせません。
適切な剪定時期
ノウゼンカズラの剪定に最適な時期は、落葉後の12月から3月です。この時期に剪定することで、翌年の春に勢いよく新しいつるが伸び、たくさんの花を咲かせやすくなります。
| 時期 | 剪定の種類 | 目的 |
|---|---|---|
| 12月~2月 | 強剪定 | 翌年の花付きをよくする 樹形を整える |
| 2月~3月 | 強剪定の最適期 | 勢いのよい新枝を出させる 長期間たくさんの花を楽しむ |
| 9月~10月 | 整理剪定 | 混み合った枝を間引く 花がら摘み |
| 開花期(6月~8月) | 軽い剪定のみ | 樹形を軽く整える程度 強剪定は避ける |
基本的な剪定方法
ノウゼンカズラの剪定は切り戻し剪定が基本です。太いつるを3節ほど残して、幹から伸びる細い枝を切り落とすのがポイントです。
この方法で剪定することで、翌年の春に勢いよく健康なつるを伸ばすことができます。剪定直後はさびしい姿になりますが、春になればすぐに新しいつるが伸びてきます。
放置するとどうなるか
剪定時の安全対策
剪定作業を行う際は、以下の点に注意が必要です。
花の蜜に毒性成分が含まれているため、ゴーグル、マスク、手袋を着用して作業しましょう。特に目に入らないよう注意が必要です。
また、高所作業が必要な場合は、無理せず専門の剪定業者に依頼することも検討しましょう。年に数回の剪定が必要で手間がかかることを理解した上で、管理できるかどうか判断することが大切です。
必要な道具
| 道具 | 用途 |
|---|---|
| 剪定ばさみ | 細い枝や茎を切る |
| 剪定のこぎり | 太い幹や枝を切る |
| 防刃手袋またはラバー加工の軍手 | 手の保護 |
| ゴーグル | 目の保護 |
| マスク | 粘膜の保護 |
| 熊手やホウキ | 切った枝を集める |
園芸用品店やホームセンターで購入できますので、剪定作業の前にしっかりと準備しておきましょう。
ノウゼンカズラを植えてはいけない場合でも安全に楽しむ方法

鉢植えで管理しながら育てる
地植えのリスクを避けながらノウゼンカズラを楽しみたい場合は、鉢植えでの栽培がおすすめです。鉢植えなら地下茎の広がりを制限でき、管理もしやすくなります。
鉢植えでの栽培方法について詳しく解説します。
適切な鉢のサイズを選ぶ
ノウゼンカズラは成長が早い植物なので、大きめのプランターを選びましょう。直径40cm以上の鉢が理想的です。排水穴がしっかりと確保されていることを確認してください。
水はけが良いだけでなく、適度な水持ちも大切です。赤玉土6に腐葉土4をブレンドした土、または市販の培養土と赤玉土を1対1で混ぜた土がおすすめです。
支柱の立て方のコツ
ノウゼンカズラはつる性植物なので、つるが這い登れるように支柱を立てることが必要です。
| 仕立て方 | 特徴 | 向いている場所 |
|---|---|---|
| あんどん仕立て | 朝顔の支柱のように円形に組む コンパクトにまとまる | ベランダや玄関先 |
| トレリス仕立て | 格子状の支柱に這わせる 壁面装飾として美しい | 壁際やフェンス沿い |
| スタンダード仕立て | 1本の支柱に這わせ傘状に垂らす 高さを出せる | 庭の目玉として |
支柱は成長を見越して、適切な長さと太さを選びます。ノウゼンカズラは10mほどまで育つこともあるため、しっかりした強度が必要です。つるは明るい方向に伸びるので、伸びる方向を考えて支柱を立てましょう。
育て方の基本
植え付けの適期は、暖かくなる3月中旬から4月中旬です。
| 項目 | 方法 |
|---|---|
| 水やり | 土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷり与える 開花時は乾燥しすぎないよう注意 |
| 肥料 | 2月に寒肥として油かすや緩効性化成肥料を施す 4月~5月にも追肥 |
| 置き場所 | 日当たりが良く風通しの良い場所 日陰では花付きが悪くなる |
| 冬越し | やや乾燥気味に管理 マイナス5℃以上なら屋外でも越冬可能 |
挿し木での増やし方
ノウゼンカズラは挿し木で簡単に増やすことができます。前年に伸びた枝を3月から4月に15cmから20cm切り、鉢に挿します。切り口を1時間ほど水につけておくと根が出やすくなります。
種からの栽培方法
花後にできる実から種を採取することもできます。ただし、一般的には種は出回っておらず、挿し木の方が確実で早く育ちます。種から育てる場合は、発芽まで時間がかかり、花が咲くまでに数年かかることもあります。
葉っぱの状態チェックポイント
健康な株を選ぶポイントとして、葉の色が濃い緑色で、幹がしっかりと太いものを選びましょう。つるの先が萎れていたり、葉が黄色くなっている株は元気がないので避けてください。
育てている間も、葉っぱの状態を定期的にチェックしましょう。新芽にアブラムシがつくことがあり、放置するとすす病を誘発することがあります。木酢酢や薬剤を薄めた液を散布すると予防できます。
鉢植えの場合も、剪定後に根を一回り小さく切って植え直すことで、管理しやすいサイズを維持できます。毎年落葉期に、太い枝の芽を3から4個残し、他のつるはばっさりと剪定しましょう。
切り花として室内で鑑賞する
ノウゼンカズラは切り花としても楽しめます。ただし、1日花であるため、一つの花の寿命は短いのが特徴です。
切り花として楽しむ際のポイントをご紹介します。
切り花にする際の注意点
花の蜜に毒性成分が含まれているため、切り花にする際は必ず手袋を着用しましょう。特に、肌が弱い方やアレルギー体質の方は注意が必要です。
長持ちさせるコツ
ノウゼンカズラは花の少ない真夏に咲く貴重な花です。切り花として室内で楽しむことで、暑い季節に涼やかな雰囲気を演出できます。
ノウゼンカズラの種類や似た花を知る
ノウゼンカズラには複数の種類があり、それぞれに特徴があります。また、似た花との見分け方を知っておくことも大切です。
主な品種・種類
| 種類 | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| ノウゼンカズラ (中国原産) | 花筒が短く広がりのある花 オレンジ色が一般的 | 最も一般的な品種 花付きが良い |
| アメリカノウゼンカズラ | 花筒が長く細長い花 赤みが強いオレンジ色 小ぶりな花 | 育てやすい 花色が濃い |
| マダム・ガレン | ノウゼンカズラとアメリカノウゼンカズラの交配種 紅オレンジ色の花 | 生育旺盛 育てやすい |
| タカラヅカゴールド | 黄色の花が特徴 | 火を連想させる色を避けたい方に |
| オランジュタカラヅカ | 黄色の花に赤い花脈 模様がユニーク | 観賞価値が高い |
| ピンクノウゼンカズラ | ポドラネア属 ピンク色の花 寒さに弱い | 鉢植え向き 珍しい色 |
似た花との見分け方
ノウゼンカズラに似た花として、キダチチョウセンアサガオがあります。ただし、両者は全く異なる植物です。
キダチチョウセンアサガオは実際に猛毒を持つ植物ですが、葉の形も樹形も葉の大きさも、さらには花の大きさもノウゼンカズラとは全く異なります。昔、この2つが混同されたことが、ノウゼンカズラに強毒があるという迷信が広まった一因ではないかという説もあります。
よくある質問
Q1. ノウゼンカズラに風水効果はありますか?
風水的には、ノウゼンカズラは人気運を上昇させる効果があるとされています。つる性植物が上に伸びていく様子は、運気の上昇を象徴するという解釈もあります。ただし、植える場所や方角については、気になる方は風水の専門家に相談することをおすすめします。
Q2. アジサイも植えてはいけないと聞きますが、理由は同じですか?
アジサイが植えてはいけないと言われる理由は、ノウゼンカズラとは異なります。アジサイの場合は、花の色が青から紫、ピンクへと変化することから「移り気」「浮気」といったネガティブなイメージを持たれることがあります。また、根に毒性があることも理由の一つです。しかし、実際にはどちらも適切に管理すれば問題なく育てられる植物です。
Q3. ノウゼンカズラの花言葉は本当に怖いのですか?
ノウゼンカズラの花言葉に怖い意味はありません。実際の花言葉は「名声」「名誉」「栄光」「豊富な愛情」「華のある人生」など、すべてポジティブな意味を持っています。花が一日で落ちることから打ち首を連想し、縁起が悪いとされることがありますが、これは花言葉とは別の話です。
Q4. すでに庭に植えてしまった場合はどうすればいいですか?
すでに地植えしている場合は、以下の対策を取りましょう。
管理が難しい場合は、専門の庭木業者に相談することも検討しましょう。
まとめ
- ノウゼンカズラにはラパコールという成分が含まれているが、失明するほどの強毒性はない
- 人によってはかぶれやアレルギー反応を起こす可能性があるため、手袋を着用して扱う
- 縁起が悪いとされる理由は花の色や落ち方に関する迷信だが、実際の花言葉はポジティブ
- 地下茎で勝手に増殖し、隣家にまで侵入することがある
- 気根が建物の外壁に張り付き、剥がすのが困難で外壁を傷める可能性がある
- 一度植えると完全に駆除するのが非常に難しく、繰り返しの作業が必要
- 他の植物に絡みついて日光を遮り、枯らしてしまうこともある
- 剪定は12月から3月の落葉期に行うのが最適で、年1回以上必要
- 放置すると電線や隣家にまで伸びて大きなトラブルになる
- 鉢植えで育てれば地下茎の広がりを制限でき、管理がしやすくなる
- 支柱の立て方を工夫すれば、あんどん仕立てやトレリス仕立てなど様々な楽しみ方ができる
- 挿し木で簡単に増やすことができ、切り口を水につけておくと根が出やすい
- 切り花としても楽しめるが、1日花のため寿命は短い
- アメリカノウゼンカズラやマダム・ガレンなど複数の品種があり、それぞれ特徴が異なる
- 風水的には人気運を上昇させる効果があるとされている
ノウゼンカズラを植えてはいけないと言われる理由は、主に繁殖力の強さと管理の難しさにあります。しかし、これらのリスクを理解し、適切な対策を取れば、美しい花を安全に楽しむことができます。鉢植えでの栽培や定期的な剪定など、管理方法を工夫しながら、夏の庭を彩る魅力的な花として付き合っていきましょう。