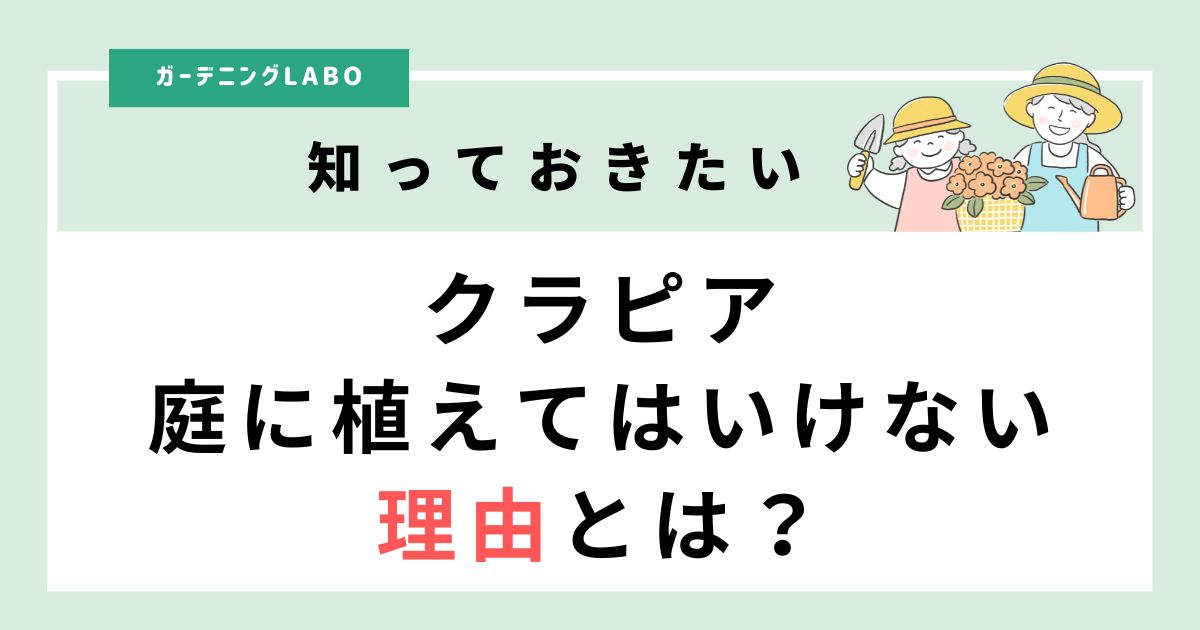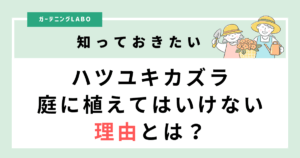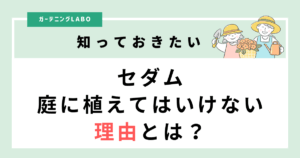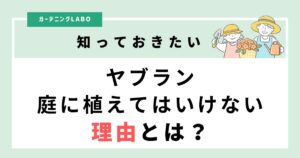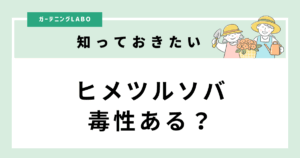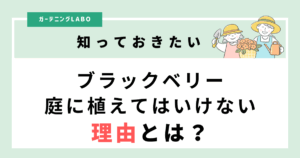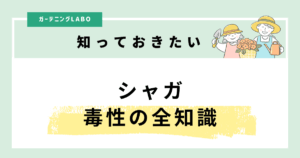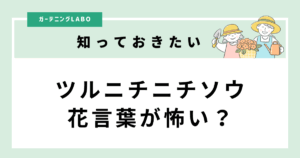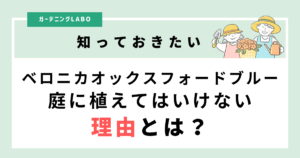クラピアを庭のグランドカバーに検討しているけれど、植えてはいけないという噂を聞いて不安になっていませんか。
クラピアは芝生の約10倍の速度で広がる魅力的な植物ですが、植える前に知っておくべきデメリットや注意点があります。実際にクラピアを植えた人の中には、夏の高温で黄色く枯れたり、梅雨時の過湿で根腐れを起こしたり、予想以上に虫が集まって後悔したという声も少なくありません。
また、芝生とどっちを選ぶべきか悩んでいる方や、種まきで増やせるのか、雑草だらけになったらどうすればよいのか、やめたいと思ったときに簡単に除去できるのかなど、気になる疑問も多いでしょう。
毒性の有無や植える時期、正しい植え方や増やし方、枯れた場合の対処法まで、クラピアに関する情報は知っておきたいことが山ほどあります。
- クラピアを植えてはいけない7つの理由とそれぞれの対策方法が分かる
- 芝生とクラピアの違いを理解し自分に合った選択ができるようになる
- 後悔しないための正しい植え方と管理方法を学べる
- クラピアが適した環境と適さない環境の見極め方が分かる
クラピアを植えてはいけないと言われる7つの理由

繁殖力が強すぎて制御不能になる恐れがある
クラピアの最大の魅力でもあり、同時に最大のデメリットとなるのが、その旺盛な繁殖力です。芝生の約10倍の速度で広がるとされており、わずか数株植えただけでも、あっという間に庭全体を覆い尽くしてしまいます。
隣家への侵入トラブルが発生する可能性
クラピアは地面を這うように伸びるランナー(匍匐茎)で増殖します。このランナーは想像以上に長く伸び、フェンスの下や境界線を越えて隣家の敷地に侵入してしまうケースが報告されています。
ネット上の口コミによると、管理を怠ったために隣家の庭までクラピアが広がってしまい、近隣トラブルに発展した事例もあるようです。定期的な刈り込みや、境界部分での物理的な遮断対策が必要不可欠となります。
雑草だらけよりも厄介な状態になることも
皮肉なことに、雑草対策として植えたクラピアが、雑草以上に手に負えない存在になってしまうこともあります。特に花壇や菜園など、他の植物を育てているエリアにクラピアが侵入すると、栽培している植物を駆逐してしまう危険性があります。
コンクリートの隙間やアスファルトの割れ目にも入り込み、放置すると建物の基礎周りや駐車場まで緑化してしまうケースもあります。
やめたいと思っても簡単には除去できない
一度定着したクラピアを完全に除去するのは容易ではありません。地下茎が土中深くまで張り巡らされているため、地上部を刈り取っただけでは再生してきます。根気よく除草作業を続ける必要があり、完全に取り除くには数年かかることもあります。
植える前に、本当にその場所にクラピアが必要か、将来的にデザインを変更する可能性はないか、しっかり検討しましょう。
夏の高温で下葉が黄色く枯れてしまう
クラピアは暑さに強いイメージがありますが、実は気温が35度を超えるような猛暑日が続くと、下葉が黄色く変色して枯れてしまうことがあります。特に日当たりが良すぎる場所では、この現象が顕著に現れます。
知恵袋で報告された実際の被害事例
Yahoo!知恵袋では、愛知県でクラピアを植えた方からこのような相談が寄せられています。
今年の春にクラピアを地植えしたが、夏に下葉が黄色くなってしまった。調べてみると暑すぎたようだが、家の作り上日陰は用意できない場所。何年もたって慣れてくれば黄色くならなくなるのか
この相談からも分かるように、植栽環境によっては高温障害を避けられない場合があります。
日陰が作れない場所での失敗パターン
南向きの庭や、終日日が当たる場所にクラピアを植えると、真夏の強烈な日差しと高温でダメージを受けやすくなります。特に建物の反射熱が加わる場所では、地表温度が50度を超えることもあり、クラピアにとって過酷な環境となります。
残念ながら、環境に慣れれば改善するというものではなく、その場所の気候条件が根本的に合っていない可能性が高いと言えます。
| 気温条件 | クラピアの状態 | 対策 |
|---|---|---|
| 25〜30度 | 最も生育が旺盛 | 定期的な水やりのみ |
| 30〜35度 | 生育は良好だがストレス | 朝夕の水やり推奨 |
| 35度以上 | 下葉の黄変・生育停滞 | 日陰作りまたは避けるべき |
| 10度以下 | 休眠期に入る | 冬季管理が必要 |
梅雨時のジメジメで根腐れ・枯死のリスクがある
クラピアは乾燥に強い一方で、過湿には非常に弱い植物です。梅雨の長雨や台風後の高湿度状態が続くと、根腐れを起こして枯れてしまうことがあります。
台風後の急な日差しでダメージが拡大
Yahoo!知恵袋の相談事例では、こんな被害が報告されています。
台風でジメジメが続いたためか、ランナーの先端10センチくらいずつを残して傷んでしまい、台風翌日の晴れの日差しで茶色く枯れてしまった。ランナー自体も枯れて切断してしまった
長雨で根がダメージを受けている状態で、急に強い日差しを浴びると、水分の吸い上げが間に合わず一気に枯れ込んでしまうのです。
水はけの悪い土壌での失敗パターン
粘土質の土壌や、雨水が溜まりやすい低地にクラピアを植えると、梅雨時期に根腐れのリスクが高まります。特に植えたばかりで根がまだ十分に張っていない段階では、過湿に対する抵抗力が弱く、簡単に枯れてしまいます。
クラピアの原種であるイワダレソウは海岸沿いで自生していた植物です。そのため、水はけの良い砂質土壌を好み、水が停滞するような環境は苦手としています。
植える前に土壌改良を行い、腐葉土や堆肥を混ぜ込んで排水性を高めておくことが重要です。
予想以上に害虫が発生して無農薬栽培が困難
クラピアは花を咲かせるため、ミツバチなどの有益な昆虫も集まりますが、同時に様々な害虫も引き寄せてしまうという大きなデメリットがあります。
ネキリムシによるランナー切断被害
Yahoo!知恵袋の相談では、最も深刻な被害としてネキリムシの存在が挙げられています。
無農薬にしたかったが、ネキリムシの被害があまりに多く断念。薬をまかなければすぐにランナー切断の嵐。バッタも葉を食べに来ており、害虫の被害が予想以上に多かった
ネキリムシは地際部分を食害する害虫で、クラピアの茎を切断してしまいます。一晩で広範囲のランナーが切られてしまうこともあり、放置すると壊滅的なダメージを受けます。
その他の害虫と対策
ネキリムシ以外にも、以下のような害虫が発生します。
| 害虫名 | 被害内容 | 発生時期 |
|---|---|---|
| ネキリムシ | 茎の切断 | 春〜秋 |
| バッタ | 葉の食害 | 夏〜秋 |
| コガネムシ幼虫 | 根の食害 | 通年(土中) |
| アブラムシ | 吸汁・ウイルス媒介 | 春〜初夏 |
| ヨトウムシ | 葉の食害 | 春・秋 |
また、花が咲く時期にはミツバチだけでなく、アシナガバチやスズメバチなども蜜を求めて飛来します。虫が苦手な方や小さなお子さんがいるご家庭では、特に注意が必要です。
芝生と比較した時の意外なデメリット
クラピアは芝生の代替として注目されていますが、実際に比較すると意外なデメリットも見えてきます。
芝生とクラピアどっちを選ぶべきか
| 比較項目 | クラピア | 芝生 |
|---|---|---|
| 刈り込み頻度 | 年1〜2回 | 月2〜4回 |
| 成長速度 | 非常に速い | ゆっくり |
| 踏圧耐性 | 強い(適度な範囲) | 非常に強い |
| 冬の見た目 | 枯れて茶色 | 品種により緑維持 |
| 初期コスト | 高い | 比較的安い |
| 花の有無 | あり(虫が集まる) | なし |
| 景観 | 自然で無造作 | 整然として洗練 |
踏圧への弱さと禿げやすさ
クラピアは踏圧に強いとされていますが、芝生ほどではありません。特に同じ場所を毎日のように踏み続けると、その部分だけ禿げてしまうことがあります。
ニチノー緑化の評価によると、1日当たり20人程度通行する踏圧の負荷には十分耐えるものの、日本芝のように多目的広場に使える程の強さはないとされています。
子供の遊び場や頻繁に人が通る動線上では、クラピアよりも芝生の方が適している場合があります。
冬の枯れ色が目立つ問題
クラピアは気温が10度を下回ると休眠期に入り、葉が枯れて茶色くなります。常緑の西洋芝と比べると、冬場の景観は著しく劣ります。
一年中緑の庭を維持したい方にとっては、この点が大きなデメリットとなります。

芝生の方がよかったかもと後悔する人も実際にいるんですね
植え方を間違えると取り返しのつかない後悔に
クラピアは比較的育てやすい植物ですが、植え方を間違えると定着せず枯れてしまうリスクがあります。
植える時期を間違えた失敗例
クラピアを植えるのに最適な時期は、桜の花が終わり八重桜が咲く頃とされています。具体的には4月下旬から9月頃までが植栽適期で、特に6〜8月が最適期です。
真冬や晩秋に植えると、根付く前に霜や急激な気温変化で枯死するリスクが高まります。また、真夏の炎天下も水分蒸発が激しく、植え付けには適していません。
土壌改良を怠った結果
クラピアは酸性からアルカリ性まで広い範囲の土壌に適応できますが、極端な粘土質や砂質の土壌では土壌改良が必須です。
日光種苗株式会社の製品情報によると、真砂土、粘土、砂地の場合は腐葉土や完熟堆肥を混ぜ込み、保水性と排水性を向上させる必要があるとされています。
この土壌改良を怠ると、水はけが悪くて根腐れを起こしたり、逆に水持ちが悪くて乾燥しすぎたりして、クラピアが健全に育ちません。
種からの育成が難しい理由
クラピアは種をつけない不稔性に品種改良されているため、種まきで増やすことはできません。市販されているのはすべてポット苗です。
ネット上で種として販売されているものは、外来種のヒメイワダレソウである可能性が高く、これは環境省の生態系被害防止外来種リストに指定されている植物です。間違って植えないよう注意が必要です。
クラピアは種苗法に基づき品種登録されています。メルカリやヤフオクなどで無許可販売されているものを購入するのは違法となる場合がありますので、必ず正規の販売店から購入しましょう。
毒性はないが一度植えると完全除去が困難
クラピアに毒性はなく、ペットや小さな子供がいる家庭でも安心して植えることができます。しかし、一度植えると完全に除去するのが非常に困難という大きな問題があります。
地下茎が残って再生する仕組み
クラピアは地上部を刈り取っても、土中に残った地下茎や根から再生してきます。完全に除去するには、スコップで根ごと掘り起こす作業を繰り返す必要があります。
広範囲に植えた場合、この作業は想像以上に大変で、完全除去には数年かかることもあります。
除草剤の使用方法と注意点
グリホサート系の除草剤(ラウンドアップなど)を使用することで、クラピアを枯らすことは可能です。ただし、周囲の植物も枯れてしまうため、慎重に使用する必要があります。
また、一度の散布では完全に枯れないことも多く、何度も繰り返し処理が必要となります。
クラピアを植えてはいけない場所・植えても大丈夫な場所の見極め方


クラピアに適した環境と正しい植え方・増やし方
デメリットばかり述べてきましたが、適切な環境で正しく管理すれば、クラピアは素晴らしいグランドカバーになります。ここでは成功のポイントをお伝えします。
クラピアに適した環境
出光テクノマルシェの公式情報によると、クラピアは日光を好む植物ですので、日当たりの良い場所を選ぶことが重要です。
| 条件 | 適している | 適していない |
|---|---|---|
| 日照時間 | 1日5時間以上 | 1日3時間未満 |
| 水はけ | 良好な排水性 | 水が溜まる低地 |
| 土壌 | 腐葉土混合の普通土 | 硬い粘土質・純粋な砂地 |
| 気温 | 最低気温-10度以上 | -10度を下回る寒冷地 |
| 管理 | 定期的な手入れができる | 完全放置したい |
正しい植え方の手順
クラピアを成功させるための植え方を順を追って説明します。
1. 雑草の除去と土壌準備
植栽前に雑草を完全に除草してください。土壌が固まっている場合は表層15センチ程度を耕起します。
2. 土壌改良
粘性土や砂質土の場合は、腐葉土や完熟堆肥を混ぜ込みます。
3. 元肥の施肥
緩効性肥料を土に混ぜ込みます。1株あたり6グラム程度が目安です。
4. 植え付け
深さ12センチ以上の穴を掘り、株間25〜50センチで植え付けます。苗が土から浮かないようやや深めに植え、周りの土をしっかり寄せて密着させます。
5. 踏み固め
植え付け後は靴で地面に押し付けるように踏みます。これにより根の付きが良くなります。
6. 水やり
植え付け直後から2〜3週間は、土が乾いたらたっぷり水をやります。
増やし方のコツ
クラピアは種まきではなく、ランナーを利用した栄養繁殖で増やします。
ただし、クラピアは種苗法で保護されているため、自分の敷地内であっても別の場所に移植することは法律で禁じられています。必要な分は最初から購入する計画を立てましょう。
クラピアが全面被覆するまでの期間は約2ヶ月とされていますが、植栽時期、温度条件、日照条件により異なります。春植えが最も成長が早く、秋植えは翌年の本格的な広がりを待つことになります。
植えてよかった人の成功事例
適切な環境で管理している人からは、植えてよかったグランドカバーとして高い評価を得ています。
成功している人の共通点は以下の通りです。
・日当たりが良好な場所に植えている
1日5時間以上の日照が確保できる南向きや東向きの庭で成功しています。
・土壌改良をしっかり行っている
植える前に腐葉土や堆肥を混ぜ込み、排水性を高めています。
・定期的な管理を楽しめている
年1〜2回の刈り込み、追肥、雑草取りを苦にせず、むしろ庭仕事として楽しんでいます。
・適度に踏んでいる
通路として利用することで、適度な踏圧がかかり、より密なマット状態を形成しています。
実際に育てている方のブログでは、芝生から切り替えて管理が楽になった、草取りの時間が大幅に減ったという声が多く見られます。



芝生の刈り込みは月2〜4回必要ですが、クラピアは年1〜2回で済むのは大きなメリットですね
また、5月から10月にかけて咲く白やピンクの可愛らしい花も、クラピアの魅力の一つです。緑の絨毯に小さな花がポツポツと咲く様子は、自然で無造作な印象を与え、ナチュラルガーデンを目指す方には最適です。
よくある質問
クラピアに関してよくある質問をまとめました。
Q1: クラピアは法律違反ですか?
クラピア自体を植えることは法律違反ではありません。クラピアは日本在来種のイワダレソウを品種改良したもので、環境省の生態系被害防止外来種リストにも入っていません。
ただし、クラピアは種苗法で品種登録されているため、権利者の許可なく増殖、販売、無償譲渡、海外への持ち出しをすることは種苗法違反となります。また、自分の土地であっても別の土地に移植することも法律で禁じられていますので注意が必要です。
Q2: クラピアの欠点は何ですか?
主な欠点は7つあります。繁殖力が強すぎて制御が難しい、夏の高温で黄変する、梅雨時に根腐れしやすい、害虫が多い、冬は枯れて茶色になる、一度植えると除去が困難、初期コストが高いことです。
Q3: 絶対に植えてはいけない庭木は?
クラピアは庭木ではなくグランドカバーですが、植えてはいけない植物として注意すべきなのは、環境省が指定する特定外来生物です。例えばオオキンケイギクなどは法律で栽培が禁止されています。
また、繁殖力が非常に強い外来種のヒメイワダレソウ(リッピア)は、生態系被害防止外来種リストの重点対策外来種に指定されており、公共事業では使用できません。クラピアと見た目が似ているため混同しないよう注意しましょう。
Q4: クラピアの寿命はどのくらいですか?
クラピアは多年草なので、適切に管理すれば5〜10年以上育ちます。ただし、年数が経つと株が老化して生育が衰えることがあるため、定期的な追肥や部分的な更新が必要です。
特に高温多湿の環境では病気が発生しやすく、寿命が短くなる傾向があります。
Q5: 種まきと苗、どちらがおすすめ?
クラピアは種をつけない不稔性に改良されているため、種まきでは育てられません。必ずポット苗を購入して植え付けてください。
種として販売されているものは、外来種のヒメイワダレソウである可能性が高いので注意が必要です。
まとめ
- クラピアは宇都宮大学で品種改良された日本在来種で法律違反ではない
- 繁殖力が強すぎて隣家への侵入トラブルが発生する可能性がある
- やめたいと思っても完全除去には数年かかることがある
- 夏の猛暑日が続くと下葉が黄色く枯れることがある
- 梅雨時の過湿で根腐れを起こして枯死するリスクがある
- ネキリムシやバッタなどの害虫被害が多く無農薬栽培は困難
- 芝生と比べて踏圧耐性は劣り禿げやすい
- 冬は休眠して葉が枯れ茶色くなる
- 毒性はないが地下茎が残って再生するため除去が困難
- 種まきはできず必ずポット苗を購入する必要がある
- 植える時期は4月下旬から9月で特に6月から8月が最適
- 植え方のコツは土壌改良と適切な株間での植え付け
- 増やし方はランナーを利用するが種苗法により移植は禁止
- 日照時間が1日5時間以上確保できる場所が適している
- 水はけの良い土壌が必須で粘土質や砂地は土壌改良が必要
- 年1から2回の刈り込みと追肥など定期的な管理が必要
- 芝生どっちを選ぶかは管理にかけられる時間と求める景観で判断
- 植えてよかったグランドカバーとして評価する人は適切な環境で管理している
- 雑草だらけになるのはクラピアが健全に育っていない証拠
- 後悔しないためには植える前に長期的な付き合いができるか検討することが重要