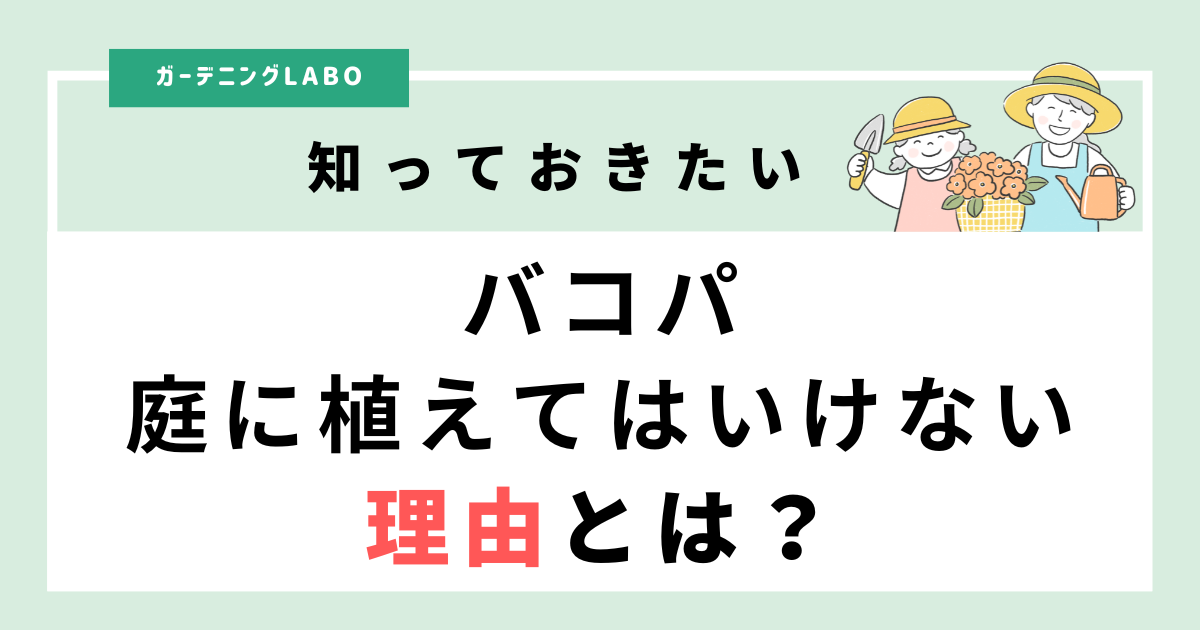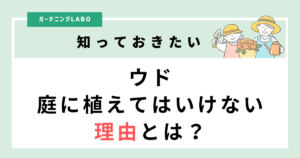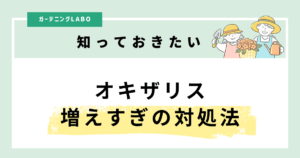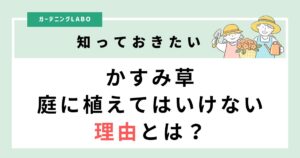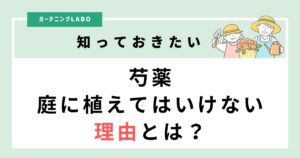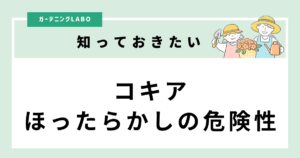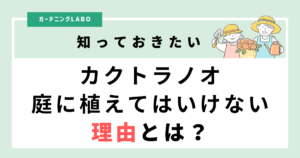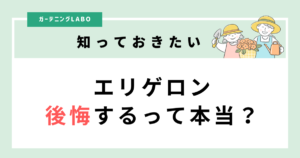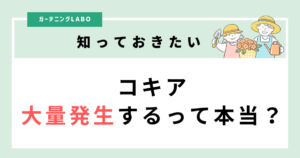バコパを植えてはいけないと言われる理由をご存知でしょうか。可愛らしい小花を咲かせるバコパですが、繁殖力の強さや高温多湿に弱い性質から、栽培に失敗してしまう方が少なくありません。庭に植えたら他の植物を覆い尽くしてしまったり、梅雨時期に蒸れて枯れてしまったりと、後悔する声も多く聞かれます。
しかし、適切な管理方法を知っていれば、バコパは初心者でも十分に育てられる魅力的な植物です。鉢植えで管理し、季節ごとのポイントを押さえることで、秋から春にかけて長期間、愛らしい花を楽しむことができます。この記事では、バコパを植えてはいけないと言われる具体的な原因と、それらを回避するための実践的な対処法を詳しく解説していきます。
- バコパを植えてはいけないと言われる5つの理由が分かる
- 繁殖力と蒸れのリスクを具体的に理解できる
- 季節ごとの正しい管理方法とコツを学べる
- 鉢植えでの育て方と挿し芽での増やし方をマスターできる
バコパを植えてはいけない原因|知っておきたい5つのリスク

| リスク | 発生時期 | 影響度 |
|---|---|---|
| 繁殖力が強い | 春〜秋 | ★★★ |
| 高温多湿に弱い | 梅雨〜夏 | ★★★ |
| 寒さに弱い | 冬 | ★★☆ |
| 木質化 | 通年 | ★★☆ |
| 害虫発生 | 春〜秋 | ★☆☆ |
バコパの特徴と基本情報
バコパは南アフリカやカナリア諸島を原産とする、オオバコ科ステラ属の多年草です。別名でステラとも呼ばれ、這うように横に広がる匍匐性の性質を持っています。直径1cm程度の小さな五弁花を次々と咲かせ、花色は白、ピンク、ラベンダーブルーなどがあります。
開花期間が非常に長く、秋から春にかけて連続して花を咲かせるため、寄せ植えやハンギングバスケットの素材として人気があります。茎がやわらかく枝垂れて育つ特性から、鉢の縁から垂らして育てるのに適しており、寄せ植えでは名脇役として活躍します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 学名 | Sutera |
| 科名 | オオバコ科ステラ属 |
| 原産地 | 南アフリカ、カナリア諸島 |
| 草丈 | 10〜20cm |
| 開花期 | 秋〜春(9月〜5月頃) |
| 花色 | 白、ピンク、紫 |
| 耐寒性 | やや強い(5℃以上) |
| 耐暑性 | 弱い |
| 花言葉 | 小さな強さ、心が和む、愛らしい |
繁殖力が強く広がりすぎる問題
匍匐性の茎がどんどん伸びる
バコパを植えてはいけないと言われる最大の理由は、その旺盛な繁殖力にあります。バコパは生育が非常に早く、横に這うように茎を伸ばす匍匐性の性質を持っているため、放置すると想像以上に広がってしまいます。
特に地植えにした場合、グランドカバーとして利用する目的であっても、管理できる範囲を超えて拡大し続けることがあります。挿し芽で簡単に増やせる性質も相まって、意図しない場所まで広がってしまい、庭全体の景観を損ねてしまう可能性があります。
他の植物を覆い尽くすリスク
繁殖力が強いことで、周囲の植物の生育スペースを奪ってしまうという深刻な問題が発生します。バコパの茎が他の植物に絡んだり、覆い被さったりすることで、周辺の植物が日光を十分に受けられなくなり、生育不良を起こすことがあります。
また、広がりすぎたバコパを管理するには、定期的な間引きや剪定が必要となり、手間が大幅に増えてしまいます。根詰まりを起こすと、水や栄養の吸収が悪くなるという問題も発生するため、注意が必要です。
地植えにする場合は、他の植物との距離を15〜20cm以上確保し、定期的な管理を前提に栽培計画を立てましょう。
高温多湿で蒸れて枯れやすい
日本の梅雨・夏に弱い性質
バコパは高温多湿に非常に弱いという性質があり、これが植えてはいけないと言われる二つ目の大きな理由です。特に日本の梅雨から夏にかけての時期は、バコパにとって過酷な環境となります。
バコパは乾燥には比較的強い一方で、湿気に極端に弱く、梅雨の時期には蒸れによって根腐れを起こすことが多いです。風通しの悪い場所では、株全体が黒ずんで枯れ込んでしまうこともあります。
蒸れが発生するメカニズム
蒸れが発生する主な原因は、茎や葉が密集することで株内部の風通しが悪くなり、湿気がこもってしまうことにあります。バコパは生育が旺盛で葉が茂りやすいため、特に注意が必要です。
その結果、葉が黄色く変色したり、根元から腐ってきたりして、最悪の場合は株全体が枯れてしまいます。雨に当たることで株元に泥が跳ね返り、さらに病気のリスクが高まることもあります。
| 時期 | リスク | 症状 |
|---|---|---|
| 梅雨(6月〜7月) | 長雨による蒸れ | 葉が黄色く変色、根腐れ |
| 夏(7月〜8月) | 高温多湿 | 株が黒ずむ、枯れ込み |
| 秋雨(9月〜10月) | 長雨と密植 | 風通し悪化、病気発生 |
梅雨入り前に切り戻しを行い、風通しを確保することが夏越し成功の鍵となります。
寒さに弱く冬越しが難しい
耐寒温度と霜害のリスク
バコパは多年草ですが、耐寒性には限界があり、5℃以下になると枯れてしまうリスクが高まります。霜や雪に当たると、一晩で株全体がダメージを受けることもあるため、冬場の管理には十分な注意が必要です。
常緑性の植物ではありますが、寒冷地では地上部が枯れてしまうこともあり、温暖な地域でも保護なしでは越冬が難しい場合があります。特に霜が降りる地域では、軒下や室内への移動が必須となります。
地域による栽培難易度の違い
バコパの栽培難易度は、お住まいの地域の気候によって大きく変わります。温暖な地域では比較的容易に越冬できますが、寒冷地では鉢植えにして冬は室内管理することが前提となります。
日本の気候に完全に適応しているとは言えない側面があり、夏の暑さと冬の寒さの両方に対策が必要なため、初心者には管理が難しいと感じられることもあります。そのため、地植えではなく鉢植えで管理し、季節に応じて移動できる状態にしておくことが推奨されます。
木質化して見た目が悪くなる
成長に伴う茎の硬化
バコパを長期間栽培していると、茎の根元から徐々に木質化(硬くなる現象)が進行します。これは植物の成長に伴う自然な現象ですが、バコパの場合は特に顕著に現れます。
木質化が進むと、茎が茶色く硬くなり、可憐だった印象が損なわれてしまいます。また、木質化した部分からは新しい芽が出にくくなり、花付きも悪くなってしまうという問題があります。
老化による花付きの低下
木質化が進んだ株は、見た目の問題だけでなく、花が付きにくくなるという実質的なデメリットがあります。枯れ枝のような部分が目立つようになり、株全体の活力が低下します。
バコパは多年草ですが、日本の環境下では1〜2年で株を更新することが一般的です。挿し芽で簡単に増やせるため、木質化が目立つ前に新しい株に更新することで、常に美しい状態を保つことができます。
害虫が発生しやすい
アブラムシの被害と対策
バコパに最もよく発生する害虫はアブラムシです。アブラムシは新芽や葉の裏に群生し、植物の汁を吸って生育を阻害します。放置すると大量発生し、株全体が弱ってしまうことがあります。
アブラムシが発生しやすい条件として、風通しが悪い環境や、窒素肥料の与えすぎが挙げられます。特にバコパは葉が密集しやすいため、アブラムシにとって格好の住処となってしまいます。
早期発見と駆除の重要性
アブラムシは繁殖力が非常に強く、発見が遅れると瞬く間に増殖してしまいます。水やりの際などに定期的に葉の裏や新芽をチェックし、早期発見に努めることが重要です。
発見した場合は、少量であればテープや手で取り除き、大量発生している場合は水で洗い流すか、オルトランやベニカファインスプレーなどの殺虫剤を使用します。予防策として、風通しを良くし、肥料を控えめにすることが効果的です。
| 駆除方法 | 対応する被害レベル | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 手で取り除く | 少量発生 | 薬剤不要だが手間がかかる |
| 水で洗い流す | 中量発生 | 簡単だが完全除去は困難 |
| 粘着テープ | 少〜中量 | 確実だが時間がかかる |
| 殺虫剤使用 | 大量発生 | 効果的だが薬剤抵抗性リスクあり |
バコパ 植えてはいけない状況を回避する対処法

| 適切な管理のメリット | 管理不足のリスク |
|---|---|
| 長期間花を楽しめる 株を健康に保てる 害虫・病気を予防できる 美しい株姿を維持できる | 蒸れで枯れる 広がりすぎて管理困難 木質化が進む 害虫が大量発生 |
鉢植えで育てて広がりを管理する
バコパを植えてはいけない状況を回避する最も効果的な方法は、地植えではなく鉢植えで育てることです。鉢植えにすることで、繁殖力が旺盛なバコパの広がりを物理的に制限でき、管理がとても楽になります。
特にハンギングバスケットでの栽培がおすすめです。バコパは茎がやわらかく枝垂れる性質があるため、鉢の縁から垂らして育てると、その特性を活かした美しい姿を楽しめます。寄せ植えの端に配置して垂らすスタイルも人気があり、名脇役として他の花を引き立ててくれます。
鉢植えのもう一つの大きなメリットは、季節に応じて移動できることです。夏は半日陰へ、冬は霜の当たらない軒下や室内へと、最適な環境に移動させることで、夏越し・冬越しの成功率が格段に上がります。
| 栽培方法 | 管理のしやすさ | おすすめ度 |
|---|---|---|
| ハンギングバスケット | 移動可能・垂れる姿が美しい | ★★★ |
| 鉢植え | サイズ調整しやすい・移動可能 | ★★★ |
| 寄せ植え | 他の植物と組み合わせ可能 | ★★☆ |
| 地植え | 広がりすぎて管理が大変 | ★☆☆ |
鉢のサイズは5〜6号鉢(直径15〜18cm)程度が適しており、苗よりも一回り大きな鉢を選びましょう。
適切な置き場所と環境づくり
バコパを健康に育てるには、日当たりと風通しの良い場所を選ぶことが最も重要です。基本的には日当たりの良い屋外で管理しますが、季節によって最適な環境が変わるため、柔軟な対応が必要です。
春と秋は日当たりの良い場所に置き、たっぷりと日光を当てることで、花付きが良くなります。この時期はバコパにとって最も生育に適した環境となるため、積極的に日光浴をさせましょう。
夏場は高温と強い直射日光を避けるため、半日陰の涼しい場所に移動させます。特に西日が当たらない場所を選ぶことが重要です。また、梅雨時期から夏にかけては、雨に当てない工夫も必要です。軒下に置くか、雨の日は室内に一時的に移動させることで、蒸れによる枯れを防ぐことができます。
冬は霜に当てないように、日当たりの良い軒下や室内の明るい場所で管理します。5℃以上を保てる環境であれば、冬の間も次々と花を咲かせてくれます。
| 季節 | 置き場所 | 管理ポイント |
|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 日当たり良好な屋外 | 生育期・花がたくさん咲く |
| 梅雨(6月) | 軒下・雨を避ける | 蒸れ対策・切り戻し実施 |
| 夏(7〜8月) | 半日陰・涼しい場所 | 西日を避ける・風通し確保 |
| 秋(9〜11月) | 日当たり良好な屋外 | 再び開花期・肥料追加 |
| 冬(12〜2月) | 軒下・室内の明るい場所 | 5℃以上保つ・霜よけ |
剪定と切り戻しのタイミング
バコパを長く美しく育てるために、定期的な切り戻しは必須の作業です。切り戻しを怠ると、蒸れて枯れてしまったり、木質化が進んで花が付かなくなったりします。
切り戻しを行うタイミングは主に2回あります。1回目は梅雨入り前の5月下旬〜6月上旬で、夏の蒸れを防ぐために早めに刈り込みます。株全体の3分の1〜2分の1程度の高さまで大胆に切り戻すことで、風通しが格段に改善されます。
2回目は花が一通り咲き終わった後や、株姿が乱れてきたタイミングです。花が少なくなってきたら、思い切って切り戻すことで、再び新しい芽が出て、秋にまた美しい花を咲かせてくれます。
日常的な手入れとしては、枯れた花がらをこまめに摘み取ることも大切です。花がらを放置すると、そこから病気が発生することがあるため、見つけ次第取り除きましょう。また、伸びすぎた枝先を摘むことで分枝を促し、こんもりとした美しい株姿を保つことができます。
清潔な剪定バサミを用意し、切り口から病気が入らないようアルコール消毒をしておきます。
株全体の高さを元の3分の1〜2分の1程度まで、思い切って短く切り戻します。
株の内側の密集した枝も間引き、風通しを良くします。枯れた葉や茎も一緒に取り除きましょう。
切り戻し後は半日陰で養生させ、新芽が出てきたら徐々に日当たりの良い場所に戻します。
正しい水やりと肥料の与え方
バコパの水やりは、土が乾いたらたっぷりと与えるという基本を守ることが重要です。鉢植えの場合、土の表面が乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。
水やりの際は、株元に直接水をかけるようにし、葉や花に水がかからないよう注意します。泥の跳ね返りを防ぐことで、病気の発生リスクを減らすことができます。地植えの場合は、基本的に降雨に任せ、極端に乾燥する時期のみ水やりを行います。
冬場の水やりは、凍結を避けるため必ず朝のうちに行いましょう。夕方に水やりをすると、夜間に土が凍ってしまい、根が傷む原因となります。
肥料は2か月に1回程度、緩効性肥料を株元に施します。開花期間が長いため、定期的な追肥が美しい花を咲かせ続けるポイントです。液体肥料を使用する場合は、10日〜2週間に1回程度、規定量に薄めて与えます。ただし、肥料の与えすぎは根焼けやアブラムシ発生の原因となるため、控えめを心がけましょう。
| 管理項目 | 頻度・タイミング | 注意点 |
|---|---|---|
| 水やり(鉢植え) | 土が乾いたら | 株元に与え、葉にかけない |
| 水やり(地植え) | 乾燥期のみ | 基本は降雨に任せる |
| 冬の水やり | 朝のうちに | 夕方は凍結リスクあり |
| 緩効性肥料 | 2か月に1回 | 与えすぎに注意 |
| 液体肥料 | 10日〜2週間に1回 | 規定量に薄めて使用 |
窒素分の多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂って花付きが悪くなり、アブラムシも発生しやすくなります。
夏越しと冬越しの管理方法
バコパを長く育てるには、夏越しと冬越しの管理が最も重要です。この2つの難関を乗り越えることで、毎年美しい花を楽しむことができます。
夏越しのポイントは、梅雨入り前の早めの切り戻しです。5月下旬〜6月上旬に株全体を大胆に刈り込み、風通しを確保します。梅雨から夏にかけては、半日陰の涼しい場所に移動させ、雨に当てないようにします。軒下や室内での管理が理想的です。株を観察し、蒸れの兆候が見られたら、すぐに枯れた部分を取り除きましょう。
冬越しのポイントは、5℃以上の温度を保つことです。霜や雪に当たらないよう、軒下や室内の明るい場所に移動させます。寒冷地では室内管理が必須となります。適切に管理すれば、冬の間も花を咲かせ続けてくれます。地植えにしている場合は、冬前に掘り上げて鉢に植え替え、室内で管理する方法もあります。
| 時期 | 管理のポイント | 具体的な対策 |
|---|---|---|
| 夏越し | 蒸れ防止 | 早めの切り戻し・半日陰管理・雨よけ |
| 冬越し | 寒さ対策 | 5℃以上保つ・霜よけ・軒下または室内 |
| 梅雨対策 | 風通し確保 | 切り戻し実施・雨に当てない |
挿し芽で株を更新する方法
バコパは挿し芽で非常に簡単に増やすことができます。木質化が進んだ株や、老化して花付きが悪くなった株は、挿し芽で新しい株に更新することで、常に若々しい状態を保つことができます。
挿し芽の適期は3〜5月、または9〜10月の生育期です。元気な枝先を5〜7cm程度の長さで切り取り、下の方の葉を取り除きます。切り口を水に1時間ほど浸けて水揚げをした後、赤玉土や挿し芽用の土に挿します。
挿し芽後は明るい日陰で管理し、土が乾かないようにこまめに水やりをします。2〜3週間ほどで発根するので、根が十分に張ったら鉢に植え替えましょう。挿し芽で増やした若い株は、親株よりも生育が旺盛で花付きも良いため、定期的な株の更新がおすすめです。
元気な枝先を5〜7cm程度の長さで切り取り、下の方の葉を取り除きます。
切り口を水に1時間ほど浸けて、しっかりと水を吸わせます。
赤玉土(小粒)や挿し芽用の清潔な土に、切り口を2〜3cm程度挿し込みます。
直射日光を避けた明るい日陰に置き、土が乾かないようこまめに水やりをします。
2〜3週間で発根するので、根が十分に張ったら鉢や花壇に植え替えます。
よくある質問
- バコパは何年くらい育てられますか?
-
バコパは多年草ですが、日本の環境下では1〜2年で株が老化することが一般的です。ただし、挿し芽で定期的に株を更新すれば、何年でも楽しむことができます。木質化が目立ってきたら、新しい株に更新するタイミングです。
- バコパの花言葉は何ですか?
-
バコパの花言葉は「小さな強さ」「心が和む」「愛らしい」です。「小さな強さ」は、小さな草姿ながら丈夫で、茎をどんどん伸ばして小さな花を次々と咲かせることに由来しています。「心が和む」は、優しい色合いの可愛らしい花姿から付けられました。
- バコパは室内で育てられますか?
-
日当たりが十分に確保できる場所であれば、室内でも育てることができます。特に冬越しには室内管理が有効で、明るい窓辺で5℃以上を保てれば、冬の間も花を楽しめます。ただし、風通しの確保も重要なので、定期的に換気をしましょう。
- バコパと相性の良い寄せ植えの組み合わせは?
-
バコパは名脇役として、様々な植物と組み合わせることができます。同じく秋から春に開花するパンジー、ビオラ、アリッサムなどとの相性が良く、バコパを鉢の縁に配置して垂らすスタイルが人気です。日当たりと水やりの好みが似ている植物を選ぶことがポイントです。
- バコパに発生する病気はありますか?
-
バコパは高温多湿の環境で、うどんこ病や斑点病などが発生することがあります。特に密植して風通しが悪い状態では、病気が発生しやすくなります。予防には定期的な切り戻しで風通しを確保し、雨に当てないことが重要です。病気の葉を見つけたら、すぐに取り除いて処分しましょう。
バコパを植えてはいけないと言われる理由を理解して上手に育てよう
バコパを植えてはいけないと言われる理由と、それぞれの対処法について詳しく解説してきました。適切な管理方法を知っていれば、バコパは初心者でも十分に育てられる魅力的な植物です。
- 繁殖力が強く広がりすぎるため、地植えより鉢植えでの管理が適している
- 高温多湿に弱いため、梅雨前の切り戻しと夏の半日陰管理が重要
- 蒸れを防ぐには風通しの良い環境と、雨に当てない工夫が必要
- 5℃以下で枯れるため、冬は霜よけをして軒下や室内で管理する
- 木質化が進んだ株は挿し芽で更新することで若々しさを保てる
- アブラムシ対策には風通しを良くし、肥料は控えめにする
- ハンギングバスケットや寄せ植えの端に配置すると美しい姿を楽しめる
- 水やりは土が乾いたらたっぷりと、株元に与えて葉にかけない
- 肥料は2か月に1回の緩効性肥料、または10日〜2週間に1回の液肥
- 季節ごとに置き場所を変えることで、夏越し・冬越しが成功しやすくなる
- 定期的な切り戻しは蒸れ防止と美しい株姿の維持に必須
- 花言葉は「小さな強さ」「心が和む」で、可憐ながら丈夫な性質を表している
- 秋から春にかけて長期間開花するため、寄せ植えの名脇役として人気
- 挿し芽は3〜5月または9〜10月が適期で、2〜3週間で発根する
- 鉢植えなら移動が可能なため、環境に合わせた柔軟な管理ができる
バコパを植えてはいけないと言われる原因を理解し、適切な対処法を実践すれば、秋から春にかけて長期間、可愛らしい花を楽しむことができます。特に鉢植えで管理し、季節ごとのケアを丁寧に行うことが成功の秘訣です。ぜひこの記事を参考に、バコパ栽培にチャレンジしてみてください。