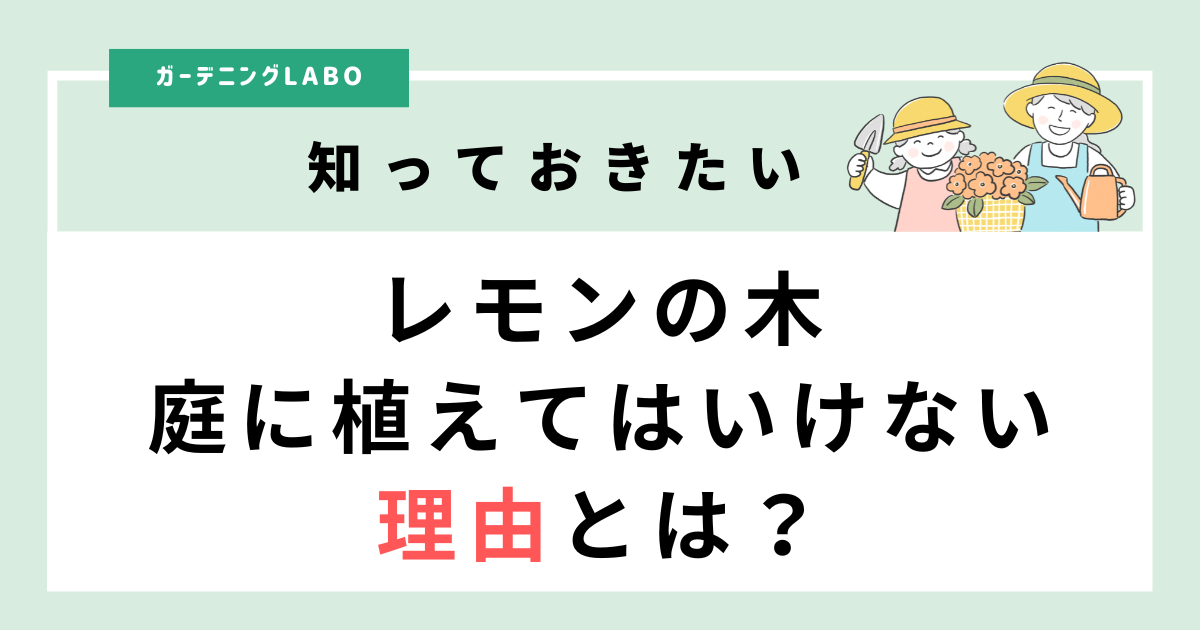レモンの木を庭に植えたいけれど、庭に植えてはいけないという声を聞いて不安になっていませんか。確かにレモンの木にはトゲがあったり実がつきにくかったりと、いくつかのデメリットが存在します。しかし、これだけは庭に植えてはいけない花草木に必ずしも該当するわけではなく、適切な知識と対策があれば家庭でも十分に育てられる魅力的な果樹なのです。
実のなる木を庭に植えてはいけないという風水的な考え方や、レモンの木を庭植えや鉢植えで育てる際の注意点、いつ植えるのが最適か、育て方や地植えの場所選び、方角の問題など、様々な疑問があるかもしれません。また、シンボルツリーとしてレモンの木を選んで後悔した人の声や、庭に植えてはいけない果物として風水でどう考えられているのか、オリーブの木と比較してどちらが良いのかなども気になるところでしょう。
この記事では、レモンの木を庭に植えてはいけないと言われる本当の理由を徹底的に解説し、それでも植えたい方のための実践的なアドバイスまでをご紹介します。レモンを植えるデメリットから、レモンの木が幸運を運んでくるという風水的な意味、レモンの木を庭のどこに植えれば良いのか、レモンの実がなるまで何年かかるのかといった疑問まで、あらゆる角度から解説していきます。
- レモンの木を庭に植えてはいけないと言われる7つの理由とデメリットを理解できる
- 鉢植えと庭植えのどちらが適しているか、それぞれのメリット・デメリットが分かる
- 地植えで成功させるための育て方のコツや植える時期・場所・方角が把握できる
- 風水的な意味や実がなるまでの年数など、よくある質問への回答が得られる
レモンの木を庭に植えてはいけないと言われる7つの理由とデメリット

「レモンの木を庭に植えてはいけない」と検索される本当の理由
レモンの木を庭に植えようと考えた時、多くの人が「レモンの木 庭に植えてはいけない」と検索しています。この背景には、レモンの木に対する憧れと不安が共存しているからです。
爽やかな香りと鮮やかな黄色い実が魅力的なレモンの木ですが、実際に植えた人の中には思わぬ問題に直面して後悔している方も少なくありません。実がほとんどならない、トゲで怪我をした、害虫に悩まされているなど、様々な悩みが寄せられています。
この記事では、レモンの木を植える前に知っておくべきデメリットと、それでも植えたい方のための実践的な対策をお伝えします
【最大の理由】花は咲くのに実がつかない問題
レモンの木を庭に植えてはいけないと言われる最大の理由が、花はたくさん咲くのに実がほとんどつかないという深刻な問題です。
10年で2個しか実らない現実
Yahoo!知恵袋には「レモンの木を庭に地植えして10年経つのに、その間2年目に1個、6年目に1個だけしか実がならなかった」という相談が寄せられています。花はいっぱい咲くのにポロポロと落ちて結実に至らず、水やりや肥料を工夫しても功を奏しないという状況です。
花が落ちる主な原因
| 原因 | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 受粉不良 | 高層階や風の通らない場所では虫による自然受粉が難しい | 筆で人工授粉する |
| 栄養過多 | 肥沃な土地では樹勢が強くなりすぎて実がつかない | 肥料を控えめにする |
| 水分管理の失敗 | 過度な水やりや水不足で花が落ちる | 土が乾いたらたっぷり水やり |
| 不完全花 | 雌しべがない不完全花には実がつかない | 完全花を見分けて大切にする |
実がなるまでの年数
レモンの苗木を植えてから実際に収穫できるまでには、通常3〜5年かかります。2年生や3年生の苗木を購入した場合でも、実際に実がつくのは植えてから3〜4年目と考えておくべきでしょう。
さらに注意が必要なのは、種から育てた場合です。種からレモンを育てると、花が咲くまでに10年近くかかることもあります。農家の方の事例では、16年間一切実をつけなかったレモンの木が、ある年を境に突然鈴なりになり始めたという報告もあります。
地植えと鉢植えでは結実率が大きく異なり、鉢植えの方が早く実がつく傾向があります。地植えは根が自由に伸びるため、木の成長に栄養が使われてしまい、実がつきにくくなるのです。
鋭いトゲによる怪我のリスク
レモンの木には1〜3cmにもなる鋭く硬いトゲが生えています。このトゲは想像以上に危険で、ちょっと触れただけでも深く刺さって怪我をすることがあります。
子どもやペットへの危険性
特に小さな子どもがいる家庭では、庭で遊んでいる際に不意にレモンの木のトゲに触れて大きな怪我をするリスクがあります。ペットも同様で、好奇心から近づいて怪我をする可能性があるため注意が必要です。
作業時の怪我
剪定作業や収穫、草むしりなどの庭作業中にもトゲで手や腕を傷つけてしまうことがあります。手袋を着用していても、鋭いトゲが貫通することもあるため、作業には十分な注意が必要です。
さらにトゲは、強風で揺れた際にレモンの葉や果実そのものを傷つける原因にもなります。その傷口から病原菌が侵入して「かいよう病」などを引き起こすこともあるため、トゲの存在は植物自身にとってもリスクとなる場合があります。
シンボルツリーには不向き
玄関先などにシンボルツリーとして植える場合、トゲがあることで美観を損ねるだけでなく、来客や家族の安全性にも問題が生じます。洗濯物を干す際に衣類がトゲに引っかかることもあり、日常生活での不便さを感じることになります。
病害虫の被害を受けやすい性質
レモンの木は、様々な病害虫の被害を受けやすいという大きなデメリットがあります。特に無農薬で育てたいと考えている方にとっては、大きな課題となります。
主な害虫
| 害虫名 | 被害内容 | 発生時期 |
|---|---|---|
| アゲハチョウの幼虫 | 新芽や葉を旺盛な食欲で食べ尽くし、木を弱らせる | 春〜秋 |
| アブラムシ | 新芽の樹液を吸い、大量発生すると新芽が枯れる | 春〜初夏 |
| カイガラムシ | 枝や葉に寄生して樹液を吸い、すす病を引き起こす | 年中 |
| ハダニ | 葉裏に寄生して葉を変色させ、光合成を阻害 | 乾燥する時期 |
| ミカンコミバエ | 果実に卵を産み付け、幼虫が果実内部を食害 | 夏〜秋 |
特にアゲハチョウの幼虫は、柑橘類を好物とするため、レモンの木には毎年のように産卵されます。一匹の幼虫が葉を数十枚も食べることがあり、放置すると木全体が丸裸になってしまうこともあります。
主な病気
害虫だけでなく、病気にもかかりやすいのがレモンの木の特徴です。
- かいよう病:葉や実に斑点ができ、果実の商品価値が下がる
- すす病:カイガラムシの排泄物が原因で葉が黒くなり、光合成ができなくなる
- うどん粉病:葉に白い粉状のカビが発生し、生育不良を引き起こす
近隣への影響
レモンの木についた害虫は、近隣の庭木にも広がりやすいという問題があります。特にアブラムシやカイガラムシは、風に乗って他の植物に移動するため、ご近所トラブルの原因になることもあります。
常緑樹なのに冬場の落葉で掃除が大変
レモンの木は常緑樹として知られていますが、実際には冬場に大量の葉が落ちるという意外な事実があります。
常緑樹とは一年中緑の葉を保つ木のことですが、これは「葉が全く落ちない」という意味ではありません。レモンの木も他の常緑樹と同様に、古い葉は徐々に黄変して落ちていきます。
特に冬場は、寒さのストレスや生理的な葉の入れ替わりによって、通常よりも多くの葉が落ちます。黄色く変色した葉が庭に散乱すると見た目が悪く、定期的な掃除が必要になります。
さらに落果の問題もあります。熟した果実が自然に落ちると、地面で潰れて周囲を汚してしまいます。また、落ちた実や葉に虫が集まってくることもあるため、衛生面でも注意が必要です。
隣家の敷地に葉や果実が落ちてトラブルになるケースもあるため、植える場所は慎重に選ぶ必要があります
シンボルツリーとして選んで後悔する人が多い理由
レモンの木をシンボルツリーとして選ぶ人は増えていますが、実際には期待と現実のギャップに後悔する人が多いという現実があります。
樹形が乱れやすい
レモンの木は自然な樹形が整いにくく、枝が不規則に伸びる傾向があります。シンボルツリーとして美しい見た目を維持するには、定期的な剪定が欠かせません。しかし剪定を怠ると、すぐに樹形が乱れて美観を損ねてしまいます。
オリーブの木などは自然に美しい樹形に育ちやすいのに対し、レモンの木は手入れをしないと雑然とした印象になりやすいのです。
実がならない失望感
シンボルツリーとしてレモンの木を選ぶ多くの人は、「家で収穫したレモンを使いたい」という期待を抱いています。しかし前述のように、実際には実がほとんどつかないケースが多く、この期待が裏切られた時の失望感は大きいものです。

実を期待してレモンの木を植えたのに、5年経っても全然実がつかない…こんなはずじゃなかった
トゲによる安全性の問題
玄関先など人通りの多い場所にシンボルツリーとして植えた場合、トゲによる怪我のリスクが高まります。特に小さな子どもがいる家庭では、シンボルツリーの近くで遊ぶことが多いため、危険性がさらに増します。
成功している人の条件
それでもレモンの木をシンボルツリーとして成功させている人もいます。そのような人には共通点があります。
- トゲなし品種を選んでいる
- 定期的な剪定と管理を楽しめる
- 実の収穫よりも樹形の美しさを重視している
- 温暖な地域に住んでいる
- 十分なスペースを確保している
実のなる木・果樹全般が庭に植えてはいけないと言われる共通理由
レモンだけでなく、実のなる木全般が「庭に植えてはいけない」と言われることがあります。これには果樹共通の問題があるためです。
管理の手間が大きい
果樹は観賞用の樹木と比べて、管理に多くの手間がかかります。
| 管理項目 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| 剪定 | 年1〜2回 | 樹形を整え、風通しを良くする |
| 施肥 | 年3〜4回 | 春・夏・秋・冬に適切な肥料を与える |
| 病害虫対策 | 常時 | 定期的な観察と早期対処 |
| 摘果 | 年1回 | 実を間引いて品質を高める |
落果による汚れと虫の発生
熟した果実が地面に落ちると潰れて腐敗し、悪臭を放つとともに、ハエやアリなどの虫を呼び寄せてしまいます。これは衛生面でも景観面でも大きな問題となります。
樹勢が強く成長管理が難しい
多くの果樹は樹勢が強く、放置すると大きくなりすぎて手に負えなくなります。レモンの木も地植えすると最大で6メートル程度まで成長する可能性があり、年間30センチメートルのペースで成長します。
大きくなりすぎた木は、剪定作業も困難になり、近隣への影響も懸念されます。建物や他の構造物から最低でも2メートル以上離して植える必要があり、根が基礎に到達して問題を引き起こすリスクもあります。
近隣トラブルのリスク
果樹を植えることで発生する可能性のある近隣トラブルには、以下のようなものがあります。
- 枝が隣家の敷地に越境する
- 落葉や落果が隣家の敷地を汚す
- 害虫が隣家の庭木に広がる
- 木が大きくなって日照を遮る
- 果実を狙って鳥が集まり、鳥のフンで周囲を汚す
風水で庭に植えてはいけない果物とされる理由
一部の風水では、実のなる木を庭に植えることを避けるべきとする考え方があります。ただし、これは迷信的な要素も強く、必ずしも科学的な根拠があるわけではありません。
「実割れ」が「身割れ」を連想させる
一部の地域や文化では、実のなる木は「実割れ」を連想させるため縁起が悪いとされています。この迷信は、実が割れることが家庭の不和や不幸を招くとされるためです。
特にザクロやイチジクなどの実が割れる果物が対象とされることが多いのですが、レモンも同様に考えられることがあります。ただし、レモンの果実自体は割れないため、この迷信を気にする必要は本来ありません。
陰陽バランスの考え方
風水における陰陽のバランスの観点から、果樹は「陰の気」が強いとされることがあります。庭に陰の気が強い木を植えると、家全体の気のバランスが崩れ、運気が低下するという考え方です。
しかし、これには反対の意見もあります。レモンの鮮やかな黄色い実は、風水では「金運」を象徴する色とされ、むしろ縁起が良いと考えられることも多いのです。
現代における風水の捉え方
現代では、風水の解釈も多様化しており、絶対的なルールというよりは、参考程度に考える人が増えています。
風水を気にする場合でも、適切な方角に植えることや、木の健康状態を良好に保つことの方が重要だとされています。枯れかけた木や病気の木は悪い気を発するため、これこそが運気を下げる要因になります。
結局のところ、風水的な観点よりも、実際の管理のしやすさや安全性、生活への影響を重視して判断するのが賢明でしょう。
これだけは庭に植えてはいけない花草木とレモンの比較
庭に植えてはいけない植物には、レモンの木よりもはるかに深刻な問題を持つものが存在します。レモンの木の位置づけを正しく理解するため、本当に避けるべき植物と比較してみましょう。
本当に避けるべき植物の特徴
| 特徴 | 具体例 | レモンとの比較 |
|---|---|---|
| 強い毒性がある | トリカブト、シキミ、ドクウツギ | レモンには毒性なし |
| 繁殖力が異常に強い | ミント、竹、ドクダミ | レモンは制御可能 |
| 根が建物を破壊する | 竹、ポプラ、イチジク(大木) | 適切に管理すれば問題なし |
| 花粉症の原因 | スギ、ヒノキ、ブタクサ | 花粉症のリスクは低い |
レモンの木の位置づけ
これらの本当に危険な植物と比較すると、レモンの木は「条件付きで栽培可能」という位置づけになります。
つまり、完全に避けるべき植物ではなく、デメリットを理解し適切に対処すれば、家庭でも十分に育てられる果樹なのです。
判断基準
レモンの木を植えるかどうかの判断基準は以下の通りです。
- 定期的な管理(剪定、害虫対策など)を楽しめるか
- 小さな子どもやペットがいる場合、トゲへの対策ができるか
- 実がつかない可能性を受け入れられるか
- 十分なスペース(最低2メートル以上)を確保できるか
- 温暖な気候の地域に住んでいるか、または冬の防寒対策ができるか
これらの条件をクリアできるのであれば、レモンの木は「植えてはいけない」植物ではなく、むしろ楽しみの多い魅力的な果樹となるでしょう。
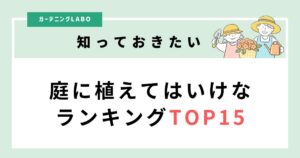
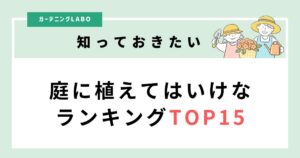
レモンの木を庭に植えてはいけない人・植えても大丈夫な人の違い


鉢植えと庭植え(地植え)どちらを選ぶべきか
レモンの木を育てる際、最初の重要な選択が鉢植えにするか地植えにするかという点です。それぞれにメリットとデメリットがあり、ご自身の状況に合わせて選ぶことが成功の鍵となります。
| 鉢植え | 地植え(庭植え) | |
|---|---|---|
| 管理のしやすさ | ◎ 移動可能、サイズ調整しやすい | △ 大きくなると管理が大変 |
| 結実率 | ◎ 早く実がつきやすい | △ 実がつくまで時間がかかる |
| 収穫量 | △ 少ない(年数個程度) | ○ 多い(数十個可能) |
| 水やりの手間 | × こまめに必要 | ◎ 基本的に不要 |
| 寒さ対策 | ◎ 室内に移動可能 | × 移動不可、防寒対策必須 |
| 植え替えの必要性 | △ 2年に1度必要 | ◎ 不要 |
| 初期費用 | △ 鉢・土が必要 | ○ 土壌改良程度 |
鉢植えなら、植えた1年目から収穫できることもあります。ただし収穫量は年に2〜3個程度と少なめです。一方、地植えは実がつくまで時間はかかりますが、木が大きく育てば毎年数十個の収穫も可能になります。



寒冷地に住んでいる方は、冬に室内に移動できる鉢植え一択です。地植えだと冬に枯れてしまう可能性が高いですからね
レモンの木を植える時期と場所・方角の選び方
レモンの木を植える時期と場所選びは、その後の成長を大きく左右する重要なポイントです。
植える時期はいつがベスト?
レモンの木の植え付けに最適な時期は、3月〜4月の春です。この時期は気温が穏やかで根が活発に成長するため、新しい環境への適応が容易になります。
秋(9月〜11月)も植え付け可能ですが、初心者の場合は寒くなっていく秋よりも、暖かくなっていく春の方が失敗が少ないためおすすめです。
日当たりの重要性
レモンの木は地中海原産の植物であり、1日6時間以上の日光を必要とします。日当たりが不足すると、果実の成長が遅くなるだけでなく、木そのものが弱くなり病害虫のリスクが高まります。
理想的なのは、南向きまたは南東向きの場所です。建物の陰になって午後の日光が当たらない場所や、北側の日陰になりやすい場所は避けるべきです。
風水を気にする場合の方角
風水の観点からレモンの木を植える方角を考える場合、いくつかの説があります。
- 南西:家庭の幸福と愛情を司る方角。金運アップも期待できる
- 東:成長と健康の象徴。子供の成長を促進するとされる
- 西:子供の運気を高める方角。金運や恋愛運にも良いとされる
- 南:家全体のエネルギーが活性化される
ただし、風水よりも実際の日当たりや風通しの良さを優先すべきです。いくら風水的に良い方角でも、日当たりが悪い場所では木が健康に育ちません。
地植えの場所選びのポイント
地植えする場合の場所選びで重要なポイントは以下の通りです。
- スペースの確保:建物や他の木から最低2メートル以上離す
- 水はけの良さ:水たまりができる場所は根腐れの原因になる
- 風通しの良さ:風通しが悪いと病害虫が発生しやすい
- 動線への配慮:人がよく通る場所はトゲによる怪我のリスクがある
- 隣家との距離:枝や根が越境しないよう配慮する
地植えで成功させる育て方のコツ
地植えでレモンの木を成功させるには、いくつかの重要なポイントがあります。
土壌改良
レモンの木は、排水性と保水性が良く、pH6.0〜6.5の弱酸性の土壌を好みます。
植え付け前には、以下の手順で土壌を改良しましょう。
- 40〜50cmの深さの植え穴を掘る(粘土質な土壌の場合は大きく深めに)
- 掘り出した土に、腐葉土や堆肥を3割程度混ぜる
- 赤玉土を2割程度混ぜて排水性を高める
- 化成肥料を1株あたり300g程度混ぜる
植え付け方法
苗木を植え付ける際は、接ぎ木部分が土に埋まらないように注意します。接ぎ木部分が地上に出るように高さを調整しながら、周囲に土を入れて固定しましょう。
植え付け後は、株元にぐるりと溝を切り、たっぷりと水やりをします。溝を埋めて株元に土寄せして盛り土の形にすれば完了です。
水やり管理
地植えの場合、基本的には自然の降雨で十分です。ただし、真夏の雨が少ない時期には、10日に1回程度たっぷりと水を与えましょう。
肥料の与え方
レモンは実つきが良く肥料食いなので、定期的な施肥が重要です。
| 時期 | 肥料の種類 | 目的 |
|---|---|---|
| 3月(春) | 有機質配合肥料または化成肥料 | 春の生育促進 |
| 6月(初夏) | 化成肥料 | 果実の成長サポート |
| 9月(秋) | 化成肥料 | 果実の充実 |
| 12〜1月(冬) | 有機質配合肥料(お礼肥) | 翌年の生育準備 |
肥料は株元から少し離れた場所に、直接根に触れないように施します。
剪定のタイミング
レモンの木の剪定は、年に1回、2〜3月の春先に行うのが基本です。常緑樹の剪定は、木全体の2割程度までに留め、切りすぎないよう注意しましょう。
剪定の目的は、樹形を整えることと風通しを良くすることです。特に、内側に向かって伸びている枝(内向枝)や、交差している枝を優先的に切り取ります。
寒冷地での防寒対策
レモンの木はマイナス3度以下になると枯れるリスクが高まります。寒冷地で地植えする場合は、以下の防寒対策が必須です。
- 株元にワラやバークチップを敷いてマルチング
- 木全体を不織布や保温シートで覆う
- 風よけのネットや囲いを設置
- 霜が降りる前に根元に土を盛る
温暖な地域(関東南部以西の沿岸地方)以外では、地植えよりも鉢植えにして冬場は室内に移動させる方が確実です。
受粉対策
レモンは自家結実性が高いため、基本的には1本だけでも実をつけます。ただし、より確実に結実させるためには、以下の対策が有効です。
- 人工授粉:筆で花の中心部を優しくなでて受粉を助ける
- 複数本植える:異なる品種を2本植えると結実率が上がる
- 昆虫を呼ぶ:受粉を助ける虫を引き寄せる植物を近くに植える
果実1個をならすのに必要な葉は約25枚と言われています。健康的に木を育てて葉をたくさんつけさせることが、結実への近道です。
よくある質問
Q1:レモンを植えるデメリットは?
レモンを植える主なデメリットは、実がつきにくい、鋭いトゲがある、病害虫に弱い、寒さに弱い、管理の手間がかかるという点です。特に地植えの場合、10年経っても数個しか実がつかないケースもあるため、実の収穫を期待しすぎると失望する可能性があります。
Q2:レモンの木は幸運を運んでくる?
風水では、レモンの鮮やかな黄色い果実が金運を象徴し、庭に植えることで運気を上げる効果があるとされています。また、レモンの木は浄化作用があり、家庭内の悪いエネルギーを取り除くとも言われています。ただし風水には様々な解釈があるため、あくまでも参考程度に考え、実際の育てやすさや安全性を優先して判断しましょう。
Q3:レモンの木を庭のどこに植えれば良いですか?
1日6時間以上日光が当たる、南向きまたは南東向きの場所が理想的です。水はけが良く風通しの良い場所を選び、建物や他の木から最低2メートル以上離して植えましょう。風水を気にする場合は、南西や東、西の方角が良いとされていますが、まずは日当たりと環境を優先すべきです。
Q4:レモンの実がなるまで何年かかりますか?
2年生や3年生の苗木を購入した場合、植えてから実際に実がつくのは3〜4年目が目安です。鉢植えの場合は早ければ1年目から収穫できることもありますが、地植えは時間がかかります。種から育てた場合は、花が咲くまでに10年以上かかることもあるため、早く実を楽しみたい方は苗木から育てることをおすすめします。
Q5:オリーブの木とレモンの木、どちらがおすすめ?
シンボルツリーとして美しい樹形を重視するならオリーブの木がおすすめです。オリーブは自然に樹形が整いやすく、寒さにも強く(マイナス10度前後まで耐えられる)、乾燥にも強いため管理が比較的楽です。一方、果実の収穫を楽しみたいならレモンの木が良いでしょう。ただし、レモンは管理の手間がかかり、寒さに弱いため、初心者にはオリーブの方が育てやすいと言えます。
レモンの木を植えてはいけない理由まとめ
- レモンの木は花は咲くのに実がつかない問題が最大のデメリット
- 地植えの場合、10年経っても数個しか実がつかないケースも多い
- 鋭いトゲがあり、子どもやペットがいる家庭では怪我のリスクがある
- アゲハチョウやアブラムシなど病害虫の被害を受けやすい
- 常緑樹でも冬場は落葉が多く掃除が大変
- シンボルツリーとして選ぶと樹形が乱れやすく後悔する人が多い
- 実のなる木全般に共通する管理の手間や近隣トラブルのリスクがある
- 風水では実割れが身割れを連想させ縁起が悪いとする説もある
- 毒性や繁殖力の問題がないため条件付きで栽培可能
- 初心者には管理しやすく結実率の高い鉢植えがおすすめ
- 植える時期は3月から4月の春が最適
- 1日6時間以上日光が当たる南向きまたは南東向きの場所を選ぶ
- マイナス3度以下になると枯れるため寒冷地では防寒対策が必須
- 苗木から育てると3〜4年目で実がつくが種からだと10年以上かかる
- トゲなし品種を選ぶことで安全性の問題を解決できる