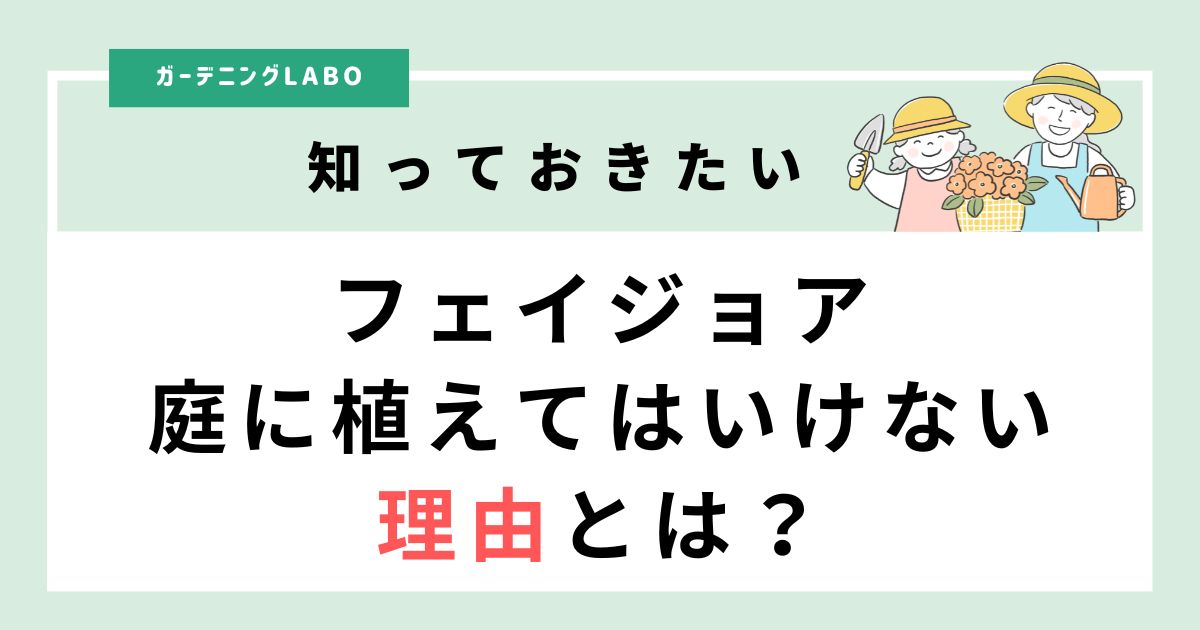おしゃれな庭のシンボルツリーとして、近年人気が高まっているフェイジョア。「エキゾチックな花が美しく、甘い香りの果実も楽しめるなんて素敵」と、お庭への仲間入りを検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、その魅力的な側面の裏で、「フェイジョアを庭に植えて後悔した」という声が聞かれるのも事実です。
成長が早くて大きくなりすぎたり、楽しみにしていた実が全くならないといった失敗談や、剪定が大変、害虫の心配など、事前に知っておくべきデメリットも存在します。また、数ある品種の中からどれを選べば良いのか、詳しい育て方や美味しい食べ方、さらには目隠しとしての活用法まで、植える前に解消しておきたい疑問は尽きないはずです。
せっかくお庭に迎えるのですから、後悔することなく、そのポテンシャルを最大限に引き出してあげたいもの。この記事では、園芸のプロが、フェイジョアを植えて後悔しがちな具体的な理由を深掘りし、同じ失敗を繰り返さないための、品種選びから剪定、病害虫対策に至るまで、あらゆる注意点と育て方のコツを徹底的に解説します。
- フェイジョアを庭に植えて後悔しがちな理由
- 後悔しないための具体的な対策や育て方のコツ
- シンボルツリーに向いている品種や正しい剪定方法
- 収穫したフェイジョアの美味しい食べ方や活用法
フェイジョアを庭に植えて後悔しがちな理由

| 後悔しがちな理由 | 対策の方向性 |
|---|---|
| 成長が早くて大きくなりすぎる | 植える場所の確保と適切な剪定 |
| 実がなりすぎたり、ならなかったり | 品種選びと受粉方法の理解 |
| 収穫や掃除の手間がかかる | 収穫方法と時期の把握 |
| 剪定など日々の手入れが大変 | 剪定時期と方法の習得 |
| 病気や育つ環境に注意が必要 | 病害虫対策と環境の確認 |
そもそもフェイジョアとは?
| 和名 | フェイジョア |
|---|---|
| 科名 | フトモモ科 |
| 原産地 | 南アメリカ(ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ、アルゼンチン) |
| 樹高 | 約3m~5m(剪定しない場合) |
| 開花時期 | 5月~6月 |
| 収穫時期 | 10月下旬~12月 |
| 特徴 | ・常緑で厚みのある葉を持つ ・病害虫に比較的強い ・花びらも食べられる(エディブルフラワー) ・果実はパイナップルとバナナを混ぜたような独特の風味 |
フェイジョアは、南米の温暖な地域を原産とするフトモモ科の常緑低木です。学名は「Feijoa sellowiana」。トロピカルで甘い芳香を放つ果実が有名ですが、初夏に咲く花も非常に個性的で美しく、庭木やシンボルツリーとしての観賞価値も高い植物です。
成長が早くて大きくなりすぎる
フェイジョアで後悔する最大の理由は、その旺盛な生命力と成長スピードにあります。「植えたときは膝丈くらいだったのに、2〜3年で自分の身長を軽々と超えてしまった」という話は決して珍しくありません。特に日当たりの良い場所に地植えした場合、放置すれば数年で2階の窓に届くほどの高さ(4〜5m)に達することもあります。

シンボルツリーのつもりが、いつの間にか家の主役級の存在感を放つ巨木になってしまい、「こんなはずでは…」と頭を抱える方が後を絶ちません。
地植えと鉢植えのサイズ感
フェイジョアは植える環境によって最終的な大きさをコントロールできます。管理の手間やスペースに不安がある場合は、鉢植えを選択したり、もともと大きくならないコンパクトな品種を選ぶのが賢明です。
| 栽培方法 | 樹高の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 地植え | 3~5m | 根が自由に張れるため成長が早く、管理には剪定が不可欠。広いスペースが必要。 |
| 鉢植え | 1~2m | 根の成長が制限されるため、サイズをコンパクトに保ちやすい。ベランダでも栽培可能。 |
| コンパクト品種(鉢) | 1m前後 | 「プリティーグリーン」など、もともと大きくならない品種なら、より管理が容易。 |
大きくなりすぎると何が問題?
木が大きくなりすぎると、見た目の問題だけでなく、様々な実害が発生し、後悔へとつながります。
高木化による三大トラブル
- 剪定の危険性と重労働化:脚立や高枝切り鋏が必要になり、作業の難易度と危険性が増します。バランスを崩して転倒するリスクも。
- 日照問題と越境トラブル:庭や室内、さらには隣家の敷地まで日陰にしてしまい、ご近所との関係悪化の原因になりかねません。落ち葉や枝の越境も問題です。
- 管理コストの増大:自力での管理が不可能になると、庭師や造園業者に剪定を依頼する必要が出てきます。年間の維持費が思わぬ出費になることも。
植え付け前に、その品種が最大でどれくらい大きくなるのかを調べ、メジャーなどを使って植栽予定地に立ち、数年後の樹高や枝の広がりを具体的にイメージすることが、後悔しないための重要なステップです。
実がなりすぎたり、ならなかったり
フェイジョア最大の魅力であるはずの「果実」も、時として後悔の原因になります。問題は「全く実がならない」という期待外れの悩みと、逆に「想像を絶するほど実がなりすぎて困る」という、嬉しい悲鳴を通り越した悩みの両極端に分かれます。
なぜ?フェイジョアの実がならない最大の原因
数年育てても一向に実がつく気配がない…その最も大きな原因は、フェイジョアが持つ「自家不和合性(じかふわごうせい)」という性質にあります。
自家不和合性とは?
植物が自分自身の花粉では受粉しても正常に種子ができず、実を結びにくい性質のことです。品質の良い子孫を残すための、植物が持つ賢い仕組みの一つです。
つまり、多くのフェイジョアは、1本植えただけでは実がなりにくいのです。実を安定して収穫するためには、遺伝的に相性の良い別の品種を「受粉樹」として近くに植え、互いの花粉が虫などによって行き来する環境を作る必要があります。
逆に、豊作すぎてパニックになるケースも
無事に結実の壁を乗り越えたとしても、次の問題が待ち構えている場合があります。それが「収穫過多」の問題です。特に樹齢が上がり、木が大きくなると、文字通り鈴なりに実をつけ、その数は数百個に及ぶこともあります。



毎日のようにボウルいっぱいの実が収穫できて、最初は喜んでいたものの、消費が全く追いつかない!ジャムにしてもスムージーにしても減らない!ご近所におすそ分けするのも限度がある…と、最終的には嬉しいはずの収穫がストレスになってしまうのです。
植える前に、収穫した実をどう活用するか、家族の消費量と照らし合わせて、本当に管理できる本数なのかを冷静に考えることが大切です。冷凍保存の方法や、ジャム、コンポート、果実酒といった加工レシピをあらかじめ調べておくと、いざという時に慌てずに済みます。
収穫や掃除の手間がかかる
フェイジョアの収穫は、他の果樹のように木になっている実をもぎ取るスタイルではありません。熟すと自然に地面にポトリと落ちる「自然落果」したものを拾い集めるのが基本の収穫方法です。このスタイルが、想像以上に日々の手間となり、後悔につながることがあります。
終わらない収穫と掃除のループ
収穫期である秋から初冬にかけて、フェイジョアはほぼ毎日、熟した実を落とします。これを放置すると、次のような問題が発生するため、こまめに拾い集める必要があります。
- 品質の劣化:地面に長時間あると、実が傷んだり、泥で汚れたりして食味が落ちる
- 害虫の発生源に:熟した果実はナメクジやアリ、コバエなどの害虫を庭に呼び寄せてしまう
- 景観の悪化:落ちて潰れた実や、腐りかけた実は衛生的にも見た目にも良くありません。
特に、木の周りが芝生や砂利、下草の生えたグランドカバーなど、複雑な地面になっていると、落ちた実が紛れてしまい、発見と回収が非常に困難になります。腰をかがめて一つひとつ拾う作業は、毎日のこととなると、足腰への負担も無視できません。
この手間を少しでも軽減するためには、植え付けの段階で、木の根元周りを平らな土やコンクリートにする、あるいは収穫期だけ防草シートや目の細かいネットを敷くといった工夫が非常に有効です。
剪定など日々の手入れが大変
「成長が早くて大きくなりすぎる」という問題と密接に関わるのが、日々のメンテナンス、特に「剪定」の手間です。フェイジョアの美しい樹形と適切なサイズを維持し、健全な生育を促すためには、定期的な剪定が絶対に欠かせません。この作業を負担に感じ、「こんなに大変だとは思わなかった」と後悔する方は少なくありません。
なぜ剪定をサボるとダメなのか?
「自然樹形が好きだから」と剪定を怠ると、見た目の問題だけでなく、様々なトラブルを引き起こします。
| 剪定しないデメリット |
|---|
| 暴走する樹形:枝が四方八方に伸び、管理不能な大きさになる 病害虫の温床に:枝が密集して風通しが悪くなり、カイガラムシなどの害虫が隠れる絶好の場所になる 収穫量の低下:木の内側まで日光が届かなくなり、花実がなっても品質が低下したりする 見栄えの悪化:枯れ枝や不要な枝が混み合い、清潔感のないボサボサの印象になってしまう |
フェイジョアは萌芽力(ほうがりょく:新しい芽を出す力)が非常に強く、剪定には比較的耐えることができる樹木です。しかし、だからといって何も考えずにバッサリ切ってしまうと、その年の、あるいは翌年の花芽ごと切り落としてしまい、「剪定したのに実がならない」という本末転倒な結果を招くこともあります。正しい知識に基づいた剪定が求められるのです。
病気や育つ環境に注意が必要
「フェイジョアは病害虫に強く、育てやすい」という情報は間違いではありませんが、それはあくまで「比較的」の話です。全くノーメンテナンスでOKというわけではなく、特定の病害虫には注意が必要ですし、そもそも日本のすべての地域で元気に育つわけではありません。
特に注意すべき病害虫「カイガラムシ」と「すす病」
フェイジョアで最も警戒すべき害虫が「カイガラムシ」です。成虫になると硬い殻や白い綿のような物質で体を覆うため、薬剤が効きにくくなる厄介な相手です。枝や葉にびっしりと付着し、樹液を吸って木を弱らせます。
さらに深刻なのが、カイガラムシの排泄物(甘露)を栄養にして繁殖する黒いカビ、「すす病」の二次被害です。葉や枝が黒いすすで覆われたようになり、見た目が著しく損なわれるだけでなく、光合成を妨げて生育不良を引き起こします。
耐寒性と土壌の適応性
フェイジョアは南米原産の亜熱帯果樹なので、基本的には温暖な気候を好みます。品種改良により耐寒性は向上しており、多くの品種がマイナス10℃程度まで耐えるとされていますが、これはあくまで一時的なものです。厳しい寒波が続いたり、頻繁に強い霜が降りたりする寒冷地では、地植えでの越冬は難しく、木が弱ったり、最悪の場合枯れてしまったりするリスクがあります。
また、土壌への適応性も重要です。フェイジョアは極端な乾燥や過湿を嫌います。特に水はけの悪い粘土質の土壌では、根が呼吸できずに「根腐れ」を起こしやすく、生育不良や枯死の原因となります。お庭の土壌が適しているかどうかの見極めも、後悔しないための大切なポイントです。
フェイジョアを庭に植える場合の注意点


| 後悔しないための注意点 | 具体的なアクション |
|---|---|
| 品種選びと植える場所 | 用途に合った品種を選び、日当たりとスペースを確保する |
| 受粉のコツ | 受粉樹を植えるか、1本で実がなる品種を選ぶ |
| 剪定方法 | 適切な時期に、正しい方法で剪定する |
| 病害虫対策 | 風通しを良くし、早期発見・早期対応を心がける |
品種選びと植える場所のポイント
フェイジョア栽培で後悔しないためには、すべての始まりである「品種選び」と「植える場所の選定」が最も重要です。この最初のステップであなたの目的や環境に最適な選択をすることが、将来の管理の手間を大きく左右します。
「何を重視するか」で決める品種選び
フェイジョアには100以上の品種があると言われ、日本国内で流通しているものだけでも数十種類に及びます。「実の味」「1本で実がなるか(自家結実性)」「樹形」など、あなたが何を最も重視するかで、選ぶべき品種は変わってきます。
| アポロ | クーリッジ | トライアンフ | ユニーク | |
|---|---|---|---|---|
| 自家結実性 | あり(不安定) | あり | なし | あり(強い) |
| 果実の大きさ | 大果 | 小~中果 | 中果 | 中果 |
| 味の特徴 | 甘みが強く、香りが非常に良い。生食に最適で人気No.1。 | 酸味があり、さっぱりとした味。加工向き。 | 甘みと酸味のバランスが良い優等生タイプ。 | ジューシーで食感が良い。名前の通り1本でよくなる。 |
| 樹形 | 開張性(横に広がりやすい) | 立性(上に伸びやすい) | やや開張性 | やや立性でコンパクト |
| おすすめの人 | 味を最優先したい人、広いスペースがある人 | 生垣など、縦方向に育てたい人 | 受粉樹として、バランスの取れた味を楽しみたい人 | 省スペースで確実に実を収穫したい初心者 |
植える場所で未来が決まる!3つの必須条件
一度地植えすると、場所の変更は容易ではありません。後から「こんなはずじゃなかった」とならないよう、以下の3つのポイントを必ず満たす場所を選んでください。
フェイジョアは日光が大好物です。最低でも半日以上、できれば一日中直射日光が当たる場所が理想。日照不足は、花付きや実付きが悪くなる最大の原因です。
根が常に湿った状態を嫌います。雨が降った後に水たまりができるような場所はNG。土を掘ってみて、粘土質で固い場合は、腐葉土やパーライトを混ぜ込んで土壌改良を行いましょう。
これが最も重要です。品種の最終樹高と枝の広がり(幅)を調べ、建物、塀、他の植栽、そして隣家の敷地から最低でも1.5〜2m以上の距離を確保してください。
確実に実をつけるための受粉のコツ
「何年も育てているのに、花は咲くけど実が一つもならない…」という後悔は、フェイジョア栽培で非常によくある失敗です。しかし、受粉のメカニズムを正しく理解し、少し手間をかけてあげるだけで、その悩みは解決できます。
基本戦略:相性の良い受粉樹を植える
最も確実で、長期的に安定した収穫をもたらす方法は、開花時期が重なる、相性の良い異なる2品種以上を近くに植えることです。フェイジョアの花粉は、主にヒヨドリなどの鳥や、ハナバチなどの昆虫によって運ばれます。彼らが活動しやすいよう、数メートル以内に植栽するのが理想的です。
- 王道の組み合わせ:「アポロ(大果・良食味)」×「トライアンフ(豊産性・バランス型)」
- 食味重視の組み合わせ:「アポロ」×「マンモス(大果・早生)」
- 省スペースの組み合わせ:「クーリッジ(自家結実性あり)」×「ユニーク(自家結実性あり)」
どの品種とどの品種の相性が良いかは、実績のある組み合わせが存在します。購入時に園芸店のスタッフに尋ねるか、信頼できる種苗メーカーのウェブサイトで確認するのが確実です。
奥の手:人の手で結ぶ「人工授粉」
「どうしても2本も植えるスペースがない」「今年こそは絶対に収穫したい」という切実な願いを叶える最終手段が「人工授粉」です。少し手間はかかりますが、これを行うことで、1本しかない木や、虫の活動が少ない都市部のベランダ栽培でも、結実率を劇的に高めることが可能です。
- 道具の準備:耳かきの梵天(ふわふわの部分)や、柔らかい化粧用の筆、綿棒などを用意する
- 花粉の採取:一方の品種(または同じ木でも別の花)の、赤いおしべの先端を筆で優しくなでて、花粉を採取する
- 受粉作業:花粉をつけた筆で、もう一方の品種(または別の花)の中心にある、一番長くて先端が少し開いているめしべの柱頭に、ちょんちょんと優しく花粉をつける
- タイミング:この作業は、花が咲いてから2〜3日以内の、よく晴れた風のない日の午前中に行うと成功率が高まる
異なる品種間で行うのが最も効果的ですが、自家結実性のある品種で、より確実に実をつけたい場合にも、同じ木の中で花から花へと花粉を移してあげることで、結実が促進されることがあります。
適切な木の大きさを保つ剪定方法
フェイジョア栽培の成否を分けると言っても過言ではない、最も重要な管理作業が「剪定」です。大きくなりすぎるのを防ぎ、風通しと日当たりを確保して病害虫を予防し、さらには品質の良い実を安定して収穫するために、正しい剪定方法をマスターしましょう。
剪定のベストタイミングは「春の芽吹き前」
フェイジョアの剪定に最適な時期は、本格的な成長が始まる前の3月〜4月の春先です。この時期に剪定を行うと、木へのダメージが少なく、剪定後すぐに新しい枝が伸び始め、樹勢を回復しやすいというメリットがあります。
その他の剪定時期
・花後の剪定(6月下旬〜7月):花が咲き終わった後、不要な枝を軽く整理する程度なら可能です。
・収穫後の剪定(12月〜1月):実の収穫が終わった後に行う剪定。ただし、厳寒期に太い枝を切ると、切り口から木が傷むことがあるため、温暖な地域以外では軽い剪定にとどめるのが無難です。
剪定の基本は「間引き」と「切り戻し」
フェイジョアの剪定は、主に2つの手法を組み合わせて行います。木の骨格を作り、健康な状態を保つための重要な作業です。
| 剪定方法 | 目的と内容 |
|---|---|
| 間引き剪定 | 風通しと日当たりの改善。混み合った枝を付け根から切り取る。木の内部まで光が届くようにする。 |
| 切り戻し剪定 | 木の大きさをコントロールする。長く伸びすぎた枝を、途中で切り詰めて短くする。 |
優先的に剪定すべき「忌み枝(いみえだ)」
- 内向枝:幹の中心に向かって伸びる枝
- 交差枝(絡み枝):他の枝と交差したり絡まったりしている枝
- 平行枝:すぐ近くで同じ方向に平行して伸びている枝(どちらか一方を剪定)
- 下垂枝(下がり枝):地面に向かって垂れ下がっている枝
- 徒長枝(とちょうし):他の枝より明らかに勢いよく、真上にまっすぐ伸びる枝
- ひこばえ:株元から生えてくる細い枝



剪定と聞くと難しく感じるかもしれませんが、まずはこれらの「忌み枝」を取り除くことから始めてみましょう。それだけでも、木全体の風通しが劇的に改善され、見た目もすっきりとします。一度に完璧を目指さず、毎年少しずつ、木の様子を見ながら理想の形に近づけていくのが成功のコツです。
剪定後の切り口には、病原菌の侵入を防ぐために「癒合剤(ゆごうざい)」を塗っておくと、より安心です。詳しい剪定方法については、造園技能士などの専門家が公開している情報も参考にすると良いでしょう。
病害虫の対策
フェイジョアは丈夫な樹木ですが、病害虫のリスクはゼロではありません。「植えてから一度も消毒しなかったら、木が真っ黒になってしまった」という後悔をしないためにも、予防を基本とし、万が一発生した際には迅速に対処することが重要です。
最大の敵「カイガラムシ」とその対策
フェイジョア栽培で最も注意すべき害虫は、繰り返しになりますが「カイガラムシ」です。この害虫の防除が、フェイジョアを健康に保つ最大のポイントと言えます 。
| 対策ステージ | 具体的な方法 |
|---|---|
| 予防 | 剪定が最大の予防策。風通しを良くして、湿気がこもらない環境を作る 。定期的に枝や葉の裏を観察する。 |
| 初期発見時 | 数が少ないうちは、古い歯ブラシや濡らした布でこすり落とすのが最も効果的で安全 。 |
| 大量発生時 | 幼虫が発生する5月~7月頃に、カイガラムシ専用の薬剤を散布する 。成虫には効きにくいため、時期が重要。冬期(12月~2月)にマシン油乳剤を散布し、越冬する卵や幼虫を駆除するのも有効。 |
日々の観察と早期対応が大切
病害虫対策の基本は、とにかく「早期発見・早期対応」に尽きます。毎日の水やりや、庭を眺めるついでに、以下のような変化がないかチェックする習慣をつけましょう。
- 葉の色がおかしくないか?(黄色い斑点、白い粉、黒いすすなど)
- 枝や幹に白い綿や茶色い殻のようなものが付着していないか?
- 新芽や葉の裏にアブラムシなどの小さな虫が集まっていないか?
- 葉が不自然に巻いたり、縮れたりしていないか?
何か異変を見つけたら、「そのうち治るだろう」と放置せず、すぐに行動を起こすことが大切です。スマートフォンで患部の写真を撮り、画像検索をしたり、園芸アプリで質問したりすることで、原因を特定しやすくなります。原因がわかれば、適切な対処法(薬剤の散布、患部の切除など)を迅速に行うことができ、被害の拡大を最小限に食い止められます。
よくある質問
- フェイジョアの実はどうやって食べるのがおすすめですか?
-
最もポピュラーで、フェイジョア本来の芳醇な香りを楽しむことができるのは、生食です。実を横半分にカットし、スプーンですくって食べるだけ。ゼリー状の果肉と、少しシャリっとした部分の食感の違いも楽しめます。追熟が進んで香りが強くなってきたら食べ頃のサインです。その他、大量に収穫できた場合は、砂糖で煮てジャムやコンポートにしたり、ホワイトリカーに漬け込んで果実酒にしたりするのも長期保存ができておすすめです。ヨーグルトやアイスクリームのトッピング、スムージーの材料としても絶品です。
- フェイジョアの収穫時期と食べ頃の見分け方は?
-
収穫時期は品種によって差がありますが、多くは10月下旬から12月頃です。収穫のサインは、木から実が自然に落ちること。決して無理にもぎ取ってはいけません。地面に落ちた実を拾い集めます。拾った直後の実はまだ硬く、酸味が強いことが多いです。常温の室内で数日から1週間ほど「追熟」させることで、果肉が柔らかくなり、甘みと香りが増します。皮を軽く押してみて少し弾力を感じ、ヘタの部分から甘い香りが漂ってきたら、最高の食べ頃です。
- フェイジョアは目隠しになりますか?
-
はい、非常に優れた目隠し(プライバシーフェンス)になります。フェイジョアは一年中葉を落とさない常緑樹であり、葉が密に茂るため、隣家や道路からの視線を効果的に遮ることができます。成長が比較的早いため、数年で立派な生垣を形成することが可能です。ただし、その分、年に1〜2回の定期的な刈り込み剪定で、幅や高さをコントロールする必要があります。剪定に強いので、好みの形に仕立てやすいのも魅力です。
- フェイジョアの木はどこで買えますか?
-
一般的な品種であれば、お近くの園芸店やホームセンターの植木・果樹苗コーナーで手に入ります。特に春(3月〜5月)は、多くの品種が出回る時期です。より多くの品種から選びたい場合や、特定の珍しい品種を探している場合は、果樹苗を専門に扱うオンラインショップを利用するのがおすすめです。オンラインであれば、各品種の詳しい特性(自家結実性の有無、樹形、果実の味など)をじっくり比較検討してから購入することができます。
フェイジョアで後悔しない!庭植え成功のための最終チェックリスト
- フェイジョアは成長が早いので植える場所を広く確保する
- 隣家や道路との距離を十分に考える
- 1本で実がなる品種か購入前に確認する
- 確実に実をつけたいなら2品種以上植える
- 1本しか植えられないならクーリッジなどの自家結実性品種を選ぶ
- 収穫期は実を拾う掃除が日課になることを覚悟する
- 木の根元にシートを敷くと収穫と掃除が楽になる
- 美しい樹形と健康を保つために定期的な剪定は必須
- 剪定は春先(3月~4月)に行うのがベスト
- 剪定の基本は混み合った枝を間引くこと
- 日当たりと水はけの良い場所を好む
- カイガラムシとすす病には特に注意する
- 風通しを良くすることが最大の病害虫予防になる
- 寒冷地では耐寒性のある品種を選び防寒対策を行う
- 収穫した実の食べ方や加工方法を事前に考えておく