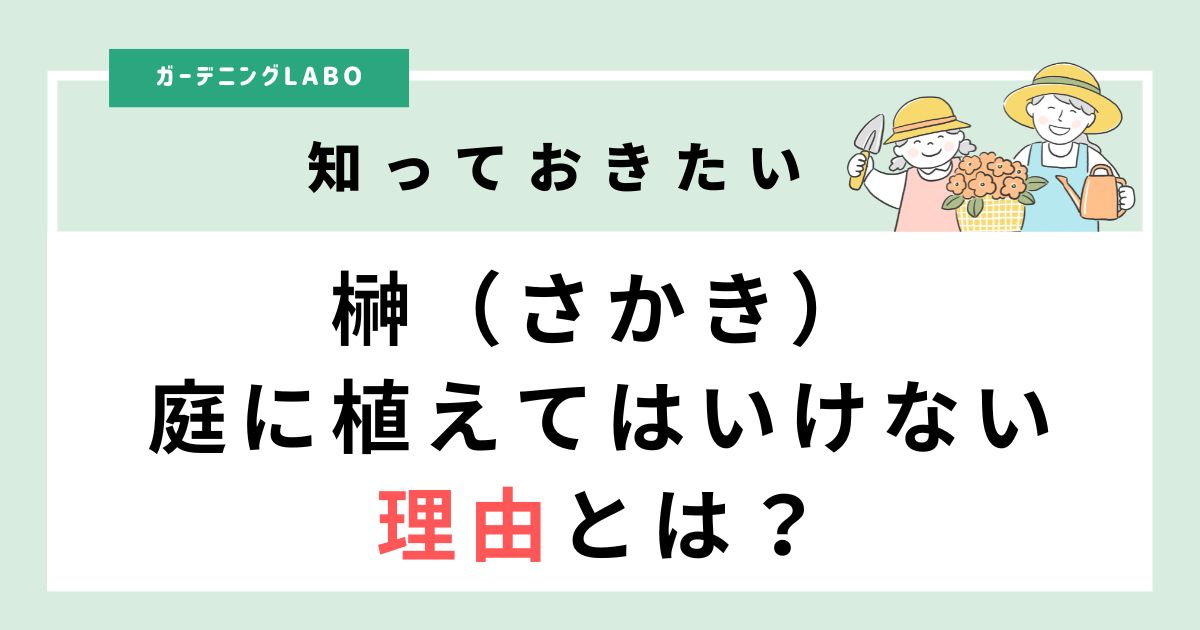「榊を庭に植えてはいけない」という古くからの言い伝えを聞いて、庭木として榊を迎えることに不安を感じていませんか。神棚に供える神聖な木というイメージがある一方で、縁起が悪い、手入れが大変といったネガティブな情報もあり、判断に迷うのは当然のことです。しかし、その背景にある理由を一つひとつ丁寧に紐解いていけば、榊が決してタブーなだけの植物ではないことがわかります。
鉢植えで育てる、病気や害虫の対策法を知る、そして万が一枯れた際の適切な処分方法を理解するなど、正しい知識を持つことで、榊との豊かな関係を築くことは十分に可能です。この記事では、榊を植えてはいけないと言われる本当の理由から、初心者でも安心して育てられる具体的な管理方法、さらには毒性の有無やよく似たヒサカキとの違い、仏壇に飾る是非といった細かな疑問に至るまで、あらゆる角度から専門家が徹底的に解説します。
- 榊を植えてはいけないと言われる本当の理由
- 縁起や風水で気をつけるべきポイント
- 初心者でも安心な榊の育て方と管理方法
- 枯れた後の処分やよくある質問への回答
榊を植えてはいけないと言われる5つの理由

神聖な木すぎて「恐れ多い」とされるから
榊が庭木として避けられる最も根源的な理由は、その極めて高い「神聖性」にあります。榊は単なる美しい緑の植物ではなく、日本の伝統的な信仰である神道と分かちがたく結びついた、特別な意味を持つ存在だからです。
日本の神話『古事記』には、太陽神である天照大神(あまてらすおおみかみ)が弟の素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴に怒り、天岩戸(あまのいわと)に隠れて世が闇に包まれた際、神々がアマノカグヤマの榊の木に八咫鏡(やたのかがみ)や八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を掛けて祈りを捧げ、大神を外に誘い出したという有名な逸話が記されています。この神話からもわかるように、榊は古来より神様をお招きするためのアンテナであり、神様が宿る「依り代(よりしろ)」として、神事において最も重要な役割を担ってきました。神前に供える玉串(たまぐし)に榊が使われるのも、自らの真心や祈りを榊の枝に乗せて神様に捧げるという意味が込められています。
このような背景から、神様そのものと深く結びついた神聖な榊を、人の住まう俗世の庭に軽々しく植えるという行為は「神様に対して恐れ多い」「不敬にあたる」と考える風潮が自然に生まれました。神聖なものであるからこそ、清浄に保たねばならず、もし日々の手入れを怠って枝を伸ばし放題にしたり、病気や害虫で弱らせたり、万が一にも枯らしてしまったりすれば、「神様に対して申し訳が立たない」「罰が当たるのではないか」という、日本人特有の畏敬の念が強く働くのです。この精神的なハードルの高さこそが、「榊を庭に植えてはいけない」という一種のタブーとして、現代にまで色濃く受け継がれている最大の要因と言えるでしょう。
縁起が悪い・死を連想させるという誤解
「榊を植えると縁起が悪い」あるいは「死を連想させるから不吉だ」という話を聞くことがありますが、これは結論から言うと、多くの場合、他の植物との混同や、その静かな佇まいからくる後付けのイメージによる誤解です。本来、榊は繁栄を象徴する、非常に縁起の良い木とされています。
一年を通じて常にみずみずしい緑の葉を保つ常緑樹である榊は、その生命力の強さから「栄える木(さかえるき)」が転じて「サカキ」となったという語源説もあるほど、繁栄のシンボルとされてきました。ではなぜ、正反対の不吉なイメージがつきまとってしまうのでしょうか。
その最大の原因として考えられるのが、榊とよく似ており、代用品として広く流通している「ヒサカキ」と、仏事で用いられる有毒植物「シキミ」の存在です。ヒサカキは、春先に非常に個性的で強い香りを放つ花を咲かせます。この香りが、一部で都市ガスや線香、あるいは火葬場の匂いを連想させることがあり、「死」のイメージと結びつけられることがあります。また、仏教、特に密教系の儀式や葬儀で使われるシキミは、その名前の響きや葉の形が榊と似ていることから混同されやすく、仏事=死というイメージが榊にまで及んでしまったと考えられます。特にシキミは全木に毒があるため、ネガティブなイメージを持たれやすい植物でもあります。
加えて、榊の葉が密に生い茂り、庭に深い影を作る静かで厳かな雰囲気が、墓地などの静寂な場所を想起させることも、一部で不吉なイメージに繋がっているのかもしれません。しかし、これらはすべて他の植物との混同や、後からつけられたイメージの問題であり、神話の時代から神事に用いられてきた榊そのものに、本来不吉な意味合いは一切ないということを理解しておくことが重要です。
風水・家相で植える場所や方角に注意が必要だから

風水や家相の世界では、家や土地を一個の生命体のように捉え、その中を流れる「気」のエネルギーバランスを重視します。庭に植える樹木一本が、その気の流れに大きな影響を与え、住人の健康運や金運、家庭運を左右すると考えられており、中でも榊のように強い生命力を持ち、特別な意味合いを持つ木は、植える場所や方角を慎重に選ぶ必要があるとされています。
家相において最も重要視され、注意が必要なのが、家の中心から見て北東の方角にあたる「鬼門(きもん)」と、その正反対の南西の方角にあたる「裏鬼門(うらきもん)」です。この鬼門から裏鬼門にかけてのラインは、古来より”鬼”(邪気)が出入りする不吉な通り道とされ、常に清潔で、物を置かずにスッキリとさせておくべき場所とされています。この神聖かつデリケートなライン上に、榊のようなエネルギーの強い木を植えてしまうと、気の流れが大きく乱れたり、邪気が滞ったりする原因になると考えられています。その結果、家庭内に病人が出たり、トラブルが絶えなくなったり、金運が低下したりといった、様々な凶作用を招くとされているのです。
一方で、榊の持つポジティブなエネルギーを最大限に活かすことができる吉方位もあります。風水では、一日の始まりである太陽が昇る「東」は発展や成長のエネルギーを司る方角とされ、また、その隣の「南東」は縁や評判を司る方角とされています。これらの場所に榊を植えることで、その強い生命力が家の運気を後押しし、仕事の成功や良縁を呼び込むと考えられています。
このように、榊を庭に植える際には、風水や家相の専門的な知識がある程度求められます。「よくわからないまま下手に植えて、かえって家の運気を下げてしまうくらいなら、最初から植えない方が無難である」という考え方が、「榊を庭に植えてはいけない」という話につながる、もう一つの側面なのです。
病害虫に弱く手入れが大変だから
神聖で清らかなイメージとは裏腹に、植物としての榊は、意外にも病害虫の被害に遭いやすいという、非常に現実的で厄介な問題を抱えています。この管理の手間と難易度の高さが、庭木として敬遠される大きな理由の一つとなっています。
榊の栽培で最も悩まされる代表的な害虫が「カイガラムシ」です。その名の通り、成虫になると硬い殻をかぶるため薬剤が効きにくく、一度発生すると根絶が難しいことで知られています。葉の裏や枝の分かれ目に、白い綿のようなものや、茶色く硬い殻のような粒が付着していたら、それはカイガラムシの仕業です。カイガラムシは植物の樹液を吸って生育を著しく阻害するだけでなく、その甘い排泄物(甘露)が原因で、二次被害として「すす病」を誘発します。
すす病は、この甘露を栄養源として黒いカビが繁殖する病気で、葉の表面がまるでススで覆われたように真っ黒になってしまいます。これにより光合成が妨げられ、見た目が損なわれるだけでなく、生育不良に陥り、最悪の場合は株全体が枯死してしまうこともあります。この「知らないうちに大量発生→気づいた頃には真っ黒→薬が効かない」という悪循環に陥りやすいことが、榊の管理を難しくしている大きな要因です。
成長が早く大きくなりすぎるから
榊は非常に生命力が旺盛な樹木であり、特に庭に直接植える「地植え」にすると、その成長スピードは多くの人が想像する以上です。購入した当初は1mにも満たない苗木でも、生育環境が合えば、数年で人の身長をはるかに超える高さに達し、適切な管理を怠ると、最終的には5メートルから10メートル、時にはそれ以上の高木に成長することがあります。
| 栽培方法 | 樹高の目安 | 管理のポイント |
|---|---|---|
| 地植え | 5~10m | 高成長、要定期剪定、広い場所が必要 |
| 鉢植え | 1~2m | サイズ調整が容易、要植え替え |
樹木がこれほど大きくなると、個人宅の庭では様々な問題が生じ始めます。まず、庭全体の日当たりが悪くなり、他の植物の生育を妨げることがあります。また、秋には常緑樹とはいえ葉が入れ替わるため、大量の落ち葉が発生し、その掃除が毎年の大きな負担となります。さらに深刻化しやすいのが、ご近所とのトラブルです。枝が隣家の敷地まで伸びてしまったり、落ち葉が隣の庭や雨どいを詰まらせたりするケースは後を絶ちません。民法も改正され、越境された側が枝を切り取ることができるようになりましたが、そうなる前に関係性が悪化するリスクは避けたいものです。(参考:法務省:隣地の竹木の枝の切取り・根の切取り)
見えない地面の下でも問題は起こり得ます。力強く伸びた根が、家の基礎や駐車場のコンクリート、地中の水道管やガス管などを持ち上げたり、損傷させたりする危険性もゼロではありません。こうした事態を未然に防ぐためには、成長を見越した計画的な剪定が毎年必ず必要になります。高くなった樹木の剪定は危険も伴うため、専門の造園業者に依頼する必要も出てきます。その維持管理にかかる費用と手間を現実的に考えた結果、「安易に庭に植えるべきではない」と判断されることが多いのです。
それでも榊を植えたい!植えてはいけないと言われた時の対策

無理に庭植えしない!鉢植えで育てるメリット

ここまで解説してきた「榊を植えてはいけない」とされる様々な理由は、そのほとんどが庭に直接植える「地植え」を前提としたものであることにお気付きでしょうか。裏を返せば、栽培方法を「鉢植え」という選択肢に変えるだけで、これまで挙げてきた懸念点の多くをスマートに解消し、榊をもっと身近で管理しやすい存在として楽しむことが可能になります。
| 鉢植えのメリット | 鉢植えの注意点 |
|---|---|
| サイズ管理が容易 場所を自由に移動可能 病害虫の発見・対処が楽 近隣トラブルの心配なし | 根詰まり(要植え替え) 水切れしやすい 大木には育たない |
鉢植え栽培の最大のメリットは、何と言ってもその管理のしやすさにあります。根の伸長が鉢の大きさに制限されるため、樹高が自然とコントロールされ、剪定の手間も大幅に軽減されます。風水が気になる場合でも、鉢ごと移動させるだけで、気になる鬼門を避けたり、最適な吉方位に置いたりと、自由にレイアウトを変更できます。また、夏は西日を避けられる涼しい場所へ、冬は寒風が当たらない軒下へ、台風や大雪の際には玄関先へ、といったように、気候変動に合わせた柔軟な対応ができるのも鉢植えならではの強みです。
病害虫が発生した際も、株全体を目の高さで細かくチェックできるため、葉の裏の異変なども見逃しにくく、早期発見に繋がります。薬剤を散布するにしても、範囲が限定的なので簡単かつ安全に行えます。このように、鉢植えという選択肢は、榊を育てる上での物理的・精神的なハードルを劇的に下げてくれる、非常に有効な解決策なのです。庭木の手入れに自信がない初心者の方や、まずは気軽に榊のある暮らしを始めてみたいという方には、この鉢植えでの栽培を強く推奨します。
植え付けに最適な時期と土壌の選び方
榊を健やかに末永く育てるためには、人間にとっての住まい選びが重要であるのと同じように、最初のスタートである「植え付け」が極めて重要です。榊にとって快適な生育環境を最初にきちんと整えてあげることが、その後の成長を大きく左右し、病気に強い丈夫な株を育てるための土台となります。
まず、植え付けの時期については、植物へのストレスが最も少ない、気候が穏やかな時期を選ぶのが鉄則です。具体的には、厳しい冬の寒さが終わり、新芽が動き出す前の春(3月下旬~5月上旬)、または、夏の酷暑が和らぎ、根が活動するのに十分な地温が保たれている秋(9月中旬~10月)が最適期です。これらの時期に植え付けることで、榊はスムーズに新しい環境に根を張り、活着しやすくなります。逆に、根の活動が鈍る真夏や、地面が凍結するような厳寒期に植え付けを行うと、根が深刻なダメージを受けてしまい、そのまま枯れてしまうリスクが非常に高くなるため、絶対に避けなければなりません。
次に、植える場所と土壌の準備です。榊は、もともと山林の木々の下などに自生していた植物であり、その頃の環境を好みます。つまり、一日中強い日差しが容赦なく照りつける場所ではなく、午前中だけ日が当たる、あるいは木漏れ日が優しく差し込むような「半日陰」で、なおかつ風通しの良い場所が理想的な生育環境です。強い西日は葉を傷める「葉焼け」の原因になりやすいため、特に避けた方が良いでしょう。土壌については、とにかく「水はけの良さ」が最も重要なキーワードです。
榊は根が常に湿った状態を嫌うため、水はけが悪いと根腐れを起こしやすくなります。鉢植えの場合は、市販の草花用あるいは観葉植物用の培養土をベースにするのが手軽ですが、より良い環境を作るなら、赤玉土(小粒)を6割、腐葉土を3割、川砂または鹿沼土を1割といった割合でブレンドした用土がおすすめです。地植えの場合は、植える予定の場所に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘り、掘り上げた土に対して3割程度の腐葉土や牛ふん堆肥をよく混ぜ込み、土壌をふかふかに改良してから植え付けます。この一手間を加えることで、水はけと水持ちのバランスが格段に向上し、根が健全に呼吸できる理想的な土壌環境を作り出すことができます。
枯らさないための日々の手入れと剪定方法

無事に植え付けが完了したら、その後の日々の地道な管理が、榊の健康を保ち、青々とした美しい姿を長く楽しむための鍵となります。プロの造園家のような特別な技術は必要ありませんが、植物の状態をよく観察し、適切なタイミングで少し手をかけてあげるという、日々の気配りが大切です。
【水やり】
日々の手入れで最も基本かつ重要なのが水やりです。榊は極度の乾燥を嫌う植物であり、特に土の量が限られ、乾燥しやすい鉢植えの場合は水切れに細心の注意が必要です。水やりのベストタイミングは、見た目や感覚で「土の表面が乾いたら」が基本のサインです。与える際は、ためらわずに鉢底の穴から水が十分に流れ出てくるまで、たっぷりと与えるのがポイントです。これにより、鉢の中の古い水分や根が排出した老廃物を洗い流し、新鮮な水と空気を根に行き渡らせる効果があります。季節ごとの頻度の目安としては、生育が活発な春から秋にかけては1〜2日に1回、特に乾燥が激しい真夏は、朝と夕方の2回が必要になることもあります。逆に、植物の活動が緩やかになる冬場は、水の吸い上げ量も減少するため、土の乾き具合をよく確認しながら、3〜4日に1回程度に頻度を落とします。常に土がジメジメしている状態は根腐れの原因になるため、「乾いたら、たっぷり」のメリハリを意識しましょう。
【剪定】
剪定は、単に樹形を美しく整えるためだけでなく、風通しを良くして病害虫を防ぐという、衛生管理の面でも非常に重要な作業です。枝葉が密集して株の内部が蒸れると、そこがカイガラムシやすす病などの温床となってしまいます。剪定の目的は、不要な枝を整理して、株の中心部まで風と光がスムーズに通り抜ける「道」を作ってあげることです。具体的には、内側に向かって伸びて他の枝の邪魔をする「内向枝(ないこうし)」、他の枝と交差してしまっている「交差枝(こうさし)」、勢いよく真上に伸びすぎる「徒長枝(とちょうし)」、そして明らかに枯れてしまった「枯れ枝」などを、枝の付け根から切り落とす「透かし剪定」が基本となります。作業の適期は、新芽が伸びる前の3月頃、または成長が一段落した9月〜10月頃です。一度に大量の枝を切り落とす「強剪定」は、木に大きなストレスを与えて弱らせる原因になるため、毎年少しずつ、全体のバランスを見ながら樹形を維持していくのが、上手に付き合うコツです。
【肥料】
榊は本来、痩せた土地でも育つ丈夫な木ですが、特に鉢植えの場合は土の中の養分が限られているため、適度な施肥が健康な生育を助けます。生育期である春(3月頃)と、夏を越して体力を回復させる秋(9月下旬〜10月頃)の年2回、緩やかに効果が持続するタイプの「緩効性化成肥料」を株元に少量施すか、油かすなどの有機質肥料を与えると、葉の色つやが良くなり、病気への抵抗力も高まります。ただし、肥料の与えすぎはかえって根を傷める原因になるため、規定量を必ず守ることが大切です。
枯れた後の処分は?神聖な木への敬意を払った供養
どれだけ愛情を込めて大切に育てていても、生き物である以上、寿命を迎えたり、病気や管理の失敗で枯れてしまったりすることは避けられません。特に、神様と深く関わる榊だからこそ、枯れてしまった後の処分方法に深く悩む方は少なくありません。「他の庭木と同じように、ただのゴミとして捨ててしまって良いのだろうか」「何か悪いことが起きないだろうか」という不安や罪悪感を抱くのは、榊を特別な存在として敬ってきた日本人として、ごく自然な感情です。
結論から言うと、法律上は他の植物と同様に可燃ゴミとして処分して問題ありません。しかし、もし気持ち的に抵抗がある場合は、感謝と敬意を込めた丁寧な方法で手放すことで、心穏やかにお別れをすることができます。
家庭でできる最も簡単な方法は、お清めの塩をひとつまみ振りかけ、白い紙(半紙やきれいなキッチンペーパーなど)に包んでから、他のゴミとは別の袋に入れてゴミに出すというやり方です。形だけのようにも思えますが、「ただのゴミ」ではなく「供養して手放すもの」として、自分の気持ちに一つの区切りをつけるという点で、非常に意味のある行為と言えます。
より正式な方法を望むのであれば、地域の氏神様である神社に相談してみるのも一つの手です。多くの神社では、一年間お世話になったお札やお守りを納めるための「古札納所(こさつおさめしょ)」が設けられており、そこに納められたものは、後日お焚き上げ(一般的に「どんど焼き」として知られる神事)によって、浄火の力で天にお還しされます。神社によっては、神事に使用した縁起物として、枯れた榊もこの古札納所で受け入れてくれる場合があります。ただし、これはあくまでも神社の厚意によるものであり、全ての神社が対応しているわけではありません。また、受け入れ可能なサイズに制限がある場合も考えられます。そのため、必ず事前に神社の社務所に電話などで問い合わせをし、持ち込んで良いか、どのような形で持ち込めば良いかを確認してから伺うのが、最低限のマナーです。感謝の気持ちで供養をお願いするのですから、決して無断で境内に放置するようなことがあってはなりません。
榊は本当に縁起が良い?ポジティブな側面
ここまで「植えてはいけない」というネガティブな側面に光を当ててきましたが、それはあくまで榊が持つ特別な力や意味合いを正しく理解し、敬意を払うための前提知識です。その本質を理解すれば、榊が日本の精神文化において、いかにポジティブで縁起の良い存在であるかがわかります。
榊の語源には諸説ありますが、その代表的なものが、神様が鎮座する神聖な領域と、我々人間が住む俗世との「境(さかい)」を示す木であったとする説です。また、一年中葉が青々として生命力に溢れているその姿から、「栄える木(さかえるき)」に由来するという説も有力です。いずれの説も、榊が単なる植物ではなく、清浄さや生命力、そして繁栄の象徴として古くから人々の暮らしの中に根付いていたことを示しています。その強い生命力は、家の繁栄や子孫の健やかな成長、商売繁盛を願う気持ちと結びつき、縁起の良い木として大切にされてきました。
神棚に榊を供えるという習慣は、単なる飾りや慣習ではありません。清浄で生命力に満ちた榊の枝を依り代として、私たちの家庭に神様をお迎えし、その偉大なご神徳をいただくことで、家全体をあらゆる災厄から守り、清らかな状態に保ってもらうという、具体的で深い意味が込められているのです。また、多くの家庭で習慣となっている、毎月1日と15日に新しい榊に交換するという行為は、月の満ち欠けに合わせて、日々の暮らしの中に神様への感謝を忘れず、心を新たにするという、精神的なリフレッシュの機会としての役割も担っています。
つまり、これまで解説してきたような「植えてはいけない理由」とされる様々な注意点は、見方を変えれば、この神聖で縁起の良い木に対する「敬意の表し方」「大切に扱うためのマニュアル」と言い換えることができます。そのルールをきちんと守り、日々感謝の気持ちを持って丁寧に育てるのであれば、榊は決して不吉なことや災いをもたらすものではなく、むしろ家庭に幸運と精神的な安らぎをもたらしてくれる、かけがえのない守り神のような存在となってくれるに違いありません。
よくある質問
- 榊に毒性はありますか?ペットや子供がいても安全ですか?
-
榊(サカキ)そのものに、強い毒性があるという公的な報告はほとんどなく、比較的安全な植物として認識されています。しかし、この質問で最も重要なポイントは、榊と非常によく似ており、時に間違って販売されたり、庭に植えられていたりすることがある有毒植物「シキミ」の存在です。
シキミは、特にその星形に似た果実や葉に「アニサチン」という痙攣毒を含む猛毒の成分を含んでいます。これを誤って口にしてしまうと、嘔吐、腹痛、下痢に始まり、重症化すると意識障害や激しい痙攣、呼吸困難などを引き起こし、最悪の場合は死に至ることもある、大変危険な植物です。実際に、乾燥させたシキミの果実を、中華料理などで使われる香辛料の八角(トウシキミ)と間違えて料理に使用し、集団食中毒に至った事例も過去に発生しています。この危険性から、厚生労働省のウェブサイトでも、シキミによる食中毒への注意が明確に呼びかけられています。
榊とシキミは、葉の付き方や形で区別することができます。榊の葉は縁が滑らかでギザギザがないのに対し、シキミの葉はやや厚みがあり、光に透かすと小さな油点が見えるなどの特徴がありますが、植物に詳しくない方が一見して判別するのは容易ではありません。そのため、特に好奇心旺盛なペットや小さなお子様がいるご家庭では、万が一の誤食事故を防ぐためにも、榊は絶対に手の届かない高い場所に置く、あるいはシキミと明確に区別して販売している、信頼できる生花店や園芸店から購入するなどの自衛策を講じることが、家族の安全を守る上で非常に重要です。
- 仏壇に榊を飾るのはマナー違反ですか?
-
はい、結論から申し上げると、日本の一般的な宗教的慣習において、仏壇に榊を飾ることはマナー違反と捉えられることがほとんどです。これは、榊と仏花の役割が、それぞれの信仰の対象である神様と仏様に基づいて、明確に区別されているためです。
榊は「神道」の世界において、神様をお迎えし、神域の清浄さを保つためにお供えするものであり、その場所は「神棚」です。一方で、仏壇は「仏教」の世界において、阿弥陀如来などのご本尊様や、亡くなられたご先祖様の霊を祀るための場所であり、ここには菊やカーネーション、リンドウといった「仏花(ぶっか)」をお供えするのが長年の習わしです。日本人の生活には神道と仏教が深く溶け込んでいますが、信仰の対象や儀式の作法はそれぞれ異なります。そのため、仏様の世界である仏壇に、神様の世界のものである榊を持ち込むことは、それぞれの作法を混同することになり、基本的には避けるべきとされています。
ただし、これは絶対的な禁忌というわけではありません。例えば、故人が生前、神社の宮司であったり、榊をこよなく愛していたりした場合など、特別な事情があれば、遺族の想いとして供えられることもあります。また、地域の独自の慣習や、家の宗派の考え方によっても解釈が異なる場合があります。もし判断に迷う場合は、ご家族や親戚の年長者、あるいは日頃お世話になっている菩提寺の住職に率直に相談してみるのが最も確実で、丁寧な対応と言えるでしょう。
- ヒサカキとの違いは何ですか?
-

左が榊、右がヒサカキ 榊(サカキ)とヒサカキは、どちらも神棚にお供えされる植物として広く流通しているため混同されがちですが、植物分類上は科は同じでも属が異なる、別の植物です。本来、神事には榊(別名:本榊、真榊)が用いられるのが正式ですが、榊は比較的暖かい地域を好むため、冬の寒さが厳しい関東以北や山間部などでは自生していません。そうした地域において、姿形が似ていて入手しやすいヒサカキが、古くからその代用品として用いられてきたという歴史的な背景があります。
この二つを見分けるための最も分かりやすく、確実なポイントは「葉の縁(ふち)の形」です。榊(本榊)の葉は、縁全体が滑らかでギザギザがなく、つるりとしているのが最大の特徴です。それに対して、ヒサカキの葉は、榊より一回り小さいことが多く、葉の縁に細かいノコギリの歯のようなギザギザ(専門用語で「鋸歯(きょし)」と言います)があるのが特徴です。葉を一枚手に取って、指先で縁をそっとなぞってみると、その違いがはっきりと分かります。現在では、スーパーや花屋で「神棚用の榊」として販売されているものの中には、このヒサカキがかなりの割合で含まれています。どちらをお供えしても神様に対して失礼にあたるということはありませんが、本来の「榊」とは異なる植物であるという点は、豆知識として知っておくと良いでしょう。
榊との上手な付き合い方!重要ポイントまとめ
- 「植えてはいけない」は神様への畏敬の念が根底にある
- 縁起が悪い説は他の植物との混同による誤解が多い
- 風水では鬼門(北東)と裏鬼門(南西)への地植えは避けるべき
- 地植えは高木になるため計画的な剪定が毎年必要
- カイガラムシやすす病が発生しやすく手入れが欠かせない
- 多くの問題は鉢植えで育てることで解消できる
- 鉢植えなら大きさ・場所・方角を自由に調整可能
- 植え付けは植物への負担が少ない春(3~5月)か秋(9~10月)が最適
- 半日陰と水はけの良い土壌環境を好む
- 水やりは「土が乾いたら、たっぷり」が基本
- 剪定は風通しを良くして病害虫を予防するのが主な目的
- 枯れた榊は塩で清め白い紙に包んで処分すると丁寧
- 榊は「栄える木」が語源とされる縁起の良い木
- 有毒なシキミと絶対に間違えないよう注意深く確認する
- 仏壇ではなく神棚にお供えするのが正しい作法