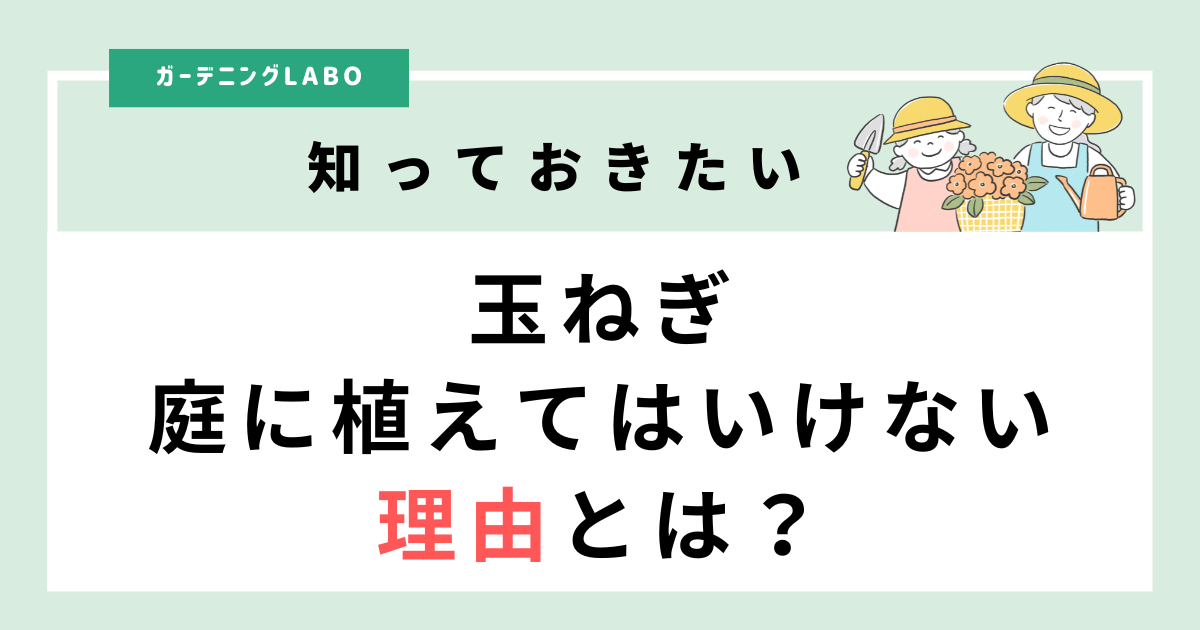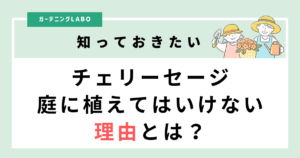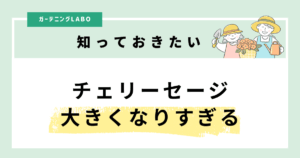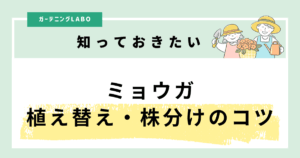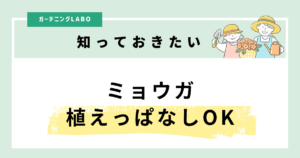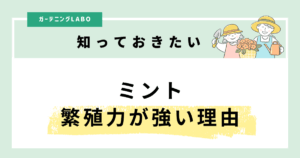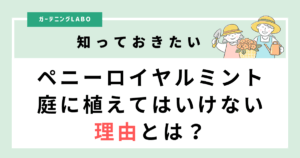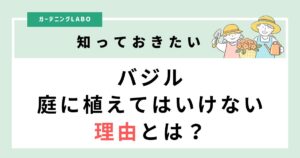家庭菜園で玉ねぎを育てたいと考えている方の中には、庭に植えてはいけないという話を耳にして不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実は玉ねぎ栽培には注意すべき点がいくつかあり、何も知らずに庭に植えると失敗するリスクが高い野菜です。
この記事では、玉ねぎを庭に植えてはいけないと言われる理由と、それを解決する具体的な対策方法をわかりやすく解説していきます。正しい知識を身につけることで、初心者でも美味しい玉ねぎを収穫できるようになります。
- 玉ねぎを庭に植えてはいけないと言われる7つの理由がわかる
- 連作障害や病害虫、土壌環境など失敗の原因が明確になる
- 土壌改良や植え付け方法など具体的な対策が学べる
- プランター栽培やコンパニオンプランツの活用法がわかる
玉ねぎを庭に植えてはいけない理由とは?

| 問題点 | 主な原因 | 影響 |
|---|---|---|
| 連作障害 | 土壌病原菌の蓄積 | 生育不良・病気の発生 |
| 病害虫 | べと病・ネギハモグリバエ | 葉の枯死・収量減少 |
| 水はけ不良 | 粘土質の庭土 | 根腐れ・腐敗 |
| 酸性土壌 | pH5台の土壌 | 生育不良・玉の肥大不良 |
| 相性の悪い野菜 | マメ科・ネギ類との混植 | 病害虫の蔓延・栄養競合 |
玉ねぎの特徴と基本情報を知ろう
玉ねぎはヒガンバナ科ネギ属の多年草で、冷涼な気候を好む野菜です。日本では主に秋まき春どりの栽培が一般的で、11月に苗を植え付けて翌年5月から6月にかけて収穫します。生育適温は15度から20度程度とされており、寒さには比較的強いものの、高温多湿の環境では病気が発生しやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 科目 | ヒガンバナ科ネギ属 |
| 生育適温 | 15~20度 |
| 植え付け時期 | 11月中旬~12月中旬 |
| 収穫時期 | 5月中旬~6月中旬 |
| 適正pH | 6.0~7.0(弱酸性~中性) |
| 栽培期間 | 約6ヶ月 |
| 株間 | 10~15cm |
| 連作年限 | 3~4年空ける |
連作障害のリスクと土壌環境の問題
玉ねぎは他の野菜と比べると連作障害が出にくい作物ですが、全く問題がないわけではありません。同じ場所で毎年玉ねぎを栽培すると、土壌中に特定の病原菌が蓄積されていき、徐々に生育が悪くなっていきます。
連作障害で起こる主な問題
連作を続けることで土壌中には白絹病や首腐れ病などの病原菌が残存し、次のシーズンの玉ねぎに感染するリスクが高まります。特に白絹病は土壌伝染性の病気で、一度発生すると根絶が非常に困難です。菌糸が土壌に広がり、地際部分に白い綿状のカビが発生して株全体が枯死してしまいます。
連作障害を防ぐには、同じ場所での玉ねぎ栽培を3年から4年は空ける輪作が推奨されています
土壌の栄養バランスの偏り
同じ作物を連続して栽培すると、特定の栄養素だけが吸収され続けるため土壌の栄養バランスが崩れます。玉ねぎは特にカリウムを多く吸収する野菜なので、連作すると土壌中のカリウムが不足しがちになり、玉の肥大が悪くなったり味が落ちたりします。また、逆に特定の成分が蓄積しすぎて生育障害を起こすこともあります。
病害虫が発生しやすい
玉ねぎ栽培で最も注意が必要なのが病害虫の発生です。庭の土壌環境によっては、さまざまな病気や害虫が発生しやすくなり、収穫量が大幅に減少したり、最悪の場合は全滅してしまうこともあります。
主な病気
玉ねぎ栽培で特に問題となる病気がべと病です。アース製薬の栽培ガイドによると、べと病は葉の脈に沿って淡黄白色の斑点ができ、病斑の裏に白カビが生えるとされています。多湿な環境で発生しやすく、降雨が連続すると一気に広がります。さび病も円形や楕円の小斑点ができて表皮が破れ、黄色の胞子が露出する病気です。
| 病名 | 発生時期 | 症状 |
|---|---|---|
| べと病 | 1~3月 | 淡黄色の斑点、葉裏に白カビ |
| さび病 | 2~4月 | 円形小斑点、黄色の胞子露出 |
| 白絹病 | 5~7月 | 地際に白い綿状のカビ |
| 軟腐病 | 5~10月 | 株元が水浸状に腐敗、悪臭 |
| 萎縮病 | 春先 | 葉にモザイク状の斑点 |
主な害虫
害虫ではネギハモグリバエが最も厄介です。幼虫が葉の内部に潜り込んで食害するため、被害が見えにくく気づいたときには手遅れになっていることが多いです。アザミウマ類も葉の汁を吸って白くかすり状にする害虫で、ウイルス病を媒介するリスクがあります。ヨトウムシは夜行性で夜間に葉を食害し、放置すると葉を食べつくしてしまいます。
水はけが悪いと根腐れを起こす
玉ねぎは水はけの良い土壌を好む野菜です。日本の庭土は粘土質が多く、雨が降ると水が溜まりやすい傾向があります。このような水はけの悪い環境で玉ねぎを栽培すると、根が酸素不足になって根腐れを起こしてしまいます。
水はけ不良が引き起こす問題
根腐れが進行すると株全体の生育が悪くなり、葉が黄色く変色して最終的には枯死します。また、湿った環境は軟腐病などの病原菌が繁殖しやすい条件でもあり、玉が水浸状に腐敗して強烈な悪臭を放つようになります。特に梅雨の時期や秋の長雨が続くと被害が拡大しやすく、一株が腐敗すると周囲にも広がっていきます。
粘土質の土壌では排水性が極端に悪いため、植え付け前に十分な土壌改良を行わないと失敗する確率が非常に高くなります。改良せずに植えた場合、雨のたびに水が引かず、根が常に過湿状態になってしまうのです。
酸性土壌では生育不良になりやすい
玉ねぎの栽培に適した土壌pHは6.0から7.0の弱酸性から中性とされています。しかし日本の土壌は雨の影響でpH5.0から5.5程度の酸性に傾きやすく、何も対策をしないと玉ねぎが育ちにくい環境になってしまいます。
酸性土壌が玉ねぎに与える影響
土壌が酸性に傾くと、玉ねぎが必要とする栄養素が溶け出しにくくなり吸収効率が低下します。自然暮らしの栽培情報によると、肥料成分は土壌pHが弱酸性の範囲で溶けだしやすいという性質があるため、多くの植物がpH6.0から6.5の弱酸性で育ちやすくなっているとのことです。酸性が強すぎると根の発達も阻害され、玉の肥大が悪くなったり形が歪んだりします。
また、酸性土壌ではアルミニウムなどの有害成分が溶け出しやすくなり、根を傷めることもあります。葉色が薄くなって生育が遅れ、最終的には小さな玉しかできません。
植え付けの2週間前に苦土石灰を施して土壌pHを調整することが、玉ねぎ栽培成功の鍵となります
相性の悪い野菜と混植すると失敗する
家庭菜園では限られたスペースを有効活用するため、複数の野菜を近くに植えることがよくあります。しかし玉ねぎには相性の悪い野菜があり、これらと混植すると互いに悪影響を及ぼし合って失敗の原因になります。
マメ科植物との相性
インゲン、大豆、エンドウなどのマメ科植物は、玉ねぎとの相性が最も悪いとされています。マメ科の根には根粒菌が共生しており、この根粒菌が空気中の窒素を固定して植物に供給する働きをしています。ところが玉ねぎが含む硫黄化合物がこの根粒菌の活動を阻害してしまうため、マメ科植物の生育が悪くなります。
逆にマメ科植物が窒素を多く供給することで、玉ねぎが窒素過多になって葉ばかりが茂り、玉が大きくならないという問題も起こります。
同じネギ類との混植リスク
ニンニク、ニラ、長ネギなど同じアリウム属の野菜を近くで栽培すると、共通の病害虫が広がりやすくなります。べと病やさび病、ネギアザミウマなどが発生した場合、あっという間に全体に蔓延してしまい被害が拡大します。また土壌中の栄養素の競合も起こりやすく、どちらも十分な養分を吸収できず生育不良になります。
| 相性の悪い野菜 | 相性の良い野菜 |
|---|---|
| マメ科(インゲン、大豆、エンドウ) ネギ類(ニンニク、ニラ、長ネギ) アブラナ科(キャベツ、ブロッコリー) | ニンジン トマト・ナス・ピーマン レタス カモミール |
芽が出た玉ねぎを植えるとどうなる?
スーパーで買った玉ねぎから芽が出てきたので、これを植えれば新しい玉ねぎができると考える方がいますが、実は芽が出た玉ねぎを植えても大きな玉にはなりません。
発芽抑制剤の影響
市販されている玉ねぎの多くは、長期保存を可能にするために発芽抑制剤が処理されています。この処理により芽が出にくくなっていますが、時間が経つと効果が薄れて芽が出てきます。しかし一度処理された玉ねぎは本来の生命力が低下しているため、植えても十分な成長は期待できません。
分球とネギ坊主
芽が出た玉ねぎを土に植えると、一つの玉が複数に分球してしまい、小さな玉がいくつもできる状態になります。また花芽が形成されてネギ坊主ができやすく、エネルギーが花の生産に使われてしまうため、玉はほとんど肥大しません。緑の葉はネギとして食べることはできますが、新たな大きな玉を収穫することは難しいのです。
腐敗すると強烈な臭いで近隣トラブルの原因に
玉ねぎが水はけ不良や過湿によって腐敗すると、硫黄化合物による非常に強烈な臭いを発します。この臭いは腐った卵のような刺激臭で、周囲に広く拡散します。住宅密集地で玉ねぎを栽培している場合、腐敗した玉ねぎの臭いが近隣に届いてクレームにつながることもあります。特に夏場の高温時に腐敗が進むと、悪臭がさらに強くなるため注意が必要です。
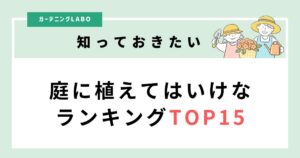
玉ねぎを庭に植えてはいけない問題を解決する対策方法

| 対策項目 | 具体的な方法 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 土壌改良 | 苦土石灰・堆肥・腐葉土の投入 | 植え付け2週間前 |
| pH調整 | 6.0~7.0に調整 | 植え付け2週間前 |
| 高畝作り | 15~20cm程度の高さ | 植え付け1週間前 |
| マルチング | 黒マルチ・ワラで覆う | 植え付け直後 |
| 追肥 | 化成肥料を施す | 12月下旬・2月下旬 |
土壌改良で玉ねぎ栽培に適した環境を作る
玉ねぎを庭で成功させるためには、植え付け前の土壌改良が最も重要です。日本の庭土は多くの場合、玉ねぎ栽培に適していないため、しっかりと土づくりをする必要があります。
pH調整の方法
まず植え付けの2週間前に苦土石灰を施して土壌pHを調整します。1平方メートルあたり100グラムから150グラム程度を土壌に混ぜ込み、pH6.0から6.5の弱酸性から中性に整えます。趣味の園芸によると、日本の土壌は雨の影響でpH5.0程度の酸性になりやすいため、石灰で調整することが推奨されています。ただし石灰を入れすぎてpHを7.0以上にしてしまうと、今度は下げるのが困難になるため注意が必要です。
有機質による排水性の改善
土壌のpH調整後、堆肥や腐葉土を1平方メートルあたり2キログラムから3キログラム投入します。有機質を混ぜ込むことで土壌の団粒構造が発達し、排水性と保水性の両方が改善されます。粘土質の土壌の場合は、さらにパーライトや赤玉土を混ぜると効果的です。
高畝による水はけ確保
土壌改良が済んだら、15センチから20センチの高さの畝を作ります。高畝にすることで雨水が溜まりにくくなり、根腐れのリスクを大幅に減らせます。畝幅は60センチから80センチ程度が作業しやすく、通路も確保できます。
1平方メートルあたり100~150グラムの苦土石灰を土壌に混ぜ込み、pH調整を行います
1平方メートルあたり2~3キログラムの完熟堆肥と腐葉土を土に混ぜ込み、よく耕します
15~20センチの高さの畝を作り、表面を平らに整えます
正しい植え付け時期と方法を守る
玉ねぎ栽培の成否は、適切な時期に正しい方法で植え付けることで大きく左右されます。植え付けが早すぎても遅すぎても、冬を越せなかったり玉が小さくなったりします。
植え付け適期
秋まき玉ねぎの植え付け適期は、地域にもよりますが11月中旬から12月中旬です。早生品種は11月中旬、中生品種は11月下旬から12月上旬、晩生品種は12月上旬から中旬が目安となります。この時期を外すと、冬の寒さで苗が傷んだり、逆に大きくなりすぎて花芽ができたりするリスクがあります。
良い苗の選び方
苗選びも重要なポイントです。草丈が20センチから25センチ程度で、茎の太さが鉛筆くらい(直径5ミリから7ミリ)のものが理想的です。太すぎる苗は冬の間に花芽ができやすく、細すぎる苗は寒さで枯れるリスクが高くなります。葉の色が濃い緑色で、病気の痕がないものを選びましょう。
植え付けの深さと株間
植え付けは浅植えが鉄則です。指の第2関節程度の深さ、約3センチから4センチに植えます。深植えにすると玉の形が悪くなったり、首が太くなって貯蔵性が落ちたりします。株間は10センチから15センチ確保し、条間は15センチから20センチとります。植え付け後は軽く土を押さえて根と土を密着させ、たっぷりと水やりをします。
| 品種タイプ | 植え付け時期 | 収穫時期 |
|---|---|---|
| 早生品種 | 11月中旬 | 5月上旬~中旬 |
| 中生品種 | 11月下旬~12月上旬 | 5月下旬~6月上旬 |
| 晩生品種 | 12月上旬~中旬 | 6月上旬~中旬 |
追肥と水やりのタイミングを間違えない
玉ねぎは植え付けから収穫までの6ヶ月間、適切な追肥と水やりで生育を支える必要があります。肥料が多すぎても少なすぎても、また水やりのタイミングが悪くても、玉の肥大に影響します。
追肥のタイミングと量
追肥は年内に1回、年明けに1回の計2回行うのが基本です。1回目は12月下旬に、2回目は2月下旬に化成肥料を1平方メートルあたり30グラムから50グラム施します。肥料は株元から少し離れた場所に施し、軽く土と混ぜます。3月以降の追肥は控えます。遅い時期まで追肥を続けると、玉が軟らかくなって貯蔵性が落ち、腐敗しやすくなるためです。
水やりの注意点
玉ねぎは比較的乾燥に強い野菜なので、地植えの場合は基本的に降雨だけで十分です。ただし冬場に極端に乾燥が続く場合や、春先の玉が肥大する時期に雨が少ない場合は、土が乾いたらたっぷりと水を与えます。過湿には弱いため、水のやりすぎには注意が必要です。
収穫の2週間から3週間前には水やりを控えめにして、玉を締めることが貯蔵性を高めるコツです
冬越し対策で霜害から守る
秋に植え付けた玉ねぎは、冬の寒さを乗り越えなければなりません。適切な冬越し対策を行うことで、苗を霜害から守り春以降の生育を良好に保てます。
マルチングによる保温
植え付け後、黒マルチやワラで畝を覆います。マルチングには保温効果だけでなく、雑草抑制や泥跳ねによる病気予防の効果もあります。黒マルチを使用する場合は、植え付け前に畝に張っておき、穴を開けて苗を植える方法が効率的です。ワラを使う場合は、株元に厚さ5センチ程度敷き詰めます。
霜柱対策
寒冷地では霜柱ができて苗が浮き上がることがあります。浮き上がった苗を見つけたら、すぐに土を寄せて根を埋め戻します。放置すると根が乾燥して枯れてしまうため、冬の間は定期的に畝を見回ることが大切です。
相性の良い野菜と一緒に植える
コンパニオンプランツとして相性の良い野菜を一緒に植えることで、病害虫を減らし互いの生育を促進できます。玉ねぎと好相性の野菜を選んで混植することが、成功への近道です。
ニンジンとの混植
ニンジンと玉ねぎはコンパニオンプランツの代表的な組み合わせです。玉ねぎ栽培ナビによると、ニンジンは玉ねぎの害虫を予防する効果があり、玉ねぎはニンジンの根を侵す病気を予防する効果があるとされています。ただしニンジンの品種によっては栽培期間が合わないものがあるため、できるだけ栽培期間が重なる品種を選びましょう。
ナス科野菜との相性
トマト、ナス、ピーマンなどのナス科野菜も玉ねぎと好相性です。玉ねぎが放つ硫黄化合物の揮発成分が、ナス科野菜につくアブラムシやハダニを遠ざける効果があります。春に玉ねぎを収穫した後の畝に、夏野菜としてナス科を植える輪作体系も効率的です。
ハーブとの組み合わせ
カモミールやマリーゴールドなどのハーブ類も、玉ねぎの害虫を遠ざける効果があります。畝の周囲に植えることで、害虫の侵入を防ぐバリアとなります。見た目も美しく、収穫後はハーブティーや観賞用としても楽しめます。
| コンパニオンプランツ | 効果 |
|---|---|
| ニンジン | 互いの害虫を予防し合う |
| トマト・ナス・ピーマン | 玉ねぎがアブラムシを忌避 |
| レタス | 玉ねぎが害虫を遠ざける |
| カモミール | 害虫忌避・生育促進 |
プランター栽培なら失敗しにくい
庭の土壌環境に不安がある場合は、プランター栽培がおすすめです。容器栽培なら土壌の質を完全にコントロールでき、連作障害の心配もほとんどありません。
プランターのサイズと種類
玉ねぎ栽培には深さ20センチから25センチ以上のプランターが必要です。標準的な710型プランター(長さ70センチ、幅30センチ、深さ25センチ)なら、8株から10株程度栽培できます。円形プランターの場合は、直径30センチ以上で深さ25センチ以上のものを選びます。プランターの底には必ず排水穴があることを確認しましょう。
用土の選び方
市販の野菜用培養土を使えば、pH調整や肥料配合の手間が省けて初心者でも簡単に始められます。自分で配合する場合は、赤玉土6、腐葉土3、バーミキュライト1の割合で混ぜ、苦土石灰と緩効性化成肥料を加えます。プランターの底には鉢底石を3センチから5センチ程度敷いて、排水性を確保します。
プランター栽培の利点
プランター栽培の最大の利点は、毎年新しい土に入れ替えられるため連作障害が起こりにくいことです。また、ベランダや玄関先など日当たりの良い場所に移動できるため、最適な栽培環境を選べます。水やりや追肥の管理もしやすく、病害虫の発見も早期にできるため、初心者には特におすすめの栽培方法です。
適切な収穫時期を見極める
玉ねぎの収穫適期を正しく見極めることは、貯蔵性の良い玉ねぎを得るために重要です。早すぎても遅すぎても品質が落ちてしまいます。
収穫のタイミング
玉ねぎの収穫時期は、品種や植え付け時期によって異なりますが、一般的には5月中旬から6月中旬です。収穫の目安は葉が7割から8割倒れたタイミングです。葉が自然に倒れることで、養分が玉に集中して充実した玉になります。全ての葉が倒れるまで待つと、腐敗が始まることもあるため注意が必要です。
収穫方法と乾燥
収穫は晴天が2日から3日続いた後の朝に行います。株元を持って引き抜き、そのまま畝の上で1日から2日天日干しします。その後、風通しの良い日陰で2週間から3週間吊るして乾燥させます。十分に乾燥させることで、貯蔵性が高まり長期保存が可能になります。葉を3本から5本束ねて紐で縛り、軒下などに吊るす方法が一般的です。
よくある質問
- 玉ねぎは植えっぱなしでも育ちますか?
-
玉ねぎは植えっぱなしでは良好に育ちません。適切な追肥、水やり、病害虫管理が必要です。特に追肥を怠ると玉が大きくならず、病害虫対策をしないと葉が食害されて収穫できなくなります。また、雑草が繁茂すると養分を奪われるため、定期的な除草も必要です。
- 玉ねぎの隣に植えてはいけない野菜は何ですか?
-
マメ科植物のインゲン、大豆、エンドウ、同じネギ属のニンニク、ニラ、長ネギは避けるべきです。マメ科は玉ねぎの硫黄化合物によって根粒菌の働きが阻害され、同じネギ属は共通の病害虫が蔓延しやすくなります。アブラナ科のキャベツやブロッコリーも栄養競合が起こるため近くに植えない方が良いでしょう。
- 玉ねぎは連作障害が出ますか?
-
玉ねぎは他の野菜に比べると連作障害が出にくい作物ですが、全く出ないわけではありません。同じ場所で毎年栽培すると、土壌中に病原菌が蓄積して白絹病や首腐れ病などが発生しやすくなります。理想的には3年から4年は同じ場所での栽培を避け、輪作することが推奨されます。
- 苗を植えるときの注意点は何ですか?
-
最も重要なのは浅植えにすることです。指の第2関節程度、約3センチから4センチの深さに植えます。深植えにすると玉の形が悪くなり、首が太くなって貯蔵性が落ちます。また、草丈20センチから25センチ、茎の太さ5ミリから7ミリ程度の良質な苗を選ぶことも大切です。植え付け後はたっぷりと水やりをして根を土に密着させます。
- 芽が出た玉ねぎを植えても大きくなりますか?
-
スーパーで買った芽が出た玉ねぎを植えても、大きな玉には育ちません。市販の玉ねぎは発芽抑制剤で処理されており、生命力が低下しています。植えると分球して小さな玉がいくつもできたり、ネギ坊主ができてエネルギーが花の生産に使われたりします。緑の葉はネギとして食べられますが、新たな大きな玉の収穫は期待できません。
- 玉ねぎの追肥はいつまで行えば良いですか?
-
追肥は2月末までに終わらせることが重要です。3月以降に追肥を続けると、玉が軟らかくなって貯蔵性が落ち、腐敗しやすくなります。基本的には12月下旬に1回目、2月下旬に2回目の計2回で十分です。春になって玉が肥大し始めたら、肥料は与えずに玉を締めることに専念します。
- プランターで何株くらい栽培できますか?
-
標準的な710型プランター(長さ70センチ、幅30センチ、深さ25センチ)で8株から10株程度栽培できます。株間を10センチ程度確保して植え付けます。円形プランターの場合は直径30センチで3株から4株が目安です。プランターは深さ20センチ以上あるものを選び、底には必ず鉢底石を敷いて排水性を確保しましょう。
- 冬の間に葉が枯れてきたのですが大丈夫ですか?
-
冬の間に外側の葉が多少枯れるのは正常な生理現象です。玉ねぎは寒さに強い野菜なので、中心部の新しい葉が元気であれば問題ありません。ただし、全体的に黄色く変色して生育が止まっている場合は、霜柱による根の浮き上がりや病気の可能性があります。霜柱で浮いた苗は土寄せをして根を埋め戻しましょう。
玉ねぎ栽培を成功させるポイント
- 植え付け2週間前に苦土石灰で土壌pHを6.0から7.0に調整する
- 堆肥と腐葉土を投入して排水性と保水性を改善する
- 15センチから20センチの高畝を作って水はけを確保する
- 草丈20センチから25センチ、茎の太さ5ミリから7ミリの良質な苗を選ぶ
- 指の第2関節程度の深さに浅植えする
- マメ科やネギ類など相性の悪い野菜を近くに植えない
- ニンジンやナス科野菜などコンパニオンプランツを活用する
- 追肥は12月下旬と2月下旬の2回、3月以降は行わない
- 黒マルチやワラでマルチングして保温と泥跳ね防止
- 霜柱で浮いた苗は土寄せして根を保護する
- べと病やネギハモグリバエなど病害虫を早期発見して対処する
- 葉が7割から8割倒れたタイミングで収穫する
- 収穫後は十分に天日干しして乾燥させる
- 庭土に不安がある場合はプランター栽培を選択する
- 連作障害を避けるため3年から4年は同じ場所での栽培を空ける