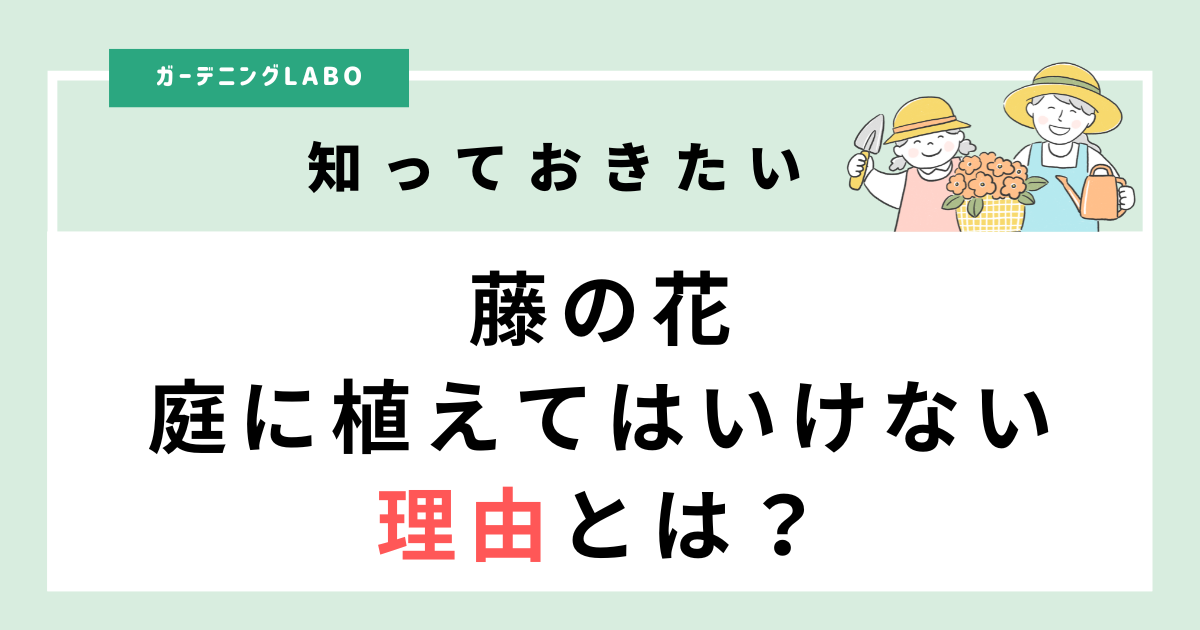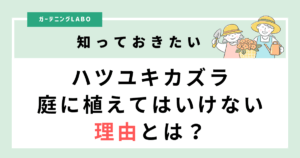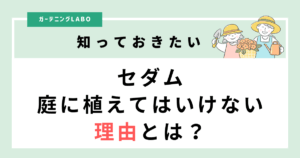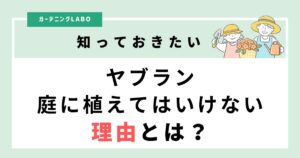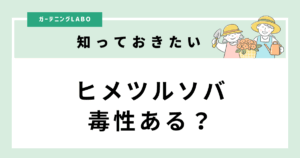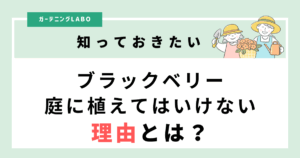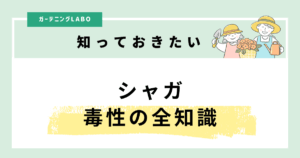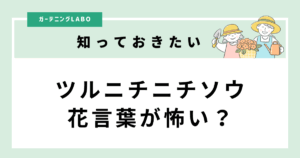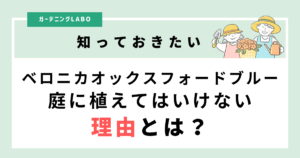美しい藤の花に憧れて、庭に植えようかと考えている方も多いのではないでしょうか。春になると紫や白の花房が垂れ下がる姿は、確かに風情があって素敵ですよね。
でも、ちょっと待ってください。
実は藤の花を庭に植えてはいけないという声が、園芸の世界では昔から根強くあるんです。縁起が悪いとか風水的によくないという話もあれば、実際に育ててみて大変な目に遭ったという体験談も少なくありません。魔除けや幸運の象徴として大切にされてきた一方で、地植えにすると根の深さや繁殖力の強さから除去が困難になり、手入れ方法や育て方を知らないまま植えてしまって後悔する人が後を絶たないのです。
この記事では、藤の花を庭に植えてはいけないと言われる理由を、風水や縁起の観点から実際の栽培上の問題まで、徹底的に解説していきます。ただし、だからといって藤を諦める必要はなく、鉢植えで小さく育てる方法や植え替え時期、増やし方や種から育て方など、安全に楽しむ方法もお伝えしますね。また、これだけは庭に植えてはいけない花草木との比較や、万が一食べる場合の注意点なども触れていきます。
- 藤の花を庭に植えてはいけない具体的な理由が縁起・風水・実害の両面から理解できる
- 根の深さや繁殖力など藤特有の問題と除去の困難さが分かる
- 地植えを避けて鉢植えで小さく育てる安全な方法が学べる
- 藤以外に庭に植えてはいけない植物との比較で判断基準が身につく
藤の花を庭に植えてはいけない5つの理由【デメリットを徹底解説】

藤の花の美しさに魅了されて庭に植えたくなる気持ち、よく分かります。でも、実際に植えてから「こんなはずじゃなかった」と後悔する人が驚くほど多いんです。
ここからは、なぜ藤の花を庭に植えてはいけないのか、その具体的な理由を詳しく見ていきましょう。
縁起が悪いと言われる理由と風水的な意味
藤の花が縁起が悪いと言われる理由、気になりますよね。実はこれ、いくつかの説があって一概には言えないんです。
まず一つ目の説は、藤という漢字が「家を覆う草冠」と「喪服の色を連想させる」ことから来ているというもの。確かに言葉の響きだけで見ると、家に何かが覆いかぶさるイメージって、あまり良い感じはしませんよね。
風水から見た藤の評価
風水の観点から見ると、藤の評価は実は賛否両論なんです。
ネガティブな見方としては、つる性植物が家に絡みつくことで気の流れを妨げるという考え方があります。つるが家の壁や屋根に這い上がると、まるで家を締め付けているように見えて、住む人の運気を下げてしまうという説ですね。
とはいえ、地域によっては全く逆の解釈もあるんです。
藤は古くから魔除けの力があるとされ、神社仏閣でも大切にされてきた植物です。紫色の花は高貴な色として扱われ、幸運を呼び込むシンボルとして珍重されてきた歴史もあります。
「不治」との語呂合わせによる忌避
もう一つ、縁起が悪いとされる大きな理由があります。それは「藤(ふじ)」が「不治(ふじ)」と同じ発音だということ。
特に病気療養中の方がいる家庭では、この語呂合わせを気にして藤を避ける傾向があるようです。日本人は縁起を大切にする文化がありますから、こういった音の連想から敬遠されることは珍しくありません。
ただ、ここで考えてほしいのは、縁起の良し悪しは地域や時代、個人の価値観によって大きく変わるということ。実際、藤の名所として知られる神社や公園は全国にたくさんありますし、藤棚を設けている一般家庭も存在します。
| 藤に対する考え方 | 根拠 | 地域性 |
|---|---|---|
| 縁起が悪い | 「不治」との語呂合わせ、家を覆うイメージ | 一部の地域で強い |
| 魔除けになる | 古来からの信仰、神社での栽培 | 神道の影響が強い地域 |
| 幸運の象徴 | 紫色の高貴さ、長寿のシンボル | 貴族文化の名残がある地域 |
つまり、縁起の問題は個人の信念次第なんですね。ただし、次に説明する実害の方は、信念とは関係なく現実的な問題として降りかかってきます。そちらの方がよほど深刻かもしれません。
根の深さと繁殖力がもたらす実害
ここからが本題です。藤の花を庭に植えてはいけない最大の理由は、縁起よりも何よりも、その驚異的な根の深さと繁殖力にあります。
私が実際に聞いた話では、庭に藤を地植えした数年後、家の基礎にひびが入ったというケースもあったんです。最初は「まさか藤のせいでは」と思っていたそうですが、調べてみると根が想像以上に広がっていたと。
藤の根はどこまで伸びるのか
藤の根の深さは、一般的に地下2メートル以上に達すると言われています。しかも厄介なのは、深さだけじゃないんですよね。
横方向への広がりはさらに驚異的で、樹冠(木の枝葉が広がる範囲)の2倍から3倍、つまり10メートル以上も広がることがあります。これは一般的な住宅の敷地を軽く超えてしまう距離です。
根が深く広く張るということは、以下のような実害をもたらします。
建物の基礎や配管への影響
藤の根は成長する過程で、わずかな隙間にも入り込んでいく性質があります。そうすると何が起こるか。
まず、住宅の基礎コンクリートの継ぎ目や亀裂に根が侵入します。最初は髪の毛ほどの細さでも、成長するにつれて太くなり、その圧力でコンクリートを押し広げてしまうんです。想像してみてください。あなたの家の土台が、じわじわと植物の根に押し広げられていく様子を。
さらに深刻なのが配管への影響です。
地中に埋設されている水道管や排水管にも根が到達し、継ぎ目から管の中に侵入して詰まりを起こすケースが報告されています。水道修理業者に依頼すると、管の中から藤の根がびっしりと詰まっていた、なんていう恐ろしい話も。修理費用は数十万円かかることも珍しくありません。
隣家への侵入という最悪のシナリオ
地植えした藤の根は、当然ながら敷地境界を認識してくれません。隣の家の庭にまで根を伸ばし、そこで同じような被害を引き起こす可能性があります。
これが原因で近隣トラブルに発展したケースは、実は少なくないんです。隣人の庭の植物が枯れた、家の基礎が傷んだなどのクレームを受け、最終的には訴訟に発展した例まであります。
| 被害の種類 | 発生時期の目安 | 修復費用の相場 |
|---|---|---|
| 基礎コンクリートの破損 | 植栽後5〜10年 | 10万円〜50万円以上 |
| 配管の詰まり・破損 | 植栽後3〜7年 | 5万円〜30万円 |
| 舗装面の隆起 | 植栽後3〜5年 | 3万円〜15万円 |
| 他の植物の衰弱 | 植栽後2〜4年 | 植え替え費用数万円 |
他の植物を圧迫する支配力
藤は地下だけでなく、地上部分でも他の植物を圧倒します。
つるが周囲の植物に絡みつき、日光を遮って成長を妨げるだけでなく、根も密集して土中の養分と水分を独占してしまいます。結果として、藤の周辺では他の植物がほとんど育たなくなるんですね。
庭全体のバランスを考えて様々な植物を配置しても、藤一本で台無しになってしまう。これも見過ごせない問題です。
つる性植物特有の管理の大変さ
藤は美しいんですが、その美しさを保つためには相当な労力が必要なんです。ここを軽く見て地植えしてしまうと、後々大変な目に遭います。
つるの伸長スピードは想像以上
藤のつるは、生育期には1日で数センチから10センチ近くも伸びることがあります。「ちょっと目を離した隙に」というのが本当に起こるんですよね。
しかも困ったことに、つるは自分の意思で(もちろん植物に意思はありませんが)伸びる方向を決めてくれません。雨樋に絡みついたり、外壁を這い上がったり、電線に到達したりと、放置すればあらゆる方向に無秩序に伸びていきます。
剪定の頻度と必要な技術
藤を美しく保つためには、年に最低2回、できれば3回以上の剪定が必要とされています。しかもこれ、ただ適当に切ればいいというものじゃないんです。
花芽をつける短枝と栄養成長する長枝を見分けて、適切な位置で切る必要があります。間違った剪定をすると、翌年花が咲かなくなったり、逆につるばかりが茂って手に負えなくなったりします。
さらに厄介なのが、高所での作業が必要になること。藤棚は通常2メートル以上の高さに設置しますから、脚立に乗っての作業が避けられません。慣れていない人がやると、転落のリスクもあります。
藤棚の設置と維持にかかるコスト
藤を地植えするなら、ほぼ確実に藤棚が必要になります。これがまた、思った以上に大変なんです。
しっかりした藤棚を作るには、初期費用だけで10万円から30万円程度かかることも珍しくありません。木製なら腐食対策、金属製なら錆止め処理など、定期的なメンテナンスも必要です。
| 項目 | 初期費用 | 年間維持費 |
|---|---|---|
| 簡易的な藤棚(2m×3m程度) | 5万円〜10万円 | 1万円〜3万円 |
| 本格的な藤棚(4m×5m程度) | 15万円〜30万円 | 3万円〜5万円 |
| 業者による剪定作業(年2回) | – | 3万円〜8万円 |
| 誘引用資材・補修費 | 1万円〜3万円 | 5千円〜2万円 |
そして忘れてはいけないのが、藤の重量です。成熟した藤は、つると葉だけで数百キロの重さになることがあります。藤棚はこの重量に耐えられる頑丈な構造が必要で、設計を間違えると棚が崩落する危険性もあるんです。
放置した場合のリスク
「じゃあ、手入れしなければいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、それが最悪の選択になります。
放置された藤は、雨樋に絡みついて排水を妨げ、雨漏りの原因になります。外壁に這い上がって塗装を傷めたり、屋根に到達して瓦をずらしたりすることも。台風などの強風時には、重量のあるつるが建物に大きな負荷をかけます。
つまり、地植えした藤は「管理するか、建物を傷めるかの二択」を迫られるわけです。どちらにしても大変ですよね。
庭に地植えしてはいけない植物との比較
実は藤だけじゃなく、庭に地植えすると後悔する植物は他にもあります。ここでは、これだけは庭に植えてはいけない花草木として有名なものと、藤を比較してみましょう。
「藤だけが危険なの?」「他の植物と比べてどうなの?」という疑問を持っている方も多いはずです。
危険度トップ5の植物たち
園芸の世界で「これだけは庭に植えてはいけない」とよく言われる植物を、藤と合わせて紹介します。
| 植物名 | 主な問題点 | 危険度 |
|---|---|---|
| 竹・笹 | 地下茎で猛烈に増殖、除去ほぼ不可能、隣家侵入 | ★★★★★ |
| 藤 | 根の広がり、建物への被害、管理の大変さ | ★★★★☆ |
| ドクダミ | 地下茎で増殖、強い臭い、根絶困難 | ★★★★☆ |
| ミント類 | 地下茎で爆発的に増殖、他の植物を駆逐 | ★★★☆☆ |
| 桜(大木になる品種) | 根が浅く広範囲に広がる、落ち葉が多い、害虫 | ★★★☆☆ |
竹・笹:最強の侵略者
竹や笹は、おそらく庭に植えてはいけない植物のナンバーワンでしょう。藤よりもさらに厄介です。
地下茎が縦横無尽に広がり、コンクリートの下をくぐって隣家の庭に侵入します。しかも除去がほぼ不可能というレベルで、一度根付くと完全に駆除するのに数年から十数年かかることも。藤は管理が大変ですが、竹ほどではありません。
ドクダミ:悪臭との戦い
ドクダミは薬草としても知られていますが、庭に植えるのは避けた方がいい植物の代表格です。
藤ほど大きくはなりませんが、地下茎で増殖する能力は驚異的で、しかも抜こうとすると独特の強い臭いを放ちます。根が少しでも残っていればそこから再生するため、完全除去は困難。藤と比べると被害の規模は小さいものの、嫌悪感という意味では上回るかもしれません。
ミント類:緑の絨毯の恐怖
「ハーブだから大丈夫」と思って植えると痛い目に遭うのがミントです。
桜:美しいが厄介な巨木
桜は日本人の心の花ですが、一般家庭の庭には向きません。
大きくなる品種は高さ10メートル以上に成長し、根は浅く広範囲に広がります。落ち葉の量も膨大で、毛虫などの害虫もつきやすい。藤と似た問題を抱えていますが、藤の方が管理の難易度は高いかもしれません。
藤が特に危険とされる理由
これらの植物と比較して、藤が特に問題視される理由は何でしょうか。
それは、「美しさゆえに安易に植えてしまう人が多い」という点にあります。竹やドクダミは最初から警戒されがちですが、藤は美しい花のイメージが先行して、リスクが軽視されやすいんです。
さらに、被害が多岐にわたることも特徴です。根の問題、つるの問題、管理の問題、コストの問題と、様々な側面で困難が生じます。
植える前のチェックリスト
もしどうしても庭に新しい植物を植えたいと思ったら、以下のポイントを必ず確認してください。
□ 成長後の最大サイズを把握していますか?
□ 根の広がり方を理解していますか?
□ 繁殖力や増殖の方法を知っていますか?
□ 定期的な管理にかかる時間とコストを見積もっていますか?
□ 除去が必要になった場合の方法を調べましたか?
□ 近隣への影響を考慮していますか?
□ 代替案(鉢植えなど)を検討しましたか?
この全てに自信を持って「はい」と答えられないなら、地植えは見送った方が賢明です。
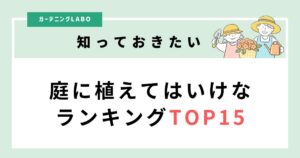
除去・撤去の困難さとコスト
「もう植えちゃったんだけど、やっぱり撤去したい」という場合、どうなるのでしょうか。残念ながら、ここが藤の最も恐ろしいところなんです。
一度地植えした藤を除去するのは、想像以上に困難で、高額な費用がかかります。
なぜ藤の除去は難しいのか
藤の根は前述の通り、地下深く、そして広範囲に張り巡らされています。地上部分を切り倒しても、根が残っていれば何度でも芽を出してくるんです。
しかも厄介なことに、藤の根は非常に太く頑丈。スコップで掘り起こそうとしても、簡単には切れません。チェーンソーが必要になることもあります。
根が建物の基礎や配管に絡んでいる場合、それらを傷つけずに除去するのはほぼ不可能です。最悪の場合、基礎の補修や配管の交換が必要になることもあります。
DIYでの除去は可能か
「業者に頼まず、自分でなんとかできないかな」と考える方もいるでしょう。正直に言いますと、かなり厳しいです。
若い苗木のうちならまだしも、数年経って根が張ってしまった藤をDIYで除去しようとすると、膨大な時間と労力がかかります。実際にやった人の体験談を見ると、「毎週末作業して半年かかった」「結局諦めて業者に頼んだ」という声が多いんです。
さらに、除草剤の使用にも限界があります。藤は生命力が強いため、一般的な除草剤では完全に枯らすことが難しく、強力な薬剤を使えば周辺の植物や土壌にも影響が出ます。
業者に依頼した場合の費用相場
専門業者に藤の除去を依頼すると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
| 藤の規模 | 作業内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 小規模(植栽後2〜3年) | 伐採・抜根 | 5万円〜15万円 |
| 中規模(植栽後5〜10年) | 伐採・抜根・廃棄 | 15万円〜40万円 |
| 大規模(植栽後10年以上) | 伐採・抜根・土壌改良 | 40万円〜100万円以上 |
| 建物への被害がある場合 | 上記に加え補修工事 | 50万円〜200万円以上 |
これらの金額は、あくまで目安です。藤の大きさや根の広がり具合、周辺環境によって大きく変動します。
特に注意が必要なのは、建物や配管に被害が出ている場合。藤の除去費用に加えて、基礎の補修や配管の交換費用が別途必要になります。合計すると数百万円に達することも。
除去にかかる期間
費用だけでなく、時間も相当かかります。
業者に依頼した場合でも、完全な除去には数ヶ月から1年程度かかることがあります。一度掘り起こした後も、残った根から新芽が出てこないか経過観察が必要なためです。
DIYの場合は、前述のように半年から1年以上かかることも珍しくありません。しかも、その間ずっと庭の一部が工事現場のような状態になります。
実際に藤を植えて後悔した事例
ここまで理論的な話をしてきましたが、実際のところどうなのか。リアルな体験談を見ていきましょう。
インターネット上の質問サイトや園芸フォーラムには、藤を植えて後悔している人の声がたくさん見つかります。
ケース1:「園芸ツウ」でも手に負えなかった
ある質問サイトでは、こんな投稿がありました。

「よく自宅の軒先に藤棚を作ってフジをはわせてる家を見かけますが、こういうのをする家って園芸ツウの中でもかなりツウな人のいる家ってことなんでしょうか?」
この質問への回答を見ると、「園芸に詳しい人でも、藤の管理は大変だと感じている」という声が多数ありました。つまり、藤を美しく保つには、単なる園芸好きというレベルを超えた、相当な知識と労力が必要だということです。
実際、「祖父の代から藤棚があったが、高齢で管理できなくなり、結局撤去した」という例も。何十年も大切にしてきた藤でも、維持できなくなれば諦めざるを得ないんです。
ケース2:隣家とのトラブルに発展
別の投稿では、こんな深刻な事例がありました。
「庭に植えた藤の根が、知らないうちに隣の家の庭まで伸びていた。隣家の植木が次々に枯れ始め、最初は原因が分からなかったが、調べてみたら藤の根が地下で絡みついていた。隣人から撤去と損害賠償を求められ、最終的に100万円以上の出費になった」
これは決して珍しい話ではありません。根は敷地境界を認識しないため、気づかないうちに隣地に侵入します。近所付き合いまで壊してしまうリスクがあるんです。
ケース3:予想外の被害が次々と
ある家では、こんな連鎖的な被害に見舞われたそうです。
「最初は雨樋が詰まって雨漏りがするようになった。修理してもらったら、藤のつるが原因だと分かった。それで剪定を始めたが、今度は根が配水管に侵入して詰まりが発生。配管の交換工事が必要になった。さらに、外壁に這い上がったつるの跡が残り、塗装の塗り直しも。全部で150万円近くかかった」
一つの問題が次々と別の問題を引き起こす。これが藤の怖いところです。
ケース4:売却時の障害に
意外と知られていないのが、不動産売却時の問題です。
「転勤で家を売ることになったが、庭の藤が原因で買い手がつかない。不動産業者からは『藤を撤去しないと売れない』と言われ、急遽撤去費用を負担することになった。しかも撤去に時間がかかり、転勤の予定が狂った」という例もあります。
藤のある家は、購入者側から見るとリスクとして捉えられることが多いんです。美しい庭の演出のつもりが、資産価値を下げる要因になってしまうこともある。
共通する後悔のポイント
これらの事例に共通するのは、「最初は軽い気持ちで植えた」という点です。
「少し手間がかかるくらいだろう」「うちの庭は大丈夫だろう」という楽観的な見通しが、後々の大きな後悔につながっています。藤の美しさに魅せられて、リスクを過小評価してしまうパターンが非常に多いんですね。
それでも藤を植えたい場合の最低条件
ここまで散々脅すようなことを書いてきましたが、「それでもやっぱり藤が好きなんだ」という方もいるでしょう。その気持ち、分かります。
もしどうしても地植えにこだわるなら、最低限これだけは満たしてほしい条件があります。
1. 広大な敷地があること
最低でも200平方メートル(約60坪)以上、できれば500平方メートル(約150坪)以上の庭があることが望ましいです。藤の根が広がっても他の構造物や隣地に影響しない距離を確保できる広さが必要です。
2. 専用の頑丈な藤棚を設置できること
建物から十分に離れた場所に、藤の重量に耐えられる本格的な藤棚を設置できること。木製なら太い柱と梁、金属製なら錆びにくい素材を使った、長期的に使用できる構造が必要です。
3. 定期的な剪定と管理ができること
年に2〜3回、高所での作業も含めた剪定ができる体力と時間、または業者に依頼できる経済的余裕があること。これは何十年も続けられる体制である必要があります。
4. 将来的な撤去も想定していること
いざという時に撤去できる費用を確保しておくこと。また、次の世代に負担を残さないための計画があること。相続や売却の際に問題にならないよう、家族で話し合っておくことも大切です。
これらの条件を全てクリアできるなら、地植えも選択肢に入るかもしれません。ただし、それでもリスクがゼロになるわけではありません。
とはいえ、多くの一般家庭ではこれらの条件を満たすのは難しいでしょう。そんな時は、次のセクションで紹介する代替案を検討してみてください。
藤の花を庭に植えてはいけない場合の安全な楽しみ方


さて、ここまで読んで「じゃあ藤は諦めるしかないのか」と思った方、安心してください。地植えしなくても、藤を楽しむ方法はちゃんとあるんです。
むしろ、これから紹介する方法の方が、一般家庭には向いているかもしれません。
鉢植えで小さく育てる方法
藤の花を庭に植えてはいけない理由の多くは、地植えによる根の広がりと管理の困難さでした。ならば、鉢植えにすればこれらの問題をほぼ解決できるんです。
「え、藤って鉢植えでも育つの?」と驚く方もいるかもしれませんが、実は鉢植えの藤は昔から盆栽として親しまれてきた歴史があります。
鉢植えのメリット
鉢植えにすることで、どんな利点があるのでしょうか。
適切な鉢のサイズと種類
鉢植えで藤を育てる場合、鉢選びが重要になってきます。
最初は7号鉢(直径21cm程度)から始めて、成長に合わせて10号鉢(直径30cm程度)まで大きくするのが一般的です。それ以上大きな鉢にすると、重くて移動が困難になるため、通常は10号程度で止めます。
鉢の素材は、通気性の良い素焼き鉢がおすすめです。プラスチック鉢でも育ちますが、夏場の根の蒸れに注意が必要。重くて移動しにくいですが、陶器の鉢も見た目が美しく藤に合います。
| 鉢のサイズ | 藤の樹齢目安 | 期待できる花房の長さ |
|---|---|---|
| 7号鉢(直径21cm) | 1〜2年生 | 10〜15cm程度 |
| 8号鉢(直径24cm) | 2〜3年生 | 15〜20cm程度 |
| 10号鉢(直径30cm) | 3年生以上 | 20〜30cm程度 |
小さく育てるコツ
鉢植えで藤を小さく保つには、いくつかのテクニックがあります。
まず、根域を制限すること。これは鉢植えにすることで自然と実現できますが、さらに効果を高めるなら、植え替え時に根を3分の1程度剪定します。こうすることで、地上部の成長も抑えられるんです。
次に、花後の剪定を徹底すること。花が咲き終わったら、すぐに花柄を切り落とし、新しく伸びたつるも短く切り詰めます。これを怠ると、あっという間に暴れてしまいます。
盆栽仕立てにすると、さらにコンパクトに楽しめます。針金で枝の形を整え、不要な芽を摘み取ることで、高さ30〜50cm程度の小さな藤でも美しい花を咲かせることができます。盆栽の藤は、毎年花を楽しめる上に、場所も取らず、管理も比較的簡単です。
植え替え時期と方法
鉢植えの藤は、2〜3年に一度の植え替えが必要になります。
植え替え時期は、休眠期である11月から2月頃がベストです。この時期なら根を少し切っても植物へのダメージが最小限で済みます。
植え替えの手順は以下の通りです。
1. 鉢から株を抜き出す
鉢の縁を軽く叩いて、根鉢を緩めます。固い場合は、鉢底の穴から棒で押し出します。
2. 古い土を落とす
根鉢の周りの古い土を、箸などで優しく崩して落とします。全部落とす必要はなく、3分の1程度で十分です。
3. 根を剪定する
傷んだ根や長く伸びすぎた根を、清潔なハサミで切ります。全体の根量の3分の1程度を目安に。
4. 新しい土で植え直す
水はけの良い培養土を使い、根の隙間にもしっかり土が入るよう、箸で突きながら植え付けます。
5. たっぷり水やり
植え替え後は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。
植え替え後1〜2週間は、直射日光を避けた半日陰で管理してください。新しい根が伸び始めるまでの回復期間です。
育て方の基本
鉢植えの藤は、基本的な育て方さえ押さえれば、初心者でも十分楽しめます。
水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。夏場は毎日、冬場は2〜3日に一度が目安です。ただし、鉢の大きさや置き場所によって変わるので、土の乾き具合をチェックする習慣をつけましょう。
肥料は、春と秋に緩効性の固形肥料を鉢の縁に置きます。花後のお礼肥も忘れずに。液体肥料を月に1〜2回与えるのも効果的です。
日当たりは、できるだけ良い場所に置いてください。半日以上日が当たる場所が理想的です。ただし、真夏の西日が強すぎる場合は、午後だけ日陰になる場所に移動するといいでしょう。
藤を増やしたい・種から育てたい人へ
鉢植えの藤を上手に育てられるようになったら、「もう一鉢増やしたいな」と思うかもしれません。または、「種から育ててみたい」という冒険心が湧いてくることも。
ここでは、藤の増やし方について簡単に紹介します。
挿し木での増やし方
藤を増やす最も簡単で確実な方法は、挿し木です。
適期は6月から7月の梅雨時。今年伸びた若い枝を10〜15cm程度の長さで切り取り、下の葉を取り除いて挿し穂にします。発根促進剤をつけてから、清潔な挿し木用土に挿し、明るい日陰で管理すれば、1〜2ヶ月で根が出てきます。
挿し木のメリットは、親株と同じ性質の株が得られること。花の色や大きさ、香りなども同じになります。
取り木という方法も
もう一つ、取り木という方法もあります。これは、枝を親株につけたまま根を出させる技術です。
枝の一部に傷をつけて、そこに湿らせた水苔を巻き、ビニールで覆います。数ヶ月すると傷の部分から根が出てくるので、それを切り離して植え付けるんです。挿し木よりも大きな株が得られる利点があります。
種から育てる場合の注意点
「種から育ててみたい」という方もいるでしょう。できないことはありませんが、いくつか知っておくべきことがあります。
まず、種から育てると花が咲くまで5〜10年かかることを覚悟してください。挿し木なら2〜3年で咲き始めるのに比べると、かなり長い時間が必要です。
また、親株と同じ花が咲く保証がないという点も重要です。種から育てた場合、遺伝的な組み合わせによって、親とは違う花が咲くことがあります。これを楽しみと捉えるか、不確実性と捉えるかは人それぞれですね。
種まきの時期は秋から冬。藤の種は非常に硬い皮に覆われているため、種皮に傷をつける(カッターで軽く切り込みを入れる)か、一晩水に浸けてから蒔くと発芽率が上がります。
初心者には苗からがおすすめ
正直なところ、初めて藤を育てる方には、園芸店で苗を購入することを強くおすすめします。
すでに2〜3年育てられた苗なら、早ければその年か翌年には花を楽しめます。品種も確実で、「こんな花が咲くはずだったのに」というがっかりもありません。
挿し木や種から育てるのは、藤の栽培に慣れてからでも遅くないですよ。まずは育てる楽しさと花を見る喜びを味わってからでも、増やすのは遅くありません。
よくある質問
ここまで読んで、まだ疑問が残っている方もいるかもしれません。よく寄せられる質問をいくつかまとめてみました。
Q1:藤の花は縁起が悪いとされますが、なぜでしょうか?
A:主に「不治」との語呂合わせや、つる性植物が家を覆うイメージから縁起が悪いとされています。ただし、これは地域や個人の信念による部分が大きく、逆に魔除けや幸運の象徴とする地域もあります。科学的根拠はありませんので、気にするかどうかは個人の判断次第です。
Q2:庭に藤を植えてはいけない理由は何ですか?
A:最も大きな理由は、根が地下深く広範囲に広がり、建物の基礎や配管に被害を与える可能性があることです。また、つるの管理が大変で、放置すると建物に絡みついたり隣地に侵入したりします。一度植えると除去が非常に困難で、高額な費用がかかることも大きな理由です。
Q3:庭に植えると運気が上がる花は?
A:風水では、南天(難を転じる)、万両(金運)、ツツジ類(繁栄)、梅(忍耐と成功)などが運気を上げる植物とされています。ただし、運気以上に大切なのは、管理しやすく長く楽しめる植物を選ぶことです。どんなに縁起が良くても、手入れが行き届かず枯れてしまっては意味がありませんからね。
Q4:庭に植えてはいけない植物5選は?
A:特に注意が必要な植物は以下の5つです。
1. 竹・笹:地下茎で猛烈に増殖し、除去がほぼ不可能
2. 藤:根の広がりと管理の困難さ
3. ドクダミ:地下茎で増殖し、強い臭い
4. ミント類:爆発的に増えて他の植物を駆逐
5. 大きくなる桜:根が浅く広がり、落ち葉と害虫の問題
Q5:藤の花は食べることができる?
A:藤の花は食用可能です。天ぷらやお浸しにして食べる地域もあります。ただし、必ず食用として栽培されたものを使用してください。観賞用として農薬を使っているものや、野生のものは避けるべきです。また、種子には毒性があるため絶対に食べないでください。花を食べる場合も、少量から試して体調に異変がないか確認することをおすすめします。
Q6:すでに地植えしてしまった藤、どうすればいい?
A:まだ若い株(植栽後2〜3年以内)なら、早めに掘り起こして鉢植えに移植することを検討してください。すでに大きく育っている場合は、定期的な剪定で成長をコントロールし、根が建物や隣地に影響しないよう注意深く管理する必要があります。どうしても管理できない場合は、専門業者に相談して撤去を検討しましょう。
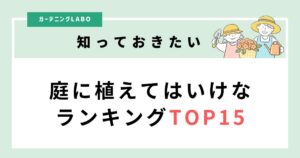
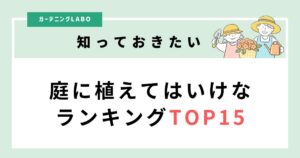
まとめ
藤の花を庭に植えてはいけない理由と、安全に楽しむ方法について詳しく見てきました。最後に、この記事の要点をまとめておきます。
- 藤は「不治」との語呂合わせや風水の観点から縁起が悪いとされることがあるが、地域や個人の信念によって解釈は異なる
- 最大の問題は根が地下2メートル以上、横方向に10メートル以上広がり、建物の基礎や配管に被害を与える可能性があること
- つるの伸長スピードが速く、年2〜3回以上の剪定が必要で、高所作業を伴う管理が大変
- 藤棚の設置と維持に初期費用10万円〜30万円、年間維持費数万円がかかる
- 竹・笹、ドクダミ、ミント、大きくなる桜なども庭に植えてはいけない植物として知られている
- 藤は美しさゆえに安易に植えてしまう人が多く、被害が多岐にわたるため特に注意が必要
- 一度地植えした藤の除去は困難で、業者に依頼すると5万円〜100万円以上の費用がかかる
- 根が残ると何度でも再生するため、完全除去には数ヶ月から1年以上かかることもある
- 実際に藤を植えて隣家トラブルや建物被害、不動産売却時の問題に直面した事例が多数ある
- 地植えするなら200平方メートル以上の広大な敷地と、長期的な管理体制が最低条件
- 鉢植えなら根の広がりを完全にコントロールでき、移動も可能で管理が格段に楽になる
- 7号鉢から始めて10号鉢程度で育てれば、一般家庭でも十分に花を楽しめる
- 鉢植えの藤は2〜3年に一度、11月〜2月の休眠期に植え替えを行う
- 増やすなら挿し木が最も簡単で確実で、6月〜7月の梅雨時が適期
- 種から育てると花が咲くまで5〜10年かかり、親株と同じ花が咲く保証もない
- 初心者は園芸店で2〜3年生の苗を購入するのが最も確実
- 藤の花は食用可能だが、食用として栽培されたもののみを使用し、種子は絶対に食べてはいけない