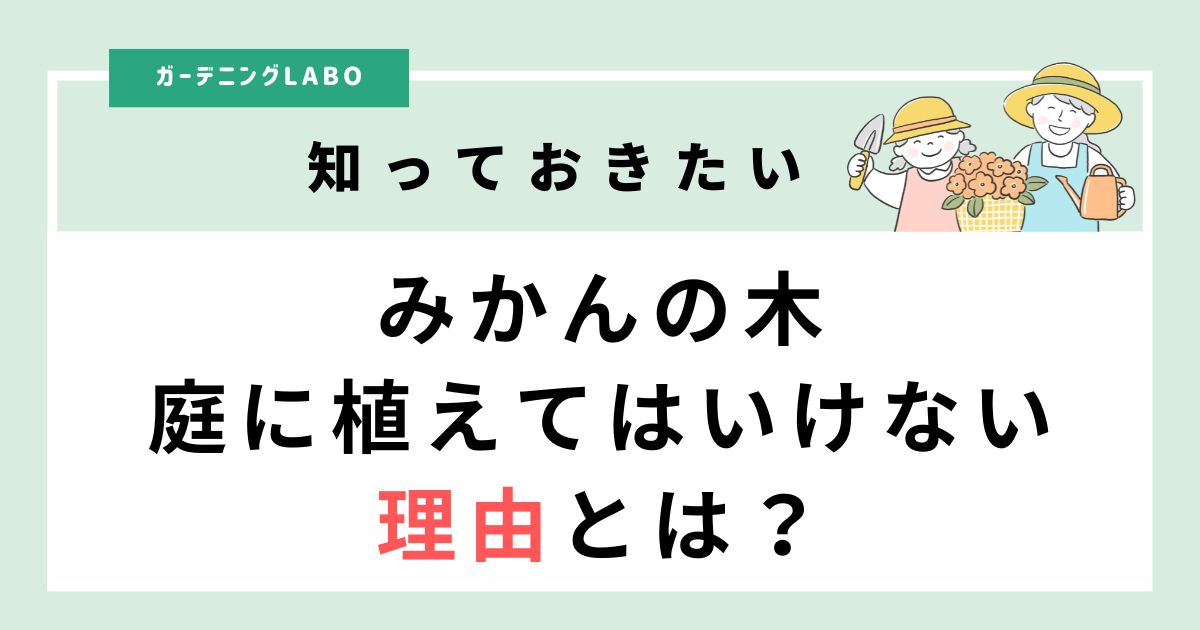「みかんの木を庭に植えたいけど、植えてはいけないって聞いて不安…」そんな声をよく耳にします。
確かに、インターネットで検索すると「みかんの木は庭に植えてはいけない」という情報が出てきますよね。シロアリが寄ってくるとか、風水的に良くないとか、いろんな噂があって心配になる気持ち、よくわかります。
でも実は、これらの心配事の多くは「正しい知識と対策」があれば解決できるんです。
この記事では、みかんの木を庭に植えてはいけないと言われる本当の理由から、庭に植える場合の植える場所の選び方、小さく育てる剪定方法、正しい植え方まで、実践的な情報をお伝えします。さらに、一緒に植えると相性の良い植物や、実がなるまでの期間、みかんの木の寿命といった長期的な栽培のポイントも解説しますね。鉢植えという選択肢や、庭のシロアリ対策、風水の観点からも詳しく見ていきましょう。
- みかんの木を庭に植えてはいけないと言われる本当の理由とその対策方法
- シロアリや風水の心配を解消する正しい植える場所と植え方
- 小さく育てるための剪定テクニックと管理のコツ
- 実がなるまでの期間や寿命、一緒に植える植物など長期栽培の知識
みかんの木を庭に植えてはいけないと言われる理由

「植えてはいけない」と言われる3つの理由
まず最初に、なぜみかんの木が「植えてはいけない」と言われているのか、その理由をしっかり理解しておきましょう。
実は、この噂には確かに根拠があるんです。でも同時に、正しく対処すれば問題ないことも事実なんですよ。
シロアリを寄せ付ける可能性がある
一番よく聞く心配事が、このシロアリの問題ですね。
柑橘類の樹液や根には、シロアリが好む成分が含まれているという研究結果があります。特に、家屋に近い場所にみかんの木を植えると、シロアリが木から家の方へ移動してくるリスクが指摘されているんです。
とはいえ、これは「みかんの木がある=必ずシロアリ被害に遭う」という意味ではありません。
建物から十分な距離を保つこと、定期的に点検すること、この2つを守れば過度に心配する必要はないんですよ。実際、多くの家庭でみかんの木を庭に植えて、何の問題もなく育てているケースがたくさんあります。
風水的に気をつけたい点
次に、風水の観点から見た注意点です。
風水では、トゲのある植物は「殺気」を発するとされています。みかんの木には枝にトゲがあるため、家の鬼門(北東)や裏鬼門(南西)に植えるのは避けた方が良いという考え方があるんですね。
ただ、これも絶対的なルールではないんです。

実は、実がたくさんなる木は「豊かさ」や「繁栄」の象徴とされていて、むしろ縁起が良いとも言われているんですよ。
つまり、適切な場所に植えれば風水的にもプラスの効果が期待できるというわけです。南側や西側に植えるのがおすすめとされていますね。
根が広がって管理が大変になる
3つ目の理由が、根の広がりです。
みかんの木は成長すると、思った以上に根が横に広がっていきます。地上部の樹冠の1.5倍から2倍程度まで根が伸びることもあるんです。
これが何を意味するかというと、隣に植えた他の植物の成長を妨げたり、配管や基礎に影響を与えたりする可能性があるということ。狭い庭だと、後から「こんなはずじゃなかった」となりがちなんですね。
| 懸念事項 | リスクの内容 | 対策方法 |
|---|---|---|
| シロアリ | 樹液や根がシロアリを引き寄せる可能性 | 建物から3m以上離す・定期点検 |
| 風水 | トゲが殺気を発するとされる | 鬼門・裏鬼門を避けて南西側に配置 |
| 根の広がり | 他の植物や構造物への影響 | 十分なスペース確保・剪定管理 |
庭にみかんの木を植える場所の選び方
さて、「植えてはいけない」理由がわかったところで、次は「どこに植えればいいのか」という話に移りましょう。
場所選びを間違えなければ、先ほどの心配事のほとんどは解決できるんです。
建物から適切な距離を保つ
まず何より大切なのが、建物からの距離です。
シロアリ対策として、最低でも3メートル以上離すことをおすすめします。できれば5メートルあると、より安心ですね。この距離があれば、たとえ木にシロアリが寄ってきても、家屋まで到達するリスクがぐっと下がるんです。
また、家の基礎や配管への影響も考慮に入れましょう。根が成長して基礎を押し上げたり、水道管に絡んだりするトラブルも、距離があれば防げます。
ちなみに、エアコンの室外機や給湯器の近くも避けた方が無難です。熱風が当たると木が弱りますし、逆に木が成長して機器のメンテナンスの邪魔になることもありますからね。
日当たりと風通しの良い場所
みかんの木は太陽が大好きな植物です。
1日のうち最低6時間、できれば8時間以上日光が当たる場所が理想的なんですね。日当たりが良ければ、実の付きも甘さも段違いに良くなります。
南向きや東向きの場所がベストですが、西向きでも午後の日差しがしっかり当たるなら問題ありません。ただし、北向きや日陰になりやすい場所は避けましょう。
そして、意外と見落としがちなのが風通しです。
風通しが悪いと、カビや病気、害虫の温床になってしまうんですよ。特に、湿気がこもりやすい場所は要注意。建物の角や塀際など、空気の流れが滞る場所は避けた方が賢明です。
水はけの良い土壌を選ぶ
みかんの木は水はけの良い土壌を好みます。
というのも、根が常に湿った状態だと根腐れを起こしやすいんです。雨が降った後、数時間で水が引くような場所が理想的ですね。
もし粘土質の土壌だったら、諦める必要はありませんよ。



植え付けの際に腐葉土や川砂を混ぜ込めば、水はけを改善できます。後ほど詳しく説明しますね。
風水を気にする場合の配置
風水を意識される方のために、配置のポイントもお伝えしておきましょう。
避けたいのは、鬼門(北東)と裏鬼門(南西)です。これらの方角にトゲのある植物を植えると、家に入る良い気を阻害すると言われているんですね。
一方、おすすめなのは庭の西側や南側。特に西側は「金運」に関わる方角とされていて、黄金色の実がなるみかんとの相性が良いんです。南側は「人間関係運」を司る方角で、実りをもたらす木との相性が抜群ですよ。
小さく育てるための剪定と管理方法
「庭が広くないから、大きな木は困る…」そんな声、よく聞きます。
でも安心してください。みかんの木は、適切な管理をすればコンパクトに育てることができるんです。
矮性台木の品種を選ぶ
まず、苗木を選ぶ段階から工夫できます。
みかんの苗木には「台木」という、接ぎ木の土台となる部分があるんですが、これにカラタチという品種が使われているものを選ぶと良いんです。
カラタチ台木の特徴は、木の成長がゆっくりで、樹高が抑えられること。一般的な台木と比べて、最終的な樹高が1.5倍から2倍程度小さくなると言われているんですよ。
園芸店やホームセンターで苗木を購入する際、「矮性品種」や「カラタチ台木」と表示されているものを探してみてください。少し割高かもしれませんが、長い目で見れば管理が楽になります。
定期的な剪定で樹高をコントロール
小さく育てるための最大のポイントが、剪定です。
みかんの木の剪定は、年に2回行うのが基本。2月から3月の休眠期と、6月から7月の梅雨明けのタイミングがベストです。
樹高は2メートルから3メートルを目安にすると、収穫も管理もしやすいんですね。それ以上伸びてきたら、主幹(中心の太い幹)を思い切って切り戻しましょう。
ただし、一度にバッサリ切りすぎると木がダメージを受けます。毎年少しずつ、全体の3分の1程度を目安に剪定するのがコツですよ。
また、内側に向かって伸びる枝や、交差している枝も切り落としましょう。これだけで、見た目もすっきりして、風通しも良くなります。
根域制限という裏ワザ
もう一つ、プロの農家さんも使っている方法があります。それが根域制限です。
これは、植え付けの際に防根シートや波板を土の中に埋め込んで、根が広がる範囲を物理的に制限する方法なんです。根の広がりが制限されると、地上部の成長も自然と抑えられるんですね。
植え穴を掘る際、周囲に深さ50センチほどの溝を掘って、そこに防根シートを立てるように設置します。少し手間はかかりますが、長期的には管理がとても楽になりますよ。
鉢植えという選択肢も
「地植えにこだわる必要はない」というのも、一つの答えです。
10号以上の大きめの鉢で育てれば、自然とコンパクトなサイズに収まります。しかも、季節に応じて移動できるというメリットもあるんです。
冬の寒さが厳しい地域なら、鉢植えの方が管理しやすいかもしれませんね。ベランダやテラスでも栽培できますし、賃貸住宅の方にもおすすめです。
| 方法 | 実施時期 | 効果 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 矮性台木の選択 | 購入時 | 樹高1.5〜2倍抑制 | 易 |
| 定期剪定 | 2月・6月 | 樹高2〜3m維持 | 中 |
| 根域制限 | 植付時 | 全体的な成長抑制 | 中 |
| 鉢植え栽培 | 随時 | 自然にコンパクト化 | 易 |
正しい植え方の手順とポイント
さあ、いよいよ実際に植えるときのお話です。
植え方一つで、その後の成長が大きく変わってきます。ここは丁寧にやりたいところですね。
植え付けに最適な時期
みかんの木を植えるベストタイミングは、3月から4月です。
この時期は気温が上がり始め、木が活動を再開するタイミング。根がしっかり張る前に暑い夏が来てしまうと、水切れを起こしやすいので、春の植え付けが一番安心なんですね。
とはいえ、秋植えも可能です。9月から10月なら、冬までに根が落ち着く時間があります。ただし、寒冷地では春植えの方が無難ですよ。
植え穴の準備が成功の鍵
まず、植え穴を掘ります。サイズは深さ・幅ともに50センチ以上が目安です。
「そんなに大きく掘らなきゃいけないの?」と思われるかもしれませんね。でも、これには理由があるんです。大きめの穴を掘ることで、根がしっかり張りやすくなるんですよ。
掘り出した土は、そのまま使わないでください。堆肥や腐葉土を3割ほど混ぜ込むのがコツです。これで栄養豊富で、ふかふかの土ができます。
水はけが悪い粘土質の土なら、川砂も2割ほど混ぜましょう。これだけで排水性が格段に良くなります。
農林水産省のガイドラインでも、果樹栽培では土壌改良が重要だと指摘されていますね。少し手間はかかりますが、ここでしっかり準備しておけば、後々の管理がぐっと楽になりますよ。
苗木選びのポイント
苗木は2年生苗を選ぶのがおすすめです。
1年生苗より少し高いですが、根がしっかりしていて、実がつくまでの期間も短くなります。投資する価値はありますよ。
そして、必ず接ぎ木苗を選んでください。実生苗(種から育てた苗)だと、実がなるまで7年から10年もかかってしまうんです。接ぎ木苗なら2年から3年で収穫できます。
購入時は、根の状態もチェックしましょう。白くて元気な根が見えていて、根鉢が崩れていないものが良品です。
植え付けの実際の手順
それでは、実際の植え付け手順を見ていきましょう。
①準備した植え穴の底に、改良した土を少し戻します。
②苗木をポットから慎重に取り出し、根鉢は崩さずにそのまま植え穴に置きます。
③接ぎ木部分が土に埋まらないよう、地表より少し高めに設置してください。接ぎ木部分が埋まると、病気の原因になることがあるんです。
④周りに土を入れながら、軽く押さえていきます。
⑤植え付け後は、たっぷりと水やりをしましょう。土と根の間の空気を追い出すイメージです。
最後に、支柱を立てるのを忘れずに。風で倒れないよう、しっかり固定してあげてくださいね。
シロアリ対策も忘れずに
前述の通り、シロアリは気になるポイントですよね。
植え付けの際に、植え穴周辺の土に防蟻剤を散布しておくと安心です。ホームセンターで購入できる家庭用のもので十分ですよ。
そして、年に一度は木の根元を点検する習慣をつけましょう。早期発見が何より大切です。
実がなるまでの期間と栽培管理
さて、木を植えたら、誰もが気になるのが「いつ実がなるの?」という点ですよね。
ここは少しだけ、気長に待つ心の準備が必要かもしれません。
実がなるまでの一般的な期間
接ぎ木苗を植えた場合、実がなり始めるのは2年から3年後が目安です。
早いものだと、植えた翌年に少し花が咲くこともあります。でも、最初の1、2年は木の成長を優先した方が良いので、花が咲いても摘んでしまうことをおすすめしますよ。
ちなみに、実生苗(種から育てた苗)だと7年から10年もかかります。これが、接ぎ木苗をおすすめする理由なんですね。



「そんなに待てない!」という気持ち、わかります。でも、木が健康に育つための大切な準備期間なんですよ。
実をつけるための管理
実をつけるためには、適切な施肥が欠かせません。
年に3回、3月、6月、11月に肥料を与えるのが基本です。柑橘類専用の肥料が市販されているので、それを使うと簡単ですよ。窒素・リン酸・カリウムがバランス良く配合されています。
水やりは、地植えの場合は基本的に不要です。ただし、夏の日照りが続くときや、植えたばかりの1年目は様子を見て水を与えましょう。
そして、実をたくさんつけすぎたら摘果をしてください。
一つの枝に実が多すぎると、どれも小さくて味も落ちてしまうんです。葉っぱ25枚に対して実1個くらいの割合が理想的とされていますね。
花が咲いても実がならない理由
「花は咲くのに実がつかない」という悩み、実は結構多いんです。
原因はいくつか考えられます。
まず、受粉の問題。みかんは基本的に自家受粉しますが、虫が少ない環境だと受粉がうまくいかないことがあります。そんなときは、筆で花を軽くなでて、人工授粉してあげると良いですよ。
次に、栄養不足。特に窒素が足りないと、花は咲いても実がつきにくくなります。
そして意外と多いのが、剪定のしすぎ。花芽がついた枝を切ってしまうと、当然実はつきません。剪定は適度に、が大切です。
初めての収穫までの準備
若木のうちは、たとえ実がついても摘果して木の成長を優先しましょう。
これ、もったいなく感じるかもしれませんが、長い目で見れば正解なんです。若いうちに無理に実をつけさせると、木が弱ってしまうんですよ。
木が十分に育ってから、たくさんの美味しいみかんを収穫する。そう考えれば、最初の我慢も悪くないですよね。
一緒に植えると良い植物・避けるべき植物
みかんの木の周りに、他の植物を植えたいと思うこと、ありますよね。
実は、相性の良い植物と避けた方がいい植物があるんです。ここをうまく活用すると、みかんの木がもっと元気に育ちますよ。
コンパニオンプランツで害虫対策
コンパニオンプランツって聞いたことありますか?
これは、一緒に植えることでお互いに良い効果をもたらす植物の組み合わせのことなんです。
みかんの木と相性が良いのは、ハーブ類です。バジル、ミント、ローズマリーなんかが特におすすめ。これらのハーブは強い香りで害虫を遠ざけてくれるんですよ。しかも、料理にも使えて一石二鳥ですよね。
マリーゴールドも優秀です。根から分泌される物質が、土壌中の害虫を減らしてくれると言われています。鮮やかな花も綺麗で、見た目も楽しめますね。
そしてクローバー。これは根に共生する菌が空気中の窒素を固定してくれるので、土を豊かにしてくれるんです。雑草対策にもなって、まさに一石二鳥。
避けるべき植物の組み合わせ
一方、避けた方がいい組み合わせもあります。
まず、同じ柑橘類を近くに植えるのは要注意です。
病害虫が発生したとき、一気に広がってしまうリスクがあるんですね。レモンやゆずも育てたいなら、ある程度距離を離した方が安全です。
それから、根が深く広がる樹木も避けましょう。桜や楓なんかがそうです。根が競合して、お互いの成長を妨げてしまいます。
あと、日陰を作る高木も好ましくありません。みかんは日光が大好きですから、影になってしまうと実付きが悪くなってしまうんです。
植える間隔は、最低でも2メートルから3メートルは離してくださいね。根の競合を避けて、それぞれの植物が健康に育つために必要な距離なんです。
| 植物の種類 | 相性 | 効果・理由 |
|---|---|---|
| ハーブ類 (バジル・ミント・ローズマリー) | 害虫忌避効果 料理にも利用可能 | |
| マリーゴールド | 土壌害虫を減らす 観賞価値が高い | |
| クローバー | 窒素固定で土を豊かに 雑草対策にもなる | |
| 他の柑橘類 | 病害虫が集中しやすい | |
| 深根性樹木 (桜・楓など) | 根が競合する | |
| 高木 | 日陰を作ってしまう |
みかんの木の寿命と長く楽しむコツ
「せっかく植えるなら、長く楽しみたい」そう思いますよね。
みかんの木は、適切に管理すれば何十年も実をつけ続けてくれるありがたい存在なんです。
平均的な寿命はどれくらい?
一般的な家庭での栽培では、30年から50年が寿命の目安とされています。
でも、これはあくまで平均的な話。適切な管理をすれば、100年以上生きる木だってあるんですよ。実際、日本には樹齢200年を超える現役のみかんの木も存在するそうです。
つまり、あなたが植えたみかんの木を、お子さんやお孫さんの世代まで引き継ぐことも、夢じゃないということです。素敵な話ですよね。
寿命を延ばす管理方法
長生きさせるコツは、何と言っても病害虫の早期発見と対処です。
定期的に木の様子をチェックする習慣をつけましょう。葉の色がおかしい、虫がついている、枝が枯れているなど、異変に気づいたらすぐに対処してください。
それから、適切な剪定と施肥も重要です。前述した通り、年2回の剪定と年3回の施肥を続けることで、木は健康を保てます。
そして意外と見落とされがちなのが、台木の選択。購入時に耐病性の強い台木を選ぶと、長期的に管理が楽になりますよ。



日々のちょっとした気配りが、木の寿命を何十年も延ばすことにつながるんですね。
老木になった時の対応
木が老化してきたら、更新剪定という方法があります。
これは、古い枝を大胆に切り戻して、若い枝を伸ばす方法。木を若返らせることができるんです。思い切った剪定ですが、適切に行えば驚くほど元気を取り戻しますよ。
また、接ぎ木で更新する方法もあります。古い木の幹に新しい品種を接ぐことで、木自体は古いままでも、新しい枝と実を楽しめるんですね。
鉢植えという選択肢のメリット
ここまで地植えの話が中心でしたが、実は鉢植えという選択肢も十分にアリなんです。
むしろ、状況によっては地植えより鉢植えの方が向いているケースもありますよ。
鉢植え栽培の嬉しいメリット
まず何より、シロアリの心配が少ないというのが大きいですね。
鉢植えなら建物から離して置けますし、コンクリートやタイルの上に置けば、シロアリが寄ってくる可能性はほぼゼロです。この安心感は大きいですよ。
それから、移動できるというのも魅力的。
冬の寒さが厳しいとき、軒下や室内に移動させて寒さから守れます。台風が来るときも、安全な場所に避難させられますね。季節に応じて最適な場所に動かせるって、実はすごく便利なんです。
そして、根の管理がしやすい点も見逃せません。鉢という限られた空間で育てるので、自然とコンパクトに収まります。剪定の手間も地植えより少なくて済みますよ。
賃貸住宅にお住まいの方にも、鉢植えはぴったり。引っ越すときも一緒に連れていけますからね。
鉢植え栽培のポイント
鉢のサイズは、10号から12号以上がおすすめです。
小さすぎる鉢だと、根詰まりを起こして木が弱ってしまいます。大きめの鉢を選んで、ゆったり育ててあげましょう。
用土は、市販の果樹用培養土が便利です。自分で配合するなら、赤玉土6、腐葉土3、川砂1の割合が基本。水はけの良さが大切ですよ。
水やりは、地植えと違ってこまめに必要です。
土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと。夏場は朝夕2回必要なこともあります。これが鉢植えの唯一の手間かもしれませんね。
そして、2年から3年に一度は植え替えをしましょう。根が鉢いっぱいになったら、一回り大きな鉢に移し替えます。このとき、古い根を少し整理してあげると、木が元気を取り戻しますよ。
地植えと鉢植えの比較
どちらが良いか、というより、それぞれ向き不向きがあるんです。
地植えは、一度植えてしまえば水やりの手間が少なく、大きく育って収穫量も多いのが魅力。でも、場所を固定されるし、シロアリのリスクもゼロではありません。
鉢植えは、管理の自由度が高く、シロアリの心配が少ない。ただし、こまめな水やりと定期的な植え替えが必要です。
| 比較項目 | 地植え | 鉢植え |
|---|---|---|
| 水やり | 基本不要 | こまめに必要 |
| シロアリリスク | 対策が必要 | ほぼなし |
| 移動 | 不可 | 可能 |
| 収穫量 | 多い | やや少ない |
| 管理の手間 | 剪定が重要 | 水やり・植え替え必要 |
| 寒さ対策 | その場で対応 | 移動で対応可 |
| 賃貸住宅 | 不向き | 適している |
みかんの木を庭に植える前に知っておきたい情報


庭に植えてもいい柑橘類の種類
みかんの木以外にも、庭で育てられる柑橘類はたくさんあります。
それぞれに特徴があって、育てやすさも違うんです。自分の庭に合った柑橘を選ぶのも楽しいものですよ。
庭植えにおすすめの柑橘類
レモンは、柑橘類の中では比較的寒さに強いのが特徴です。
四季なり性の品種を選べば、年に何度も収穫できるんですよ。料理に使いやすいので、実用的な選択ですね。トゲが多い品種もあるので、購入時に確認しておくと良いでしょう。
ゆずは、柑橘類の中でもトップクラスの耐寒性を誇ります。
東北地方でも栽培できるほど丈夫なんです。香りが良くて、お風呂に浮かべたり料理に使ったりと、用途も広いですね。ただし、実がなるまで少し時間がかかります。
キンカンは、初心者に特におすすめです。
樹形がコンパクトで、鉢植えでも十分育てられます。実を皮ごと食べられるのも魅力的。しかも、比較的病害虫にも強いんですよ。
すだちやかぼすも、樹形が小さめで管理しやすい柑橘です。
四国地方が有名な産地ですが、本州の温暖な地域なら問題なく育ちます。料理の香りづけに重宝しますね。
そしてもちろん、温州みかんも庭植えに適しています。
育てやすく、実もたくさんつくので、家庭栽培では定番中の定番です。
品種選びのポイント
柑橘を選ぶとき、まず考えたいのが地域の気候です。
寒い地域なら耐寒性の高い品種、暖かい地域なら選択肢が広がります。自分の住んでいる地域の最低気温を確認して、それに耐えられる品種を選びましょう。
トゲの有無も重要なポイント。
小さなお子さんがいる家庭や、木の近くを頻繁に通る場所なら、トゲの少ない品種を選んだ方が安全です。最近は、トゲなし品種も増えてきていますよ。
それから、樹勢の強さ。狭い庭なら樹勢が穏やかで、コンパクトに育つ品種がおすすめです。
避けた方がいい柑橘類
グレープフルーツは、家庭の庭には不向きかもしれません。
というのも、樹高が5メートル以上になることもあり、管理が大変なんです。広大な土地があるなら別ですが、一般的な住宅の庭には大きすぎますね。
また、熱帯性の柑橘(ライムやシークワーサーの一部品種など)は、寒さに非常に弱いです。温暖な地域以外では、冬越しが難しいでしょう。
自分の地域に合った品種を選ぶことが、成功への第一歩です。地元の園芸店で相談すると、その土地に適した品種を教えてくれますよ。
庭に絶対植えてはいけない木とその理由
さて、みかんの木は適切に管理すれば問題ないという話をしてきました。
でも、世の中には本当に植えない方がいい木というのも存在します。参考までに、そういった木についても触れておきましょう。
成長が早すぎて手に負えない木
竹や笹類は、絶対に避けたい植物の筆頭です。
地下茎でものすごい勢いで広がって、隣家にまで侵入することも。一度植えてしまうと、完全に駆除するのは本当に大変なんです。風情があって素敵に見えますが、庭に植えるのは危険すぎますね。
桐も成長が非常に早い木です。
あっという間に大木になって、日陰を作ったり、落ち葉の処理が大変になったりします。
ポプラ類は、根が非常に強力で、建物の基礎や配管を傷めることがあります。欧米では街路樹としてよく見かけますが、家庭の庭には向きません。
シロアリを呼び寄せやすい木
枯れやすい針葉樹の一部は、シロアリの餌になりやすいとされています。
特に、木材が腐りやすい樹種は要注意。健康な木なら問題ないことも多いんですが、弱った部分からシロアリが侵入するリスクがあります。
トゲや毒がある木
タラノキは、新芽が美味しい山菜として知られていますが、幹に非常に鋭いトゲがあります。
子供やペットがいる家庭では、危険すぎて不向きですね。
イチイは、種に毒性があることで知られています。実は甘くて美味しそうに見えるんですが、種を飲み込むと危険なんです。
落ち葉が多すぎる木
クヌギやコナラは、秋になると大量の落ち葉を落とします。
掃除が本当に大変で、雨どいに詰まったり、隣家に迷惑をかけたりすることも。自然の風情はありますが、住宅地の庭には不向きかもしれません。
庭に植えると縁起がいい木
植えてはいけない木の話をしたので、今度は逆に縁起の良い木についても触れておきましょう。
日本には古くから、庭に植えると良いとされる木がいくつかあるんです。
伝統的に縁起が良いとされる木
南天は、「難を転じる」という語呂合わせから、魔除けの木として親しまれています。
赤い実が美しく、お正月の飾りにも使われますね。鬼門や裏鬼門に植えると良いとされています。
松は、長寿の象徴です。
「松竹梅」としておめでたい植物の代表格。ただし、手入れにはそれなりの技術が必要ですね。
梅は、開運の木とされています。
早春に美しい花を咲かせ、実も楽しめます。縁起が良いだけでなく、実用性も高い木です。
金木犀は、金運上昇の木として人気があります。
秋の香りは格別ですよね。比較的育てやすく、庭木として優秀です。
柿は、「代々続く繁栄」を象徴する木です。
「柿の木がある家は栄える」という言い伝えもあるほど。実もたくさんなって、食べられるのも嬉しいですね。
みかんも実は縁起が良い
実は、みかんの木も縁起の良い木なんですよ。
実がたくさんなることから、子孫繁栄や豊かさの象徴とされています。黄金色の実は金運を呼ぶとも言われていますね。
また、常緑樹であることから、「永続性」や「不変」を意味するとも。
つまり、風水的な配置さえ気をつければ、みかんの木は縁起の良い選択なんです。
風水的な配置の工夫
縁起の良い木でも、植える場所を間違えると効果が半減してしまいます。
前述した通り、みかんの木なら南側や西側がおすすめ。これらの方角は、風水的にも実りをもたらす木との相性が良いとされているんです。



「縁起」って気にしすぎると疲れちゃいますが、可能な範囲で考慮してみるのも楽しいものですよ。
よくある質問
最後に、みかんの木について特によく聞かれる質問をまとめておきますね。
Q1:庭にみかんの木を植えると風水的にどうなりますか?
鬼門(北東)や裏鬼門(南西)を避ければ、基本的に問題ありません。
むしろ、実がなる木は繁栄の象徴として縁起が良いとされています。トゲがあるので配置には注意が必要ですが、西側や南側に植えるのがおすすめです。これらの方角は、金運や人間関係運に関わる場所とされているんですよ。
風水を気にされる方は、専門家に相談するのも一つの方法です。でも、あまり神経質になりすぎず、基本的なルールを守れば十分だと思います。
Q2:マンションのベランダでみかんの木を育てられますか?
鉢植えなら十分可能です。
10号以上の大きめの鉢を使用して、日当たりの良い場所を確保してください。ベランダの場合、風が強すぎたり、逆に風通しが悪かったりすることがあるので、その点は注意が必要ですね。
冬の寒さ対策として、寒冷地では不織布で覆ったり、室内に取り込んだりする工夫も大切です。水やりは地植えより頻繁に必要ですが、それさえクリアできれば、ベランダでも立派なみかんが収穫できますよ。
Q3:みかんの木の害虫対策はどうすればいいですか?
みかんの木で最も注意したいのが、アゲハチョウの幼虫です。
葉を食べてしまうので、見つけたらすぐに取り除きましょう。緑色の大きな幼虫で、結構目立つので発見は難しくありません。
カイガラムシも厄介な害虫。枝に白いカビのようなものが付いていたら、カイガラムシの可能性が高いです。歯ブラシなどでこすり落とすか、専用の薬剤を使用してください。
ハダニは乾燥した環境で発生しやすいです。葉の裏に水をかけるだけでも予防効果があります。
無農薬で育てたい場合は、定期的な観察と早期発見が鍵。害虫を見つけたら、数が少ないうちに手で取り除くのが一番です。
Q4:実がつかない原因は何ですか?
実がつかない原因はいくつか考えられます。
まず、木がまだ若い場合。接ぎ木苗でも、植えてから2、3年は実がつかないことがあります。これは自然なことなので、焦らず待ちましょう。
日照不足も大きな原因。1日6時間以上の日光が必要です。周りに建物や木が増えて、以前より日当たりが悪くなっていないか確認してみてください。
水や肥料のやりすぎも実がつかない原因になります。特に窒素肥料が多すぎると、葉ばかり茂って実がつきません。
そして、剪定時期の間違い。花芽がつく時期に強剪定をすると、翌年の実がつきません。剪定は適切な時期に、適度に行うことが大切です。
これらのポイントを一つずつチェックしていけば、原因が見えてくるはずですよ。
まとめ
ここまで、みかんの木を庭に植えることについて、様々な角度から見てきました。
「植えてはいけない」と言われる理由には確かに根拠があるものの、適切な知識と対策があれば、十分に庭で育てられるということが理解していただけたのではないでしょうか。
- シロアリ対策は建物から3m以上離し定期点検を行うことで対処可能
- 風水では鬼門・裏鬼門を避け、南側や西側に植えるのがおすすめ
- 根の広がりは十分なスペース確保と適切な剪定で管理できる
- 植える場所は日当たりと風通しが良く、水はけの良い土壌を選ぶ
- 小さく育てるには矮性台木の選択、定期剪定、根域制限が効果的
- 年2回(2月と6月)の剪定で樹高2〜3mに維持できる
- 植え付けは3〜4月が最適で、植え穴は深さ・幅ともに50cm以上必要
- 接ぎ木苗なら2〜3年で実がなり始める
- コンパニオンプランツとしてハーブやマリーゴールドが相性良好
- 適切な管理で30〜50年、場合によっては100年以上の寿命
- 鉢植え栽培ならシロアリの心配が少なく移動も可能
- レモン、ゆず、キンカンなど他の柑橘類も庭植えに適している
- 竹や笹、成長が早すぎる木こそ本当に植えてはいけない木
- 実がたくさんなるみかんは子孫繁栄や豊かさの象徴で縁起が良い
- 地植えと鉢植えはそれぞれメリット・デメリットがありライフスタイルに合わせて選択
みかんの木は、正しく育てれば家族で長く楽しめる素晴らしい庭木です。
自分で育てたみかんを収穫する喜びは、何物にも代えがたいもの。この記事が、あなたのみかん栽培の第一歩を後押しできたら嬉しいです。