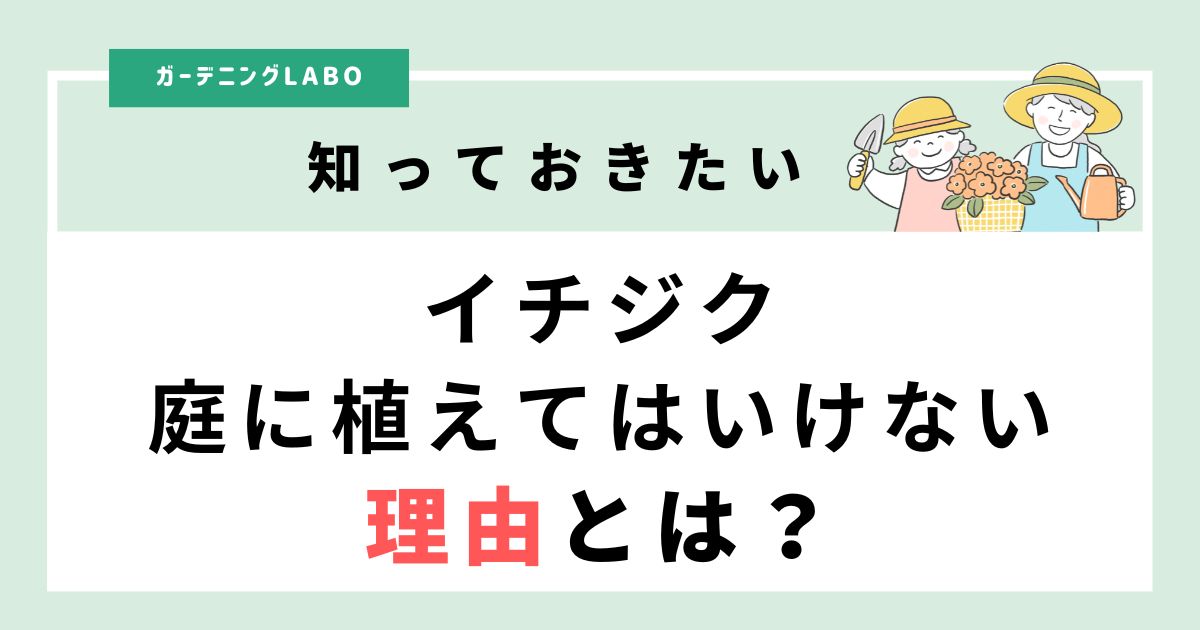イチジクを庭に植えようと考えたとき、インターネットで検索すると庭に植えてはいけないという情報を目にして、不安になった方も多いのではないでしょうか。確かにイチジクは無花果という漢字から縁起が悪いと言われたり、根が張りすぎて家屋の基礎に影響を与えるという話も耳にします。
しかし実際のところ、イチジクには子宝に恵まれるや多産といった花言葉もあり、適切な対策を講じれば庭での栽培も十分可能です。寒さに弱い特性やカミキリムシなどの害虫被害、鳥害による問題、樹液でかぶれる可能性など、確かに注意すべき点は存在します。
でも鉢植えでの栽培を選んだり、植え付け場所を工夫したり、適切な剪定を行えば、これらの問題は十分に対処できます。水やりや肥料の管理、挿し木での増やし方、おすすめの品種選びなど、正しい知識を持てば初心者でも美味しいイチジクを収穫できるのです。
- イチジクを庭に植えてはいけないと言われる8つの具体的な理由
- 根の張り方や害虫被害など実際に起こりうる問題点
- 鉢植え栽培や適切な植え付け場所など具体的な対策方法
- 実がならない原因の解決方法とおすすめ品種の選び方
イチジクを庭に植えてはいけない理由を徹底解説

| 植えてはいけない理由 | 問題の程度 | 対策の可否 |
|---|---|---|
| 縁起が悪い | 迷信レベル | 実際は子宝の花言葉あり |
| 根が家屋を傷める | 中程度のリスク | 距離を取れば対策可能 |
| 枝が日陰を作る | 庭のスペース次第 | 剪定で対応可能 |
| 害虫被害 | 高リスク | 定期的な防除で対策可能 |
| 鳥害 | 収穫期に発生 | ネット設置で対策可能 |
| 樹液でかぶれ | 肌が弱い人は注意 | 手袋着用で対策可能 |
| 寒さに弱い | 地域による | 鉢植えで対策可能 |
イチジクの特徴と基本情報
イチジクはアラビア半島や地中海沿岸を原産とする落葉低木で、日本では古くから親しまれてきた果樹です。亜熱帯性の植物であるため温暖な気候を好み、関東以西の暖地での栽培に適しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原産地 | アラビア半島・地中海沿岸 |
| 分類 | クワ科イチジク属の落葉低木 |
| 樹高 | 2~3m程度(剪定により調整可能) |
| 漢字表記 | 無花果(花を咲かせずに実をつけるように見えるため) |
| 花言葉 | 多産・子宝に恵まれる・実りある恋・裕福 |
| 収穫時期 | 夏果(6月下旬~7月)・秋果(8月~10月) |
| 結実年数 | 植え付けから2~3年 |
| 栽培難易度 | 初心者向け(比較的育てやすい) |
イチジクという名前の由来にはいくつかの説があり、果実がひとつずつ熟すことから一熟と呼ばれるようになったという説や、中国名の映日果から名前がついたという説などがあります。一般的な果樹は植え付けから収穫まで3~4年かかりますが、イチジクは早ければ1年目から収穫できることも大きな魅力です。
縁起が悪いと言われる理由と風水の真実
イチジクが庭に植えてはいけないと言われる最も有名な理由が、縁起が悪いという迷信です。しかし実際のところ、この迷信には科学的な根拠は全くありません。
無花果という漢字が生んだ誤解
イチジクは漢字で無花果と書きます。この漢字から花も実もならないと解釈され、出世しない、子孫が途絶える、家に病人が出るといった縁起の悪いイメージが生まれました。実際には実の中に花が咲いており、花も実もならないわけではありません。
病人が集まるという迷信の真相
昔イチジクの葉は漢方の生薬として用いられており、病人がイチジクの葉を求めて集まってきたため、イチジクの木がある家には病人が出ると言われるようになったという説があります。つまりイチジク自体が不幸を招くのではなく、薬として重宝されていたことが誤解を生んだのです。
実は縁起の良い花言葉と風水
風水では実のなる樹木には子宝運が宿っているという考えがあります。イチジクの花言葉は多産、子宝に恵まれる、裕福、実りのある恋といったポジティブなものばかりです。一つの木からたくさんの実がなることに由来しており、むしろお子さんを望むご家庭にとっては縁起の良い木だと言えるでしょう。
イチジクには食物繊維やビタミン、ミネラル、鉄分が豊富に含まれており、特に女性の体調を整えるのに最適な食材です。栄養面から見ても、自宅で栽培できるのは嬉しいメリットと言えます。
根が張りすぎて家屋の基礎に悪影響を及ぼす
イチジクを庭に植えてはいけない理由として、根が横に広く張る特性が挙げられます。これは迷信ではなく、実際に注意が必要な点です。
イチジクの根の張り方の特徴
イチジクの根は深さ50cm程度と浅根性ですが、横方向に大きく広がる性質があります。根は細く細かい根毛を中心に上に向かって伸びていき、表層部分で広範囲に広がります。この根の成長力は非常に旺盛で、発根力が強いことから挿し木でも容易に増やせるほどです。
家屋への影響と湿気の問題
根が横に広く張ることで、家屋の基礎や配管に影響を与える可能性があります。特に古い住宅の場合、基礎部分に根が入り込むリスクも考えられます。またイチジクは湿気を呼びやすい性質があるため、家屋の近くに植えると建物周辺の湿度が高くなる可能性もあります。
枝が横に張り日陰を作ってしまう
イチジクの木は枝が横に広がる樹形をしており、庭の貴重な日照を奪ってしまうという問題があります。
横に広がる樹形の特徴
イチジクは枝を横に大きく張りながら成長します。木の周囲は完全に日陰になり、せっかくの日当たりの良い庭でも、イチジクの木の下は暗くなってしまいます。枝を横に張られるとその分庭のスペースが狭くなり、他の植物を育てるのが難しくなります。
周辺の植物への影響
イチジクの木が作る日陰の影響で、周辺に植えている花壇や芝生が育ちにくくなることがあります。特に日光を好む植物にとっては大きな問題となり、庭全体のガーデニング計画に支障をきたす可能性があります。
カミキリムシなどの害虫被害に遭いやすい
イチジク栽培で最も深刻な問題の一つが、カミキリムシによる害虫被害です。この被害を放置すると、最悪の場合木が枯れてしまうこともあります。
イチジクを襲う2種類のカミキリムシ
| 害虫名 | 活動時期 | 被害の特徴 |
|---|---|---|
| キボシカミキリ | 5月~10月 | 活動期間が長く被害が大きい |
| クワカミキリ | 7月~8月 | 真夏に集中して被害を与える |
カミキリムシの被害内容
成虫は葉を食害して樹勢を弱らせ、花つきや実つきを悪くします。さらに深刻なのは、樹皮に傷をつけて産卵し、孵化した幼虫が枝や幹に侵入することです。幼虫は木の内部を食い荒らし、木は衰弱して実がつかなくなります。ひどい場合は枝が風で折れたり、木全体が枯れてしまうこともあります。
被害のサインと早期発見
実がつかないと思っていたら急に枝が枯れてきた場合は、カミキリムシの被害に遭っている可能性が高いです。木の周辺に木屑のようなものが落ちていたら、幹に穴が開いて幼虫が侵入しているサインです。定期的に木の状態を観察し、早期発見に努めることが重要です。
カミキリムシの被害は、ただ植えておくだけでは防ぐことができません。適切な防除対策を講じなければ、イチジクの木が枯れてしまうリスクが非常に高いのです。
鳥害による被害と庭の汚れ
イチジクの甘い実は人間だけでなく鳥にとっても魅力的な食料源です。鳥害による被害は収穫量の減少だけでなく、庭の美観を損ねる原因にもなります。
鳥がもたらす具体的な被害
熟したイチジクの実を目当てに、多くの鳥が木にやってきます。鳥は実を部分的につついて食べることが多く、食べかけの実が木に残ったり地面に落ちたりします。さらに鳥のフンが庭のあちこちに落ちるため、清掃の手間が大幅に増加します。見た目の美しさを損ねるだけでなく、衛生面でも問題になります。
収穫量への影響
鳥による食害が激しいと、せっかく育てたイチジクの実のほとんどを鳥に食べられてしまい、収穫できる量が大幅に減少してしまいます。特に熟した甘い実から狙われるため、一番美味しい時期の実を収穫できないという事態になりかねません。
樹液に触れるとかぶれる可能性がある
イチジクの果実や葉から出る白い乳液には、肌に刺激を与える成分が含まれています。特に肌が敏感な人は注意が必要です。
樹液によるかぶれの症状
イチジクの樹液に触れると、かぶれや炎症を起こすリスクがあります。特に果実を収穫する際や剪定作業をする際に、樹液が手に付きやすくなります。人によっては痒みや赤み、腫れなどのアレルギー反応が出ることもあります。
注意が必要な作業
特に注意が必要なのは、果実の収穫時と枝の剪定時です。果実を収穫する際は実の切り口から樹液が出ますし、枝を切ると大量の樹液が出てきます。また葉に触れただけでも樹液が付着することがあるため、葉の手入れをする際も注意が必要です。
寒冷地では栽培が難しい
イチジクは亜熱帯性の果樹であるため、寒さに弱いという特性があります。特に寒冷地での地植え栽培は困難です。
イチジクの耐寒性
イチジクは比較的温暖な気候を好む植物で、関東地方北部以北では庭植えでの栽培が難しいとされています。東北地方より北の地域では、冬季の寒さによって枯死するリスクが非常に高いです。温暖な地域であっても、異常な寒波や霜が降りることで生存が難しくなることがあります。
栽培に適した地域
庭植えの場合、適地は関東以西の暖地とされています。これらの地域でも冬の風が強い場所は避けるべきです。寒冷地で栽培したい場合は、鉢植えにして冬季は室内に移動させる必要があります。ただし耐寒性の強い品種を選べば、寒い地域でも地植えできることもあります。
| 地域 | 栽培方法 | 難易度 |
|---|---|---|
| 関東以西の暖地 | 地植え・鉢植えとも可能 | 易しい |
| 関東地方北部 | 鉢植え推奨 | やや難しい |
| 東北地方以北 | 鉢植えで室内越冬必須 | 難しい |
イチジクを庭に植えてはいけない問題への対策方法

| 適切な対策をすれば得られるメリット | 対策をしないと起こるデメリット |
|---|---|
| 樹上完熟の美味しい実が収穫できる 初心者でも育てやすく成功率が高い 2~3年で収穫が始まる早生性 栄養価が高く健康に良い果実 鉢植えなら場所を選ばず栽培可能 | 根が家屋の基礎を傷める カミキリムシで木が枯れる 鳥害で収穫量が激減する 樹液でかぶれる危険性 寒冷地では冬に枯死する |
植え付け場所の選び方と家屋からの適切な距離
イチジクを庭に植える場合、適切な植え付け場所を選ぶことが成功の鍵となります。特に家屋からの距離は重要なポイントです。
家屋からの推奨距離
根が横に広く張る特性を考慮すると、家屋から最低でも3~5m以上離して植え付けることが推奨されます。根が基礎や配管に影響を与えないよう、十分な距離を確保しましょう。また湿気を呼びやすい性質があるため、建物の風通しを阻害しない位置に植えることも大切です。
日当たりと風通しの確保
イチジクは日光を好む植物です。日当たりの良い南向きの場所を選び、一日に最低でも6時間以上は直射日光が当たる場所に植えましょう。強風を嫌う性質があるため、風の当たりにくい場所を選ぶことも重要です。
土壌の条件
イチジクは水はけの良い場所を好みます。過湿や水が停滞する場所は不適です。また中性から弱アルカリ性の土壌を好むため、植え付けの2週間前に苦土石灰を混ぜ込んでおくと良いでしょう。土層が深く水はけの良い土地条件が理想的です。
| 条件 | 推奨内容 |
|---|---|
| 家屋からの距離 | 3~5m以上 |
| 日照時間 | 1日6時間以上 |
| 方角 | 南向きが理想 |
| 風当たり | 強風を避ける |
| 土壌pH | 中性~弱アルカリ性 |
| 水はけ | 良好であること |
鉢植え栽培なら問題を回避できる
鉢植え栽培はイチジクの問題点のほとんどを解決できる最良の方法です。特にマンションのベランダなど限られたスペースでも栽培が可能です。
鉢植え栽培のメリット
鉢植えなら根の広がりを制限でき、家屋への影響を心配する必要がありません。移動が可能なため、日照条件の良い場所に置き換えたり、寒い時期には室内に移動させたりできます。樹高も剪定により1m程度に抑えられるため、管理が非常に楽になります。
適切な鉢のサイズ
3年生苗であれば7~8号鉢が理想的です。成長に応じて徐々に大きな鉢に植え替えていき、最終的には10号以上の大きな鉢で育てると良いでしょう。ただしあまり大きな鉢にすると移動が困難になるため、管理のしやすさとのバランスを考える必要があります。
鉢植えでの栽培ポイント
鉢植えの場合、市販の果樹用培養土を使用すると便利です。自分で配合する場合は赤玉土と腐葉土を7対3の割合で混ぜた土がおすすめです。鉢植えは地植えに比べて水切れしやすいため、こまめな水やりが必要になります。
| 栽培方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 地植え | 水やりの頻度が少ない・大きく育つ | 根の管理が難しい・移動不可 |
| 鉢植え | 移動可能・サイズ調整可・管理が楽 | 水やりの頻度が多い・定期的な植え替え必要 |
鉢植えなら大きくなりすぎないように伸びてくる枝をしっかり剪定すれば、1m程度の高さに収まって収穫できるため、ベランダ栽培に最適です。
日当たりと風通しを確保する剪定方法
適切な剪定を行うことで、枝が横に張りすぎる問題を解決し、風通しを良くして病害虫を防ぐことができます。
剪定の適期
剪定は葉が落ちた12月から翌年2月の休眠期に行います。この時期なら木へのダメージが最小限で済みます。葉がある活動期に根切りや剪定を行うと、蒸散や光合成といった生命活動の妨げになり、最悪の場合は枯れてしまうので注意が必要です。
品種別の剪定方法
イチジクには夏果専用種、秋果専用種、夏秋兼用種があり、それぞれ剪定方法が異なります。
| 品種タイプ | 実のなる場所 | 剪定方法 |
|---|---|---|
| 夏果専用種 | 前年枝の先端 | 切り戻しを最小限に・枝先を残す |
| 秋果専用種 | 新梢(当年枝) | 前年枝を2~3芽残して切り詰める |
| 夏秋兼用種 | 両方 | 夏果用と秋果用の枝を半々に分ける |
混み合った枝の整理
込み合った枝や徒長枝、主枝の裏側から出ている枝は間引き剪定を行います。風通しを良くすることで、湿気による果実の裂果を防ぎ、病害虫の発生も抑えられます。枝が交差している部分や内向きに伸びている枝も切り取りましょう。
カミキリムシ対策と害虫駆除の方法
カミキリムシの被害を防ぐには、予防と早期発見、そして迅速な駆除が重要です。
成虫の捕殺
キボシカミキリは5月から10月、クワカミキリは7月から8月に活動します。この時期に見つけ次第、成虫を捕殺することが基本です。早朝や夕方に木の周りを観察し、成虫を見つけたらすぐに捕まえて処分しましょう。
幼虫の駆除方法
木の周辺に木屑のようなものが落ちていたら、幹のどこかに穴が開いている証拠です。穴を見つけたら、その穴から園芸用殺虫剤を注入して幼虫を退治します。糞の出ている穴に薬剤を注入し、穴を粘土などで塞ぐと効果的です。
予防的な対策
定期的に樹木の状態を観察することが最も重要です。被害の初期段階で発見できれば、対処も容易になります。予防的に薬剤を散布する場合は、カミキリムシの活動期である5月から10月に実施します。
5月から10月は週に1回、木の周辺と幹を観察します。木屑や糞が落ちていないかチェックしましょう。
カミキリムシを見つけたらすぐに捕まえて処分します。早朝や夕方が見つけやすいタイミングです。
幹に穴を発見したら、殺虫剤を穴に注入し、穴を塞ぎます。
カミキリムシの被害は放置すると木が枯れてしまいます。ただ植えておくだけでは防げないため、必ず定期的な観察と防除を行いましょう。
鳥害対策とネットの設置
鳥害を防ぐには、物理的に鳥を近づけない対策が最も効果的です。
防鳥ネットの設置
最も確実な方法は、木全体を防鳥ネットで覆うことです。実が色づき始めた時期から収穫が終わるまで、ネットで保護します。ネットの目は細かいものを選び、鳥が入り込めないようしっかりと固定することが大切です。
その他の鳥害対策
反射テープやCDを木に吊り下げることで、光の反射により鳥を遠ざける方法もあります。ただしこれらの方法は時間が経つと鳥が慣れてしまうため、ネットと併用するのが効果的です。熟す前の早めの収穫も一つの手段ですが、完熟の美味しさは味わえなくなります。
| 対策方法 | 効果 | コスト |
|---|---|---|
| 防鳥ネット | 非常に高い | 中程度 |
| 反射テープ・CD | 一時的 | 低い |
| 早めの収穫 | 中程度 | なし |
樹液かぶれを防ぐ手袋と保護具の使用
樹液によるかぶれを防ぐには、適切な保護具を着用することが必須です。
必要な保護具
収穫作業や剪定作業を行う際は、必ずゴム手袋を着用しましょう。できれば長袖の作業着を着用し、肌の露出を最小限に抑えることが重要です。特に剪定時は大量の樹液が出るため、しっかりとした保護が必要です。
作業時の注意点
樹液が目に入らないよう注意が必要です。枝を切る際は樹液が飛び散ることがあるため、保護メガネの着用も検討しましょう。作業後は手や腕をよく洗い、樹液が付着していないか確認します。万が一かぶれた場合は、速やかに皮膚科を受診してください。
寒冷地での冬越し方法
寒冷地でイチジクを育てる場合、適切な冬越し対策が栽培成功の鍵となります。
鉢植えでの冬越し
鉢植えの場合は、寒風の当たらない室内に移動させます。ただし暖房のきいた場所よりも、無暖房の室内が適しています。玄関や廊下など、凍結しない程度の温度が保てる場所が理想的です。
地植えでの保温対策
地植えの場合で翌年も収穫を見込みたいなら、保温対策が必要です。株元にマルチングを施し、根を寒さから守ります。藁やバークチップ、腐葉土などを厚めに敷き詰めると効果的です。幹には保温材を巻き付けることも有効です。
耐寒性の強い品種選び
寒冷地で栽培する場合は、耐寒性の強い品種を選ぶことも重要です。品種によって耐寒性に差があるため、購入時に確認しましょう。ただしイチジクは基本的に寒さに弱い植物であるため、寒冷地では鉢植え栽培が無難です。
実がならない原因と水やり・肥料管理
イチジクの実がならない場合、水やりや肥料管理に問題があることが多いです。
実がならない主な原因
| 原因 | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 水不足 | 特に夏場の水切れ | 朝夕2回、夏は1日3回水やり |
| 日照不足 | 日陰では実付きが悪い | 1日6時間以上の日照を確保 |
| 湿気過多 | 果実が裂けて落ちる | 風通しを良くする剪定 |
| 肥料不足 | 実を膨らませる養分不足 | 定期的な追肥 |
| 樹が若い | 植え付け1~2年目 | 待つことも必要 |
| カミキリムシ | 幼虫が幹を食害 | 早期発見と駆除 |
正しい水やりの方法
イチジクは水分要求量が大きく、根は浅根性であるため、特に果実の発育期間中は毎日の水やりが必要です。夏場は土が常に程よく湿っているくらいが良いとされています。朝と夕方の2回、真夏の盛りには1日3回の水やりが必要になることもあります。
ただし水の与えすぎは根腐れの原因となるため注意が必要です。表土が乾いたらたっぷりと水を与え、鉢植えの場合は鉢底から水が流れ出るまで与えます。
肥料の種類と施用時期
イチジクは他の果樹に比べて肥料を多く必要とします。冬には寒肥として油かすや完熟堆肥を施します。また弱アルカリ性から中性の土壌を好むため、苦土石灰も一緒に施すと良いでしょう。
4月から10月の生育期には毎月、化成肥料を施します。イチジクはカルシウム、マグネシウム、カリウムを多く吸収する性質があるため、苦土石灰、有機石灰、草木灰といった肥料を用いると効果的です。
イチジクは昔、田んぼのあぜ道によく植えられていたそうです。これは水分を好む性質と根腐れに強い性質を示しています。
挿し木で増やす方法と植え替え時期
イチジクは挿し木で非常に簡単に増やせる果樹です。発根率は90パーセント以上と言われており、初心者でも成功しやすい方法です。
挿し木の適期と方法
挿し木の適期は2月から3月です。この時期に行うことで、生育期を迎える4月から6月にたくさんの枝や葉を伸ばすことができます。剪定で切り落とした前年に伸びた枝を挿し穂として利用します。
病気になっていない充実した枝を15~20cm程度にぶつ切りにします。幹側の切り口を斜めまたは鉛筆の先のようにカットし、切り口の表面積を増やします。
市販の挿し木用培養土または鹿沼土100パーセントを使用します。水はけの良い砂質の土を選びましょう。
土に挿し穂を挿し、明るいですが直射日光の当たらない場所で管理します。土に水分がありすぎると腐るため、適度な湿度を保ちます。2~3週間で発根し始めます。
植え替えの時期と方法
挿し木後の植え替え時期は、挿し木してから3~4か月後、時期でいうと6月から7月にかけてです。焦らずにイチジクの根がしっかり育ってから6号から8号鉢に植え替えます。鉢底から根が見えるくらいしっかり発根している状態になってから植え替えするのがポイントです。
通常の植え替え時期は3月です。ポットに入った苗木を購入した場合も、新しい鉢に植え替えてください。3月を過ぎて苗木を購入した場合は、真夏と収穫期を避けた時期であれば植え替えできます。
実がなるまでの期間
挿し木をしてから約2~3年で実がつきます。ただしこれは日当たりや水やり、肥料などを適切に与えた上での収穫なので、発根してからは正しい管理方法で栽培することが大切です。
おすすめの品種選び
イチジクには多数の品種があり、それぞれ特性が異なります。栽培目的や環境に合った品種を選ぶことが大切です。
主要品種の特徴
| 品種名 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| 桝井ドーフィン | 夏秋兼用 | 最も栽培が多い・大果で収量が多い・樹勢も強くない |
| 蓬莱柿(日本イチジク) | 秋果専用 | 古くからの品種・根強いファンがいる・甘みが強い |
| ホワイトゼノア | 夏秋兼用 | 白い果肉・上品な甘さ |
| ブラウンターキー | 夏秋兼用 | 濃厚な味わい・家庭栽培向き |
| セレスト | 秋果専用 | 小ぶりで甘い・耐寒性がやや強い |
| ビオレドーフィン | 夏果専用 | 大果・梅雨時期の栽培は難しい |
家庭栽培におすすめの品種
家庭での栽培は輸送の日数などを考えなくてよいので、完熟させた時に実が柔らかくても問題ありません。甘くて美味しい好みの品種を選んで楽しむことができます。
桝井ドーフィンは青果店に出ているもののほとんどがこの品種で、味はもう一歩ですが大果で収量が多く樹勢も強くないため育てやすいです。蓬莱柿は桝井ドーフィンよりも古くに中国から日本に伝わった品種で、日本イチジクと呼ばれることもあります。
夏果と秋果の違い
夏果は前年の秋に前年枝の先端部に付いた幼果が冬に発育を停止し、春先から再び発育して6月下旬から7月上旬に成熟します。秋果は春から伸びる新梢の中間部に着果し、8月中旬から10月中旬まで順に成熟します。
夏果は秋果より大果でおいしいのですが、日本では梅雨期に腐りやすいので、家庭用には秋果専用種か夏秋果兼用種が良いでしょう。
よくある質問
- イチジクは本当に縁起が悪いのですか
-
いいえ、迷信です。無花果という漢字から誤解が生まれましたが、実際には多産や子宝に恵まれるといった縁起の良い花言葉を持っています。風水でも実のなる樹木には子宝運が宿っているとされており、むしろポジティブな木と言えます。
- 植えてから何年で実がなりますか
-
一般的には植え付けてから2~3年で実がつき始めます。早ければ1年目から収穫できることもあります。ただし適切な環境や管理を行っていない場合、結実までにもっと時間がかかることもあります。日当たりが悪い場所で育てたり、むやみに剪定したりすると結実開始が遅れる場合があります。
- 鉢植えでも実はなりますか
-
はい、鉢植えでも十分に収穫可能です。7~10号鉢で栽培すれば、樹高を1m程度に抑えながら実を収穫できます。マンションのベランダなど限られたスペースでも栽培でき、むしろ管理がしやすいというメリットがあります。
- イチジクの寿命はどのくらいですか
-
農家が商業的に果実を収穫できる経済樹齢は10~15年程度とされています。それ以降は木自体が生きていても果実の収穫量が減少します。日本の気候では比較的短命な場合が多いですが、他国では100年以上の寿命を持つイチジクの木も存在します。
- 1本で実はなりますか
-
はい、多くの品種は単為結果性で1本でも結実します。受粉をしなくても果実が大きく実る性質を持つ品種が多いため、1本だけ植えても問題ありません。収穫前提で売り出されているイチジクであれば、だいたいは1株で結実する性質を持っています。
- 実が落ちてしまうのはなぜですか
-
主な原因は水不足と湿気過多です。夏場の水切れで実がしおれて落ちることがあります。逆に湿気が多いと果実が裂けて落ちることもあります。混み合った枝を剪定して風通しを良くし、夏場はこまめに水やりをすることで対策できます。
- どの品種が初心者におすすめですか
-
桝井ドーフィンが初心者におすすめです。樹勢も強くなく木の収まりが良く、大果で収量が多いため育てやすい品種です。夏秋兼用種なので長期間収穫を楽しめます。より美味しさを求めるなら蓬莱柿もおすすめですが、こちらは秋果専用種です。
イチジク植えてはいけないポイントまとめ
- イチジクを庭に植えてはいけないという理由の多くは迷信や誤解であり、科学的根拠のないものが大半
- 縁起が悪いという話は無花果という漢字から生まれた誤解で、実際の花言葉は多産や子宝に恵まれるなど縁起が良い
- 根が横に広く張る特性があるため、家屋から3~5m以上離して植えれば基礎への影響は回避できる
- 鉢植え栽培を選択すれば根の問題、寒さの問題、スペースの問題のほとんどを解決できる
- カミキリムシによる害虫被害は深刻だが、定期的な観察と早期駆除で対策可能
- 鳥害は防鳥ネットの設置により確実に防ぐことができる
- 樹液によるかぶれはゴム手袋と長袖の作業着で簡単に予防できる
- 寒冷地でも鉢植えにして冬季は室内に移動させれば栽培可能
- 実がならない原因は水不足、日照不足、肥料不足などが多く、適切な管理で解決できる
- イチジクは初心者でも育てやすく、植え付けから2~3年で収穫できる早生性が魅力
- 挿し木での増殖が容易で発根率90パーセント以上と非常に高い
- 桝井ドーフィンや蓬莱柿など品種によって特性が異なるため、環境に合った品種選びが重要
- 日当たりの良い南向きの場所で水はけの良い土壌を選べば栽培は成功しやすい
- 12月から2月の休眠期に適切な剪定を行えば枝が横に張りすぎる問題も解決できる
- イチジクは食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で女性の体調を整えるのに最適な果実