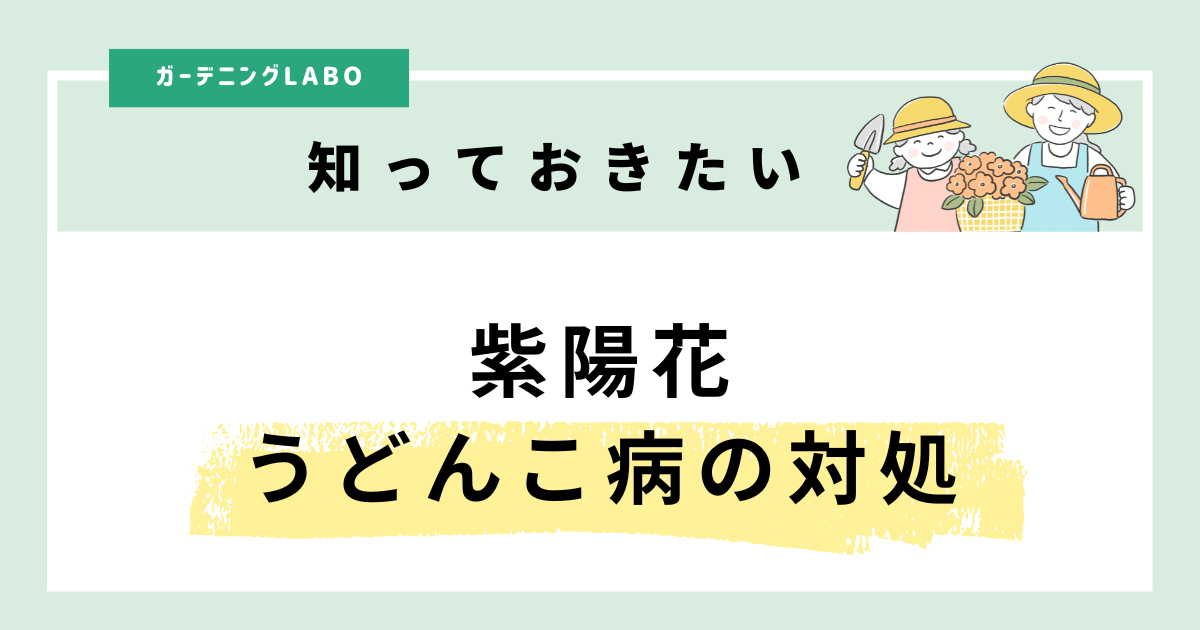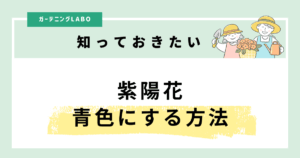大切に育てている紫陽花の葉に白い粉のようなものが付いていたら、それはうどん粉病かもしれません。うどん粉病はカビが原因で発生する病気で、放置すると葉が黒く変色し、最終的には株全体が枯れてしまう可能性があります。
しかし、早期に発見して適切な対処を行えば、紫陽花を元気に回復させることができます。乾燥した環境で発生しやすいこの病気は、梅雨明けや秋口に特に注意が必要です。
この記事では、紫陽花がうどん粉病になったときの具体的な対処法から、二度と発生させないための予防法まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
- 紫陽花のうどん粉病の症状と見分け方を写真付きで理解できる
- 重曹や食酢を使った自然派の対処法から薬剤による確実な治療法まで学べる
- うどん粉病が発生する根本原因と環境改善のポイントがわかる
- 日々の管理で実践できる具体的な予防策を習得できる
紫陽花のうどん粉病になったら実践すべき対処法

| 進行段階 | 主な症状 | 推奨対処法 |
|---|---|---|
| 初期段階 | 白い斑点が数枚の葉に出現 | 重曹スプレー+病葉除去 |
| 中期段階 | 葉の広範囲が白く覆われる | 薬剤散布+こまめな観察 |
| 進行段階 | 葉が黒変し枯れ始める | 強力な薬剤+株の隔離 |
うどん粉病の特徴と基本情報を知る
うどん粉病は、カビの一種である糸状菌が原因で発生する植物の病気です。紫陽花は特にこの病気にかかりやすい植物の一つとされています。
病気の初期段階では、葉の表面に白い粉のようなものが薄く付着します。これは文字通り、うどん粉をまぶしたように見えることから「うどん粉病」と呼ばれるようになりました。症状が進行すると、白いカビが厚くなり、最終的には葉が紫褐色から黒色に変色していきます。
| うどん粉病の基本情報 | |
|---|---|
| 原因 | カビ(糸状菌)の胞子による感染 |
| 発生時期 | 春から秋(4月〜11月)、特に梅雨明けと秋口 |
| 発生条件 | 気温20〜32度、乾燥した環境 |
| 感染経路 | 風によって運ばれるカビの胞子 |
| 主な症状 | 葉の白色化→黒変→枯死 |
うどん粉病のカビは、湿度が低く乾燥した環境を好みます。そのため、多くの人が紫陽花は湿気を好むと誤解していることから、水やりを控えめにしてしまい、かえってうどん粉病を発生させてしまうケースが多いのです。
この病気を放置すると、光合成が阻害され、植物は栄養不足に陥ります。その結果、葉が枯れ落ち、最悪の場合は株全体が弱って枯死してしまいます。
うどん粉病かどうかを見分ける方法
紫陽花の葉に異変を見つけたとき、それがうどん粉病なのか、それとも他の病気なのかを正確に判断することが重要です。
初期症状の見分け方
うどん粉病の最も初期の段階では、葉の表面に小さな白い斑点が現れます。指で触ると、粉のようなものがわずかに付着します。この時点で発見できれば、対処は比較的容易です。
発症しやすいのは、若い葉や新芽の部分です。古い葉よりも柔らかく、カビの胞子が付着しやすいためです。葉の表側だけでなく、裏側にも症状が現れることがあるため、両面を確認しましょう。
進行した症状の特徴
症状が進むと、白い斑点が広がり、葉全体がうどん粉をまぶしたような状態になります。さらに放置すると、紫陽花特有の症状として、白い部分が紫褐色や黒色に変色していきます。これは、カビが栄養を奪い、葉の組織が壊死している証拠です。
他の病気との違い
紫陽花がかかりやすい病気には、うどん粉病の他に炭疽病があります。炭疽病は褐色の丸い斑点が特徴で、中心部が灰色になります。うどん粉病は白い粉状の症状から始まるため、見分けることができます。
| 病気の種類 | 主な症状 | 見分けるポイント |
|---|---|---|
| うどん粉病 | 白い粉状→黒変 | 葉の表面全体が白くなる |
| 炭疽病 | 褐色の丸い斑点 | 中心部が灰色、穴が開く |
| 灰色かび病 | 灰色のカビ | 高湿度時に発生、花にも症状 |
発症したらすぐにやるべき応急処置
うどん粉病を発見したら、すぐに応急処置を行うことが重要です。早期対応により、被害の拡大を最小限に抑えることができます。
病気の葉を取り除く
まず最初に行うべきは、病気にかかった葉をすべて取り除くことです。うどん粉病のカビは胞子を飛ばして他の葉に感染を広げるため、感染源を物理的に除去することが最も効果的な対策となります。
病気の葉を取り除く際は、園芸用のハサミを使用し、健康な葉を傷つけないよう注意しましょう。
取り除いた葉の正しい処分方法
取り除いた葉は、絶対に地面に放置したり、コンポストに入れたりしてはいけません。カビの胞子が残っているため、再び感染源となる可能性があります。ビニール袋などに密閉して、可燃ゴミとして処分しましょう。
感染株の隔離と道具の消毒
複数の紫陽花を育てている場合は、感染した株を他の株から離して管理します。また、使用したハサミや手袋は、必ず消毒用エタノールや漂白剤で消毒してから、他の植物の手入れに使用してください。
白い斑点のある葉を見つけたら、すぐにハサミで切り取ります
取り除いた葉はビニール袋に密閉して可燃ゴミへ
使用したハサミや手袋を消毒用エタノールで拭きます
感染株を他の植物から離して管理します
重曹を使った自然派の対処法
化学薬品を使わずにうどん粉病を治療したい方には、重曹を使った方法がおすすめです。重曹は食品添加物としても使われるため、人体や環境に優しく、安心して使用できます。
重曹が効く理由
重曹(炭酸水素ナトリウム)はアルカリ性の物質です。うどん粉病の原因となるカビは酸性の環境を好むため、アルカリ性の重曹が葉の表面環境を変化させることで、カビの成長を抑制できます。また、重曹には胞子の形成や発芽を抑える作用もあります。
重曹スプレーの作り方
重曹スプレーの作り方は非常に簡単です。ただし、濃度が重要なポイントとなります。
| 希釈倍率 | 重曹の量 | 水の量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 500倍希釈 | 重曹1g(小さじ約1/4) | 500ml | 初期症状・予防 |
| 1000倍希釈 | 重曹1g(小さじ約1/4) | 1000ml | 初期症状・予防 |
重曹を水によく溶かし、スプレーボトルに入れます。濃すぎる液は逆に植物を傷めてしまうため、必ず規定の濃度を守りましょう。アース製薬の園芸情報によると、適切な希釈倍率で使用することが重要とされています。
スプレーの散布方法と頻度
重曹スプレーは、病気の葉だけでなく、健康な葉の表面と裏面にも均一に散布します。特に葉の裏側は胞子が付着しやすいため、念入りに行いましょう。
散布は早朝か夕方の涼しい時間帯に行います。直射日光が当たる時間帯に散布すると、葉焼けを起こす可能性があります。
効果を持続させるためには、1週間に1〜2回程度、定期的に散布することが推奨されます。雨が降った後は効果が薄れるため、再度散布しましょう。
重曹使用時の注意点
重曹は安全性が高い物質ですが、過度に使用すると土壌のpHバランスを崩す可能性があります。また、濃度が濃すぎると葉にダメージを与えることがあるため、まずは少量で試してから全体に散布しましょう。
食酢・木酢液を使った対処法
重曹の他にも、食酢や木酢液を使った自然派の対処法があります。これらも家庭で手軽に実践できる方法です。
食酢を使った方法
食酢(酢酸)には殺菌作用があり、うどん粉病の初期症状に効果を発揮します。食酢を水で100倍程度に希釈してスプレーボトルに入れ、病気の部分に散布します。
ただし、食酢は揮発性が高いため、効果の持続時間は重曹よりも短くなります。こまめに散布する必要があります。
木酢液の効果
木酢液は木材を炭化する際に出る液体で、殺菌・防虫効果があります。300倍程度に希釈して使用します。独特の煙のような香りがありますが、植物を元気にする成分も含まれているため、病気の治療と同時に株の活力向上も期待できます。
重曹との組み合わせ
重曹スプレーと木酢液を交互に使用することで、より効果的な対策となります。ただし、同時に混ぜて使用するのではなく、数日間隔を空けて使い分けることがポイントです。
| 自然農薬の種類 | 希釈倍率 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 重曹 | 500〜1000倍 | 安全性が高い、入手しやすい | 濃度管理が必要 |
| 食酢 | 100倍 | 殺菌力が強い | 効果の持続時間が短い |
| 木酢液 | 300倍 | 殺菌+活力向上 | 独特の香りがある |
市販の薬剤を使った確実な治療法
症状が進行している場合や、重曹などの自然派対策で効果が見られない場合は、市販の専用薬剤を使用することをおすすめします。
薬剤が必要なケース
葉の広範囲が白くなっている、または黒く変色し始めている場合は、自然派の方法では対処しきれないことが多いです。このような場合は、早めに専用薬剤を使用することで、株全体の枯死を防ぐことができます。
効果的な薬剤の種類
うどん粉病に効果的な薬剤には、以下のようなものがあります。
| 薬剤名 | 有効成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| STサプロール乳剤 | トリホリン | 浸透移行性、予防と治療 |
| カリグリーン | 炭酸水素カリウム | 有機栽培可、収穫前日まで使用可 |
| ベニカXネクストスプレー | マンデストロビン他 | 殺虫・殺菌効果、即効性 |
| トップジンM水和剤 | チオファネートメチル | 広範囲の病気に対応 |
これらの薬剤は、園芸店やホームセンターで購入できます。使用前には必ず説明書をよく読み、適切な希釈倍率と散布方法を守りましょう。
薬剤の正しい散布方法
薬剤を散布する際は、必ずマスクと手袋を着用し、風のない穏やかな日に行います。葉の表面と裏面の両方に、霧状に均一にかかるよう散布します。
薬剤散布後は、少なくとも24時間は雨に当てないようにします。雨で流れてしまうと効果が半減します。
散布頻度は薬剤によって異なりますが、一般的には7〜10日間隔で2〜3回繰り返すことが推奨されています。
薬剤使用時の安全対策
農薬を使用する際は、以下の安全対策を必ず守りましょう。
- 散布時は長袖・長ズボン、マスク、手袋、保護メガネを着用する
- 風上から散布し、自分に薬剤がかからないようにする
- 散布後は手や顔をよく洗う
- ペットや子供が近づかないよう注意する
- 薬剤は直射日光を避け、涼しい場所で保管する
症状の進行度別の対処手順
うどん粉病の対処法は、症状の進行度によって使い分けることが効果的です。それぞれの段階に応じた最適な方法を実践しましょう。
初期段階の対処法
葉に白い小さな斑点が数個程度見られる初期段階では、重曹スプレーと病葉の除去だけで十分効果が期待できます。
この段階で発見できれば、1〜2週間程度で症状の改善が見られるはずです。毎日観察を続け、新たな斑点が現れていないか確認しましょう。
中期段階の対処法
葉の広範囲に白い粉が広がり、複数の葉に症状が見られる中期段階では、専用薬剤の使用を検討すべきタイミングです。
重曹スプレーと薬剤を併用することも効果的です。まず病葉を除去し、翌日に薬剤を散布するという手順で進めましょう。
進行段階の対処法
葉が黒く変色し、枯れ始めている進行段階では、即座に強力な薬剤を使用する必要があります。同時に、感染した株を他の植物から隔離し、感染拡大を防ぎます。
この段階では、完全に回復するまでに1ヶ月以上かかることもあります。根気強く治療を続け、新しく出てくる葉が健康であるか確認しながら管理しましょう。
| 早期発見のメリット | 放置した場合のリスク |
|---|---|
| 重曹だけで対処可能 1〜2週間で回復 薬剤コストがかからない 他の株への感染を防げる | 株全体が枯死する可能性 他の株にも感染拡大 回復に長期間必要 強力な薬剤が必須になる |
紫陽花のうどん粉病になったら始める予防法

| 予防のポイント | 具体的な方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 環境管理 | 風通しと適度な日当たりの確保 | カビの発生を抑制 |
| 水分管理 | 適切な水やりで乾燥を防ぐ | 葉の抵抗力向上 |
| 栄養管理 | 窒素過多を避けたバランスの良い施肥 | 健康な株づくり |
| 定期管理 | 予防散布と剪定 | 病原菌の除去 |
うどん粉病が発生する根本原因を理解する
うどん粉病を効果的に予防するためには、まず病気が発生する根本的な原因を理解することが重要です。
カビが好む環境条件
うどん粉病の原因となるカビは、気温が20〜32度で、湿度が低く乾燥した環境を好みます。これは多くのカビ類が高湿度を好むのとは対照的な特徴です。
そのため、梅雨明けの乾燥した時期や、秋の爽やかな季節に発生しやすくなります。また、室内で管理している鉢植えの紫陽花は、年間を通じて発生リスクがあります。
紫陽花が特にかかりやすい理由
紫陽花は葉が大きく、葉の表面積が広いため、カビの胞子が付着しやすい植物です。また、紫陽花は水を好む植物というイメージから、水やりを控えめにしてしまう誤った管理により、かえって乾燥状態を招いてうどん粉病を発生させやすくなっています。
窒素肥料の与えすぎが招く問題
窒素肥料を過剰に与えると、葉が柔らかく育ちすぎて病気に対する抵抗力が低下します。また、窒素過多の状態では、葉の表面にアミノ酸が多く分泌され、これがカビの栄養源となってしまいます。
| 発生要因 | 具体的な状況 | 対策 |
|---|---|---|
| 気候条件 | 気温20〜32度、乾燥 | 適度な水やり、葉水 |
| 風通し不良 | 枝葉が密集、壁際に配置 | 剪定、配置の見直し |
| 窒素過多 | 肥料の与えすぎ | バランスの良い施肥 |
| 株の密植 | 株間が狭すぎる | 適切な株間の確保 |
日当たりと風通しを改善する方法
うどん粉病の予防において、最も基本的で重要なのが栽培環境の改善です。特に風通しと日当たりの管理は、病気の発生を大きく左右します。
適度な日当たりの重要性
紫陽花は半日陰を好む植物ですが、全く日が当たらない場所では株が軟弱に育ち、病気にかかりやすくなります。理想的なのは、午前中は日が当たり、午後は明るい日陰になるような場所です。
日当たりが良すぎても葉焼けを起こす可能性があるため、特に真夏は適度な遮光が必要です。
風通しを良くする具体的方法
風通しの改善は、うどん粉病予防の最重要ポイントです。以下の方法を実践しましょう。
地植えの場合は、紫陽花の周囲に他の植物を密植しすぎないよう注意します。鉢植えの場合は、壁際や建物の角など、風が滞りやすい場所を避けて配置しましょう。
また、株元の落ち葉や枯れ葉をこまめに除去することも、風通しの改善につながります。落ち葉は湿気をこもらせるだけでなく、病原菌の越冬場所にもなるため、定期的に清掃しましょう。
季節ごとの環境管理
梅雨時期は湿度が高いものの、梅雨明けの急激な乾燥がうどん粉病を引き起こしやすくなります。梅雨明け直後は特に注意して水やりを行い、急激な乾燥を防ぎましょう。
秋口も気温が下がり、空気が乾燥してくるため発生リスクが高まります。この時期も定期的な葉水を行うと効果的です。
水やりで乾燥を防ぐコツ
うどん粉病は乾燥した環境で発生しやすいため、適切な水やり管理が予防の鍵となります。
紫陽花の水やりの基本
紫陽花の名前の由来は「あずさい(集真藍)」とも言われ、水を好む植物です。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることが基本です。
特に鉢植えの場合は、鉢底から水が流れ出るまでしっかりと水やりを行います。地植えの場合も、夏場は朝夕2回の水やりが必要になることがあります。
葉水の効果
根元への水やりだけでなく、葉全体に霧吹きで水をかける「葉水」も非常に効果的です。葉水には以下のような効果があります。
- 葉の表面の湿度を保ち、カビの発生を抑える
- 葉の気孔を清潔に保ち、光合成を促進する
- 葉の温度を下げ、暑さによるストレスを軽減する
- ハダニなどの害虫予防にもなる
葉水は早朝か夕方の涼しい時間帯に行います。日中に行うと、水滴がレンズの役割を果たして葉焼けを起こす可能性があります。
土の水はけと保水のバランス
水やりの頻度も重要ですが、土の質も同様に大切です。水はけが悪すぎると根腐れを起こし、逆に水はけが良すぎるとすぐに乾燥してしまいます。
理想的なのは、赤玉土と腐葉土を混ぜた、適度な保水性と排水性を持つ土です。市販の「紫陽花の土」を使用するのも良い選択です。
| 季節 | 水やり頻度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 春 | 土が乾いたら(1日1回程度) | 新芽の成長期、乾燥に注意 |
| 夏 | 朝夕2回 | 葉水も併用、午後は避ける |
| 秋 | 土が乾いたら(1〜2日に1回) | 気温低下で水の減りが遅くなる |
| 冬 | 土が乾いたら(2〜3日に1回) | 休眠期、水やり控えめ |
肥料管理で病気に強い株を育てる
適切な肥料管理は、病気に負けない健康な紫陽花を育てるために欠かせません。
窒素過多が招くリスク
窒素(N)は葉を大きく育てる栄養素ですが、与えすぎると葉が軟弱に育ち病気にかかりやすくなります。また、窒素過多の状態では、葉の表面にアミノ酸が過剰に分泌され、これがうどん粉病のカビの栄養源となってしまいます。
病気に強い株を作る肥料バランス
健康な株を育てるには、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)のバランスが重要です。紫陽花には、NPKの比率が5:10:5程度のバランスの良い肥料が適しています。
リン酸は根の成長と花付きを良くし、カリウムは耐病性を高める効果があります。特にカリウムは、植物の細胞壁を強化し、病原菌の侵入を防ぐ役割を果たします。
適切な施肥時期と量
紫陽花への施肥は、年に2〜3回程度が適切です。
- 2月〜3月:寒肥として緩効性肥料を株元に施す
- 5月〜6月:花後のお礼肥として液体肥料を与える
- 9月:秋の追肥として緩効性肥料を施す
定期的な予防散布で発生を抑える
うどん粉病が発生する前に、予防的に薬剤や重曹スプレーを散布することで、発生リスクを大幅に減らすことができます。
予防散布が効果的な理由
病気が発生してから治療するよりも、発生前に予防する方が遥かに少ない労力で管理できます。予防散布は、カビの胞子が葉に付着しても、発芽や繁殖を抑制する効果があります。
予防散布の時期とタイミング
うどん粉病が発生しやすい春(4月〜5月)と秋(9月〜10月)に、定期的な予防散布を行います。特に梅雨明けの時期は最も発生リスクが高いため、重点的に管理しましょう。
散布頻度は、重曹スプレーの場合は1週間に1回、市販の予防薬剤の場合は2週間に1回程度が目安です。
予防に使える薬剤と自然農薬
予防目的であれば、重曹スプレーや木酢液などの自然農薬で十分効果があります。化学薬品を使用したくない方には、これらの方法がおすすめです。
市販の予防薬剤では、「カリグリーン」や「ベニカXネクストスプレー」などが予防効果が高く、安全性も優れています。
雨上がりは葉が濡れているため、薬剤の吸収が良くなります。雨が上がって数時間後に散布すると効果的です。
剪定と清掃で病原菌を残さない
日々の管理作業である剪定と清掃も、うどん粉病の予防に大きく貢献します。
花後の剪定の重要性
紫陽花は花が終わった7月頃に剪定を行います。この剪定には、翌年の花付きを良くするだけでなく、風通しを改善して病気を予防する効果もあります。
花から2〜3節下の位置で切り戻し、込み合っている枝や古い枝も一緒に間引きましょう。株の中心部まで光と風が届くようになることで、カビの繁殖を抑えられます。
病気の枝葉の処分
剪定で切り取った枝葉、特にうどん粉病の症状が出ていた部分は、必ずビニール袋に密閉して可燃ゴミとして処分します。地面に放置したり、コンポストに入れたりすると、カビの胞子が残って翌年の感染源となります。
剪定バサミの消毒
剪定作業で使用したハサミには、病原菌が付着している可能性があります。作業後は必ず消毒用エタノールや漂白剤で消毒し、他の植物に病気を広げないようにしましょう。
株元の清潔を保つ
落ち葉や枯れ葉は、カビや病原菌の越冬場所となります。特に秋から冬にかけて、こまめに株元の清掃を行い、落ち葉を除去しましょう。
また、雑草も風通しを悪くする原因となるため、定期的に除草作業を行うことも大切です。
株間を広く取って感染を防ぐ植え方
紫陽花を植え付ける際の配置も、病気の予防に大きく影響します。
適切な株間の距離
紫陽花は成長すると枝を横に広げて大きくなります。植え付け時は小さくても、成長後の大きさを考慮して株間を確保することが重要です。
一般的な紫陽花の場合、株間は最低でも1メートル以上、できれば1.5〜2メートル取ることをおすすめします。コンパクトな品種でも、80センチメートル程度は確保しましょう。
地植えでの配置計画
地植えする場合は、建物の壁際や塀の近くは避けましょう。これらの場所は風通しが悪く、うどん粉病が発生しやすくなります。
また、他の植物との組み合わせにも注意が必要です。紫陽花の周囲に背の高い植物を密植すると、日当たりや風通しが悪くなります。周辺には、グランドカバーや低木など、競合しない植物を配置しましょう。
鉢植えの場合の管理
鉢植えの紫陽花は、複数の鉢を並べる際に、鉢同士の間隔を十分に取ります。葉が重なり合わないよう、少なくとも30センチメートルは離して配置しましょう。
また、鉢の置き場所は定期的に変更し、特定の株だけが風通しの悪い場所に長期間置かれることがないよう配慮します。
| 植え方のタイプ | 推奨株間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般品種(地植え) | 1.5〜2m | 成長後の大きさを考慮 |
| コンパクト品種(地植え) | 0.8〜1m | 風通しを確保 |
| 鉢植え | 0.3m以上 | 葉が重ならないように |
| 他の植物との距離 | 1m以上 | 競合を避ける |
よくある質問
- うどん粉病は他の紫陽花にうつりますか?
-
はい、うどん粉病は感染します。カビの胞子が風によって飛散し、近くの健康な株にも付着して発病します。そのため、発病した株を見つけたら、すぐに病葉を除去し、他の株から離して管理することが重要です。
- 梅雨時期でもうどん粉病は発生しますか?
-
梅雨時期よりも、梅雨明けの乾燥した時期に発生しやすくなります。うどん粉病のカビは乾燥した環境を好むため、空梅雨で雨が少ない年や、梅雨明け直後は特に注意が必要です。
- 重曹とクエン酸は一緒に使えますか?
-
いいえ、重曹とクエン酸を同時に使用すると中和反応が起きて、両方の効果がなくなってしまいます。重曹はアルカリ性、クエン酸は酸性なので、どちらか一方を使用するか、日を分けて使い分けてください。
- 病気の葉を全部取ってしまっても大丈夫ですか?
-
病気にかかった葉だけを取り除き、健康な葉はできるだけ残すようにします。葉をすべて取ってしまうと、光合成ができなくなり、株が弱ってしまいます。症状が出ている部分のみを選んで除去しましょう。
- 一度発生したら毎年出ますか?
-
適切に対処せずに放置すると、カビの胞子が株元や落ち葉の中で越冬し、翌年も発生する可能性が高くなります。しかし、病葉の除去、株元の清掃、予防散布などを徹底すれば、翌年の発生を大幅に抑えることができます。
- 室内の鉢植えでも発生しますか?
-
はい、室内でも発生する可能性があります。特にエアコンで空気が乾燥している室内では、年間を通じて発生リスクがあります。室内で管理する場合は、こまめな葉水と、定期的な換気を心がけましょう。
- 薬剤と重曹はどちらが効果的ですか?
-
初期症状であれば重曹スプレーでも十分効果がありますが、症状が進行している場合は専用の薬剤の方が確実です。予防目的なら重曹、治療目的なら症状に応じて薬剤を選ぶことをおすすめします。
紫陽花のうどん粉病対策で美しい花を長く楽しむために
- うどん粉病は葉が白い粉で覆われ、進行すると黒変して枯れる病気
- 原因はカビで、気温20〜32度の乾燥した環境で発生しやすい
- 発見したらすぐに病葉を除去し、ビニール袋に密閉して処分する
- 初期段階では重曹1000倍希釈液のスプレーが効果的
- 食酢100倍希釈や木酢液300倍希釈も自然派対策として有効
- 症状が進行している場合は専用の殺菌剤を使用する
- 予防には風通しと適度な日当たりの確保が最重要
- 乾燥を防ぐため、土の表面が乾いたらたっぷり水やりする
- 葉水を行うことで葉の表面湿度を保ち発生を抑制できる
- 窒素肥料の与えすぎは避け、バランスの良い施肥を心がける
- 春と秋の発生しやすい時期は定期的な予防散布を実施する
- 花後の剪定で込み合った枝を整理し風通しを改善する
- 株元の落ち葉をこまめに除去して病原菌の越冬を防ぐ
- 株間は最低1メートル以上確保して植え付ける
- 日々の観察を怠らず、異変に気づいたらすぐに対処する
もし病気が発生してしまっても、諦めずに適切な治療を行えば、紫陽花は必ず回復します。健康に育てた紫陽花は、梅雨時期に美しい花を咲かせ、私たちの心を癒してくれます。日々の丁寧な管理で、あなたの紫陽花を病気から守り、長く美しい花を楽しんでください。