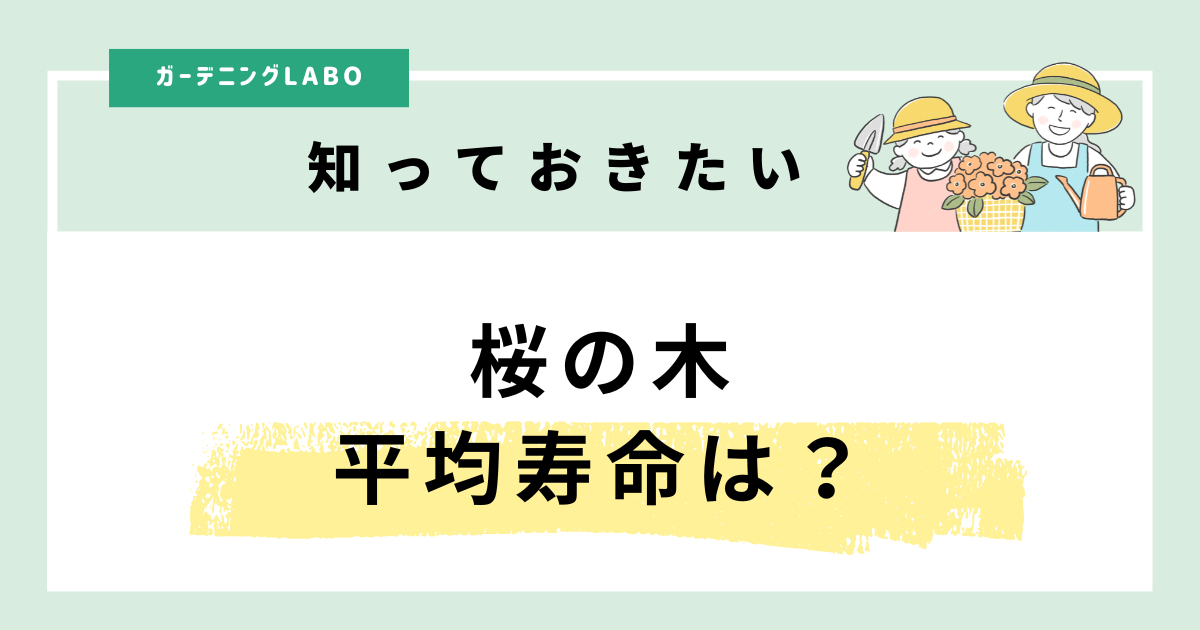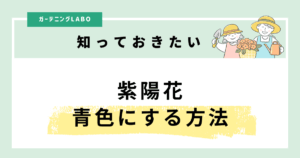春になると美しい花を咲かせる桜の木ですが、実は種類によって寿命が大きく異なることをご存じでしょうか。身近なソメイヨシノは60年程度とされる一方で、エドヒガンザクラのように1000年以上生きる種類も存在します。桜の木の寿命は平均何年なのか、また桜の木の寿命に影響する要因にはどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
本記事では、種類ごとの平均樹齢から寿命を延ばすための管理方法まで、桜の木の寿命について総合的に解説します。適切な手入れを行うことで、短命といわれるソメイヨシノでも100年以上生きることが可能になります。
- 桜の木の寿命は種類によって60年から1000年以上まで大きく異なる
- ソメイヨシノの寿命は平均60年だが適切な管理で100年以上も可能
- 病気への弱さやクローンであることが寿命を縮める主な要因
- 剪定や施肥などの適切な手入れが桜の寿命を大きく延ばす
桜の木の寿命は平均何年?種類別に詳しく解説

| 種類 | 平均寿命 | 最大樹齢 |
|---|---|---|
| ソメイヨシノ | 約60年 | 100年以上 |
| ヤマザクラ | 200~300年 | 300年以上 |
| エドヒガンザクラ | 500年以上 | 1000~2000年 |
| しだれ桜 | 100年以上 | 数百年 |
桜の木の特徴と基本情報
桜の木はバラ科サクラ属に属する落葉樹で、日本を代表する花木として古くから親しまれてきました。桜の木の寿命を考える際には、まず樹木の寿命には人間のように明確な基準がないことを理解しておく必要があります。生育環境や管理状態によって樹齢は大きく左右され、同じ種類でも数十年から数百年の差が生じることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 科名 | バラ科 |
| 属名 | サクラ属 |
| 原産地 | 日本、中国、朝鮮半島 |
| 開花時期 | 3月~5月(種類により異なる) |
| 花言葉 | 精神美、純潔、優美な女性 |
| 樹高 | 5~15m(種類により異なる) |
桜の花言葉である精神美は、日本人の心の美しさや品格を表しているとされています。また、純潔や優美な女性という花言葉は、桜の花の清らかな美しさから生まれたものです。
ソメイヨシノの寿命は60年が平均

ソメイヨシノ60年説の根拠
ソメイヨシノの寿命はおおよそ60年が平均とされています。この60年説が広まった背景には、戦後に全国各地へ植えられたソメイヨシノが、樹齢50年を超えた頃から幹の内部が腐朽し始め、樹勢が衰えるケースが多く見られたことがあります。気象庁の情報によると、折れた枝や枝の切り口から幹を腐らせる菌が侵入しやすく、樹齢50年を超えると幹の内部が腐ることから、60年で寿命を迎えてしまうという説が唱えられるようになりました。
管理次第で100年を超える個体も存在
しかし、適切な管理を行えばソメイヨシノでも100年以上生きることが可能です。青森県の弘前公園では、樹齢100年を超えるソメイヨシノが多数存在し、毎年見事な花を咲かせています。弘前公園の管理方法として知られる弘前方式では、剪定、施肥、薬剤散布を3本柱として徹底した管理を行っています。
都市部と郊外での寿命の違い
ソメイヨシノの寿命は生育環境によっても大きく変わります。都市部の公園や街路樹として植えられたソメイヨシノは、狭い植栽基盤や日照不足、土壌条件の悪さなどから、60年から70年程度で活力を失うケースが多いとされています。一方、郊外の開けた場所で十分な日当たりと土壌が確保できる環境では、より長生きする傾向にあります。
| 環境 | 平均寿命 | 主な制限要因 |
|---|---|---|
| 都市部 | 60~70年 | 狭い植栽基盤、日照不足、土壌条件の悪さ |
| 郊外 | 80~100年以上 | 比較的少ない(適切な管理が重要) |
| 管理が徹底された公園 | 100年以上 | 病害虫対策が適切であれば長寿 |
ヤマザクラの寿命は200~300年

野生種ならではの強健さ
ヤマザクラの寿命は200年から300年程度とされています。ヤマザクラは日本の山野に自生する野生種であり、本州の関東以西から四国、九州にかけて広く分布しています。野生種ならではの強健な性質を持ち、ソメイヨシノなどの園芸品種と比較して病気に強く、環境への適応力も高いことが長寿の理由です。
自生地での生育状況
ヤマザクラは山地の斜面などに自生し、適度な日当たりと水はけの良い土壌を好みます。自生地では人為的な管理を受けることなく、自然の中で長い年月を生き抜いています。樹高は10メートルから15メートルに達し、花と同時に赤褐色の若葉を展開するのが特徴です。吉野山の桜もヤマザクラが中心で、古くから日本人に愛されてきました。
エドヒガンザクラは500年以上の長寿

桜の中で最も長寿な種類
エドヒガンザクラは桜の中で最も長寿な種類として知られ、500年から1000年以上生きる個体が数多く存在します。春の彼岸頃に咲くことからエドヒガンと名付けられたこの桜は、本州から九州にかけて広く分布しています。天然記念物に指定される老木や巨木が多いことからも、その長寿ぶりがうかがえます。
日本三大桜の樹齢
日本三大桜として知られる名木は、いずれもエドヒガン系の桜です。福島県三春町の三春滝桜は樹齢1000年以上、山梨県北杜市の神代桜は樹齢約2000年、岐阜県本巣市の淡墨桜は樹齢1500年以上とされています。これらの桜は国の天然記念物に指定され、今もなお見事な花を咲かせ続けています。
| 名称 | 所在地 | 樹齢 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 三春滝桜 | 福島県三春町 | 1000年以上 | 樹高13.5m、根回り11.3mの巨木 |
| 神代桜 | 山梨県北杜市 | 約2000年 | 日本最古級の桜 |
| 淡墨桜 | 岐阜県本巣市 | 1500年以上 | 継体天皇お手植えと伝えられる |
エドヒガン系の特徴
エドヒガンザクラが長寿である理由には、いくつかの特徴が関係しています。まず、材質が緻密で腐朽しにくいこと、病害虫に比較的強いこと、そして深く広く根を張る性質を持つことが挙げられます。ただし興味深いことに、エドヒガンとオオシマザクラを交配して作られたソメイヨシノは、親であるエドヒガンの長寿の特性を受け継いでおらず、むしろ病気に弱い性質を持っています。
しだれ桜は100年以上

品種による違い
しだれ桜の寿命は100年以上とされています。しだれ桜は枝が柔らかく垂れ下がる特徴を持つ桜の総称で、エドヒガンの変種であるシダレザクラや、ヤエベニシダレなど複数の品種が存在します。品種によって寿命には差がありますが、エドヒガン系のしだれ桜は比較的長寿です。
有名なしだれ桜の樹齢例
京都の祇園しだれ桜や京都御苑の近衛邸跡のしだれ桜など、各地に樹齢100年を超える名木が存在します。適切な管理が行われていれば、200年から300年生きるしだれ桜も珍しくありません。しだれ桜は観賞価値が高いため、寺社や庭園で大切に管理されることが多く、それが長寿につながっています。
園芸品種と野生種の寿命の違い
園芸品種は100年前後
ソメイヨシノをはじめとする園芸品種の寿命は100年前後とされています。園芸品種は観賞用に品種改良されたもので、花の美しさや開花の揃いやすさなどが重視されています。しかし、その反面として病気への抵抗力が弱かったり、環境変化への適応力が低かったりする傾向があります。
野生種は数百年から1000年以上
ヤマザクラやエドヒガンなどの野生種(基本種)は、数百年から1000年以上の寿命を持ちます。自然環境の中で長い年月をかけて進化してきた野生種は、病害虫への抵抗力や環境への適応力が高く、人為的な管理がなくても長生きする傾向にあります。
寿命に差が出る理由
園芸品種と野生種の寿命に大きな差が生じる理由はいくつかあります。まず、園芸品種は成長が早い反面、早く老化する傾向があります。また、接ぎ木で増やされることが多く、接ぎ木部分が弱点となって病気が侵入しやすくなります。さらに、遺伝的多様性が低いため、特定の病気や環境変化に弱い特性を持っています。
接ぎ木栽培の影響
ソメイヨシノなどの園芸品種は、接ぎ木によって増殖されます。接ぎ木とは、台木となる桜の木に別の品種の枝を接ぐ方法で、同じ遺伝子を持つクローンを大量に生産することができます。しかし、接ぎ木部分は樹木の弱点となりやすく、そこから病原菌が侵入すると樹全体に広がりやすいという問題があります。また、台木と穂木の相性によっても寿命が左右されます。
| 園芸品種の特徴 | 野生種の特徴 |
|---|---|
| 花が美しく観賞価値が高い 開花が揃いやすい 成長が早い 寿命が短め(100年前後) 病気に弱い傾向 接ぎ木が必要 | 病害虫に強い 環境適応力が高い 寿命が長い(数百年~1000年以上) 種子で増殖可能 開花時期にばらつき 成長がやや遅い |
最古の桜は樹齢何年?日本の名桜
山梨県の神代桜(樹齢2000年)

日本最古の桜として知られる神代桜は、山梨県北杜市の実相寺境内にあるエドヒガンザクラで、樹齢約2000年とされています。神代とは神話の時代を意味し、それほど古い時代から存在していることを示しています。日本武尊が東征の際に植えたという伝説も残されており、国の天然記念物に指定されています。
福島県の三春滝桜(樹齢1000年以上)

福島県田村郡三春町にある三春滝桜は、樹齢1000年以上といわれる紅枝垂桜の巨木です。樹高13.5メートル、根回り11.3メートルの大きさを誇り、四方に伸びた太い枝から無数の花が咲く様子が、まるで滝が流れ落ちるように見えることから滝桜と呼ばれています。大正11年に国の天然記念物に指定され、日本三大桜の一つに数えられています。
岐阜県の淡墨桜(樹齢1500年以上)

岐阜県本巣市の根尾谷淡墨公園にある淡墨桜は、樹齢1500年以上とされるエドヒガンザクラです。第26代継体天皇がお手植えされたと伝えられ、古墳時代から現在まで生き続けています。樹高約17メートル、幹周り約9メートルの巨木で、つぼみのときは薄いピンク、満開時には白色、散りぎわには淡い墨を引いたような色になる特徴があり、この独特の色合いから淡墨桜と名付けられました。
桜の木の寿命に影響する要因と長持ちさせる秘訣

| 影響要因 | 寿命への影響度 | 対策の可否 |
|---|---|---|
| 病気 | 大 | 可能(薬剤散布、剪定) |
| クローン特性 | 中 | 困難(品種の特性) |
| 成長速度 | 中 | 一部可能(施肥調整) |
| 生育環境 | 大 | 可能(土壌改良、植栽場所選定) |
| 管理不足 | 大 | 可能(適切な手入れ) |
病気に弱い性質が寿命を縮める
テングス病の脅威
桜の寿命を縮める最も大きな要因の一つが病気です。特にテングス病(てんぐ巣病)は、ソメイヨシノにとって深刻な脅威となっています。この病気はタフリナ菌というカビの一種が原因で、葉の裏に胞子が付着して感染が広がります。感染した枝は小枝が密集して玉状になり、花が咲かなくなります。放置すると他の枝や近隣の桜にも感染が広がり、最終的には木全体を枯らしてしまう恐ろしい病気です。
幹腐病と切り口からの菌の侵入
桜には古くから「桜切るばか梅切らぬばか」ということわざがあります。これは桜が剪定に弱いことを示しており、切り口から腐朽菌が侵入しやすい特性を持っているためです。樹齢50年を超えると幹の内部腐朽が進みやすくなり、幹が空洞化してしまうケースが多く見られます。切り口には必ず癒合剤を塗布し、病原菌の侵入を防ぐ対策が必要です。
土壌伝染病の影響
老木になると傷や剪定跡から担子菌の胞子が入りやすくなり、根や幹が腐りやすくなります。ナラタケ病などの土壌伝染病も桜の寿命を縮める要因となります。これらの病気は一度発生すると治療が困難で、予防が何より重要です。定期的な薬剤散布や、土壌の水はけを良くすることで、病気の発生リスクを減らすことができます。
| 病気の種類 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| テングス病 | 小枝が密集し玉状に、花が咲かない | 感染枝の除去、薬剤散布 |
| 幹腐病 | 幹の内部が腐朽、空洞化 | 切り口への癒合剤塗布、適切な剪定 |
| ナラタケ病 | 根や幹の腐朽、キノコの発生 | 土壌改良、水はけ改善 |
| こうやく病 | 枝に白い膜状のもの付着 | 感染部位の除去、薬剤散布 |
クローンであることの影響
ソメイヨシノは全て接ぎ木のクローン
ソメイヨシノの大きな特徴として、全ての個体が接ぎ木によるクローンであることが挙げられます。江戸時代末期にエドヒガンとオオシマザクラを交配して誕生したソメイヨシノは、種子では増えることができないか、増えても親と同じ特性を持たないため、接ぎ木によってのみ増殖されてきました。つまり、全国に植えられているソメイヨシノは、遺伝子的に全て同一の双子のような関係にあります。
遺伝的多様性の欠如
全ての個体が同じ遺伝子を持つということは、特定の病気や環境変化に対して、全ての木が同じように弱いという弱点を持つことを意味します。野生種であれば個体ごとに遺伝子が異なるため、ある病気が流行しても抵抗力の強い個体は生き残ることができます。しかし、ソメイヨシノの場合は全ての個体が同じ弱点を持っているため、一度大規模な病気が流行すると、一斉に被害を受けるリスクがあります。
種子で増えることができない特性
ソメイヨシノは種子をつけることもありますが、その種子から育った木は親と同じソメイヨシノにはなりません。これは雑種第一代の特性によるもので、自然に子孫を残して世代交代することができないのです。この特性も、ソメイヨシノの寿命が限られている要因の一つといえます。老木が弱ってきても自然に若木が育つことはなく、人為的に新しい苗木を植える必要があります。
成長速度の早さと寿命の関係
成長が早い樹木は短命の傾向
一般的に、成長が早い樹木ほど寿命が短いという傾向があります。これは植物の成長と老化のバランスに関係しています。急速に成長する植物は、それだけ早く成熟し、早く老化が始まるという特性を持っているのです。ソメイヨシノは成長が非常に早く、植えてから数年で花を咲かせ始め、10年から15年ほどで立派な木に成長します。
ソメイヨシノの急速な成長
ソメイヨシノが戦後に全国へ急速に広まった理由の一つが、この成長の早さです。公園や街路樹として植えられてから短期間で見応えのある桜並木を作ることができるため、各地で積極的に植栽されました。しかし、その急速な成長の代償として、他の桜に比べて寿命が短くなっているのです。一方、エドヒガンやヤマザクラは成長がゆっくりで、若木から開花までに時間がかかりますが、その分長寿です。
| 桜の種類 | 開花までの年数 | 成長速度 | 平均寿命 |
|---|---|---|---|
| ソメイヨシノ | 3~5年 | 早い | 約60年 |
| ヤマザクラ | 7~10年 | 中程度 | 200~300年 |
| エドヒガン | 10~15年 | 遅い | 500年以上 |
生育環境が桜の寿命を左右する
都市部と山間部での寿命の違い
桜の寿命は生育環境によって大きく左右されます。都市部の公園や街路樹として植えられた桜は、山間部に自生する桜に比べて寿命が短い傾向にあります。都市部では植栽後に周囲の環境が変化することが多く、当初は日当たりが良かった場所でも、建物が建つことで日陰になってしまうケースがあります。また、狭い植栽基盤では根が十分に伸びることができず、水分や養分の吸収が制限されてしまいます。
土壌条件の重要性
桜は水はけが良く養分に富んだ土壌を好みます。水はけが悪い土壌では根腐れを起こしやすく、養分が不足すると樹勢が衰えてしまいます。都市部では土壌が固く締まっていたり、建設工事の影響で土壌が劣化していたりすることが多く、これが桜の寿命を縮める要因となっています。植栽前の土壌改良や、定期的な施肥が重要です。
日照条件と風通し
桜は日光を好む樹木で、十分な日照がないと樹勢が衰え、病気にもかかりやすくなります。また、風通しの悪い場所では湿度が高くなり、病害虫が発生しやすい環境になります。桜並木として密植されている場合、枝が絡み合って風通しが悪くなることがあり、これも寿命を縮める要因となります。適切な間隔を保ち、定期的な剪定で風通しを確保することが大切です。
人間活動の影響
花見の時期に大勢の人が桜の根元を踏み固めることも、桜にとってはストレスとなります。根元の土壌が固く締まると、根への酸素供給が妨げられ、根の生育が阻害されます。また、根の上を車両が通行したり、建設工事で根を切断したりすることも、桜の寿命を大きく縮める要因です。名所として多くの人に親しまれている桜ほど、このような人為的なストレスにさらされているのです。
適切な手入れで寿命を延ばす方法
剪定のタイミングと方法
桜の寿命を延ばすために最も重要なのが、適切な剪定です。青森県弘前公園で実践されている弘前方式では、毎年2月下旬から3月末にかけて剪定作業を行っています。剪定の目的は、枯れた枝や病気の枝を落とすこと、風通しや日当たりを良くして木を元気にさせること、老化した枝を切り落として若い枝を伸ばすことの3点です。ただし、剪定後は必ず切り口に癒合剤を塗布し、病原菌の侵入を防ぐことが重要です。
施肥の重要性
桜は花を咲かせるために多くの養分を必要とします。毎年見事な花を咲かせるためには、花が終わった後に適切な施肥を行うことが大切です。弘前公園では、りんご栽培で培った技術を応用し、花が終わると肥料を根元に施しています。有機質肥料をゆっくりと効かせることで、樹勢を維持し、病気への抵抗力も高めることができます。
病害虫の予防と対策
病気や害虫から桜を守るためには、予防的な薬剤散布が効果的です。弘前公園では、虫や病気から守るため定期的に薬剤を散布する管理を行っています。特にテングス病の感染を防ぐためには、発病前の予防散布が重要です。また、感染した枝を見つけたら速やかに切除し、他の枝への感染拡大を防ぐ必要があります。
樹木医による定期診断
樹齢が高くなった桜は、専門家による定期的な診断を受けることが望ましいです。弘前市では2014年に樹木医3人と現場職員約40人で構成するチーム桜守という体制を作り、専門的な知識と経験に基づいた管理を行っています。樹木医は木の健康状態を診断し、必要な処置を判断することができます。個人で管理している桜でも、樹木医に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。
弘前公園の成功事例
弘前公園の桜管理は、桜の寿命を延ばす成功事例として全国から注目されています。明治時代に植えられた桜が一般的な寿命である60年を超えて衰え始めた際、りんご栽培の技術を応用して剪定を行ったところ、弱った桜が再び美しい花を咲かせるようになりました。現在でも弘前公園には樹齢100年を超えるソメイヨシノが多数存在し、毎年ボリュームのある見事な桜を咲かせています。
枯れた枝や病気の枝を除去し、風通しと日当たりを改善します。切り口には必ず癒合剤を塗布します。
花が終わった後、根元に有機質肥料を施して樹勢を回復させます。
病害虫を予防するため、適切な時期に薬剤を散布します。
木の状態を常に観察し、異常があれば早期に対処します。必要に応じて樹木医に相談します。
老木の特徴と見分け方
幹の空洞化
老木の最も分かりやすい特徴が幹の空洞化です。樹齢が高くなると幹の内部が腐朽し、中が空洞になることがあります。軽く幹を叩いてみて空洞音がしたり、幹に穴が開いていたりする場合は、内部が腐朽している可能性が高いです。空洞化が進むと強風時に幹が折れたり、倒木したりする危険性が高まります。
樹皮の剥がれと枝の枯れ込み
樹皮が部分的に剥がれたり、表面がゴツゴツと荒れていたりするのも老木の特徴です。また、枝の先端から徐々に枯れ込んでくる症状も見られます。健康な桜であれば枝の先まで若々しい芽が付きますが、老木になると枝の先端部分が枯れて、次第に枯れ込みが幹に近い部分まで進行していきます。
花付きの悪化
以前に比べて花の数が減ったり、花が小さくなったりするのも、樹勢が衰えている兆候です。桜は花芽を前年の夏に形成するため、樹勢が衰えると翌年の花付きに影響が出ます。部分的に花が咲かない枝がある場合は、その枝が病気にかかっているか、枯れかけている可能性があります。
倒木の危険性
幹の空洞化が進んだ老木は、台風などの強風時に倒木する危険性があります。特に公園や街路樹として人通りの多い場所に植えられている場合は、安全性の確保が重要です。樹木医による診断を受け、必要に応じて支柱を設置したり、危険な枝を除去したりする対策が必要です。場合によっては伐採も検討しなければなりません。
| 老木の兆候 | 見分け方 | 危険度 |
|---|---|---|
| 幹の空洞化 | 幹を叩いて空洞音、穴の存在 | 高(倒木リスク) |
| 樹皮の剥がれ | 樹皮が部分的に剥がれている | 中 |
| 枝の枯れ込み | 枝先から徐々に枯れる | 中 |
| 花付きの悪化 | 花の数が減少、花が小さい | 低(美観の問題) |
| キノコの発生 | 幹や根元にキノコが生える | 高(内部腐朽の証拠) |
植え替えと世代交代の必要性
全国で進むソメイヨシノの植え替え
戦後に植えられたソメイヨシノが樹齢60年から70年を迎え、全国各地で植え替えや世代交代が進んでいます。愛着のある桜を伐採することには抵抗感もありますが、倒木などの危険性を考えると、計画的な世代交代が必要です。多くの自治体では、老木が完全に枯れる前に後継樹を植え、段階的に世代交代を進める取り組みを行っています。
後継品種の選択
ソメイヨシノの後継として、どの品種を選ぶかは重要な課題です。再びソメイヨシノを植える選択肢もありますが、病気に弱いという問題は解決されません。そこで、ソメイヨシノに似た花を咲かせながら、テングス病に強い品種として開発されたジンダイアケボノなどの新品種が注目されています。公益財団法人日本花の会では、2005年からソメイヨシノの苗木の出荷を停止し、病気に強い品種への切り替えを推奨しています。
忌地現象への対応
桜には忌地現象という特性があり、同じ場所に続けて桜を植えることが困難です。古い桜を伐採した後、その場所に新しい桜を植えても生育が悪くなることが多いのです。これは土壌中の病原菌や、前の木が出していた化学物質などが影響していると考えられています。対策としては、植え付け場所を少しずらす、土壌を全て入れ替える、数年間別の植物を植えてから桜を植えるなどの方法があります。
植え替えの際は、古い桜が完全に枯れる前に後継樹を植えることで、桜の景観を途切れさせない工夫が大切です。
よくある質問
- 桜の盆栽の寿命はどれくらいですか
-
桜の盆栽の寿命は一般的に数十年程度とされています。鉢植えという制限された環境で育てられるため、地植えに比べて寿命は短くなります。ただし、適切な管理を行えば50年以上生きる盆栽もあります。定期的な植え替え、剪定、施肥が長寿の秘訣です。
- 桜の切り花はどのくらい持ちますか
-
桜の切り花は適切に管理すれば1週間程度楽しむことができます。水揚げをしっかり行い、こまめに水を替えることが大切です。また、直射日光を避け、涼しい場所に飾ることで長持ちします。促成栽培の技術により、12月から4月頃まで切り花として流通しています。
- 自宅の桜が枯れそうなときはどうすればよいですか
-
桜が枯れそうな場合は、まず樹木医に相談することをおすすめします。樹木医は木の健康状態を診断し、適切な処置を提案してくれます。早期に対応することで回復の可能性が高まります。一般社団法人日本樹木医会のウェブサイトで、お住まいの地域の樹木医を検索することができます。
- 桜の木の下に植えても良い植物はありますか
-
桜の木の下には、根を深く張らず、桜の根を傷めない植物を選ぶことが大切です。シバザクラやスミレ、ツツジなどが適しています。ただし、桜の根元を覆いすぎると通気性が悪くなるため、適度な範囲にとどめることが重要です。また、根元での作業は桜の根を傷つける可能性があるため、慎重に行う必要があります。
- 桜の木は自宅の庭に植えても大丈夫ですか
-
桜は大きく成長する樹木のため、十分なスペースが確保できる広い庭であれば植えることができます。ソメイヨシノは高さ10メートル、横にも10メートルほどに広がるため、狭い庭には向きません。コンパクトな品種や鉢植えで管理できる品種を選ぶと良いでしょう。また、落葉や毛虫の発生など、近隣への配慮も必要です。
種類によって異なる桜の木の寿命と適切な管理のポイント
- 桜の木の寿命は種類によって大きく異なり、ソメイヨシノは約60年、ヤマザクラは200~300年、エドヒガンは500年以上
- ソメイヨシノの60年説は戦後植樹された木が樹齢50年を超えて衰え始めたことに由来する
- 適切な管理を行えばソメイヨシノでも100年以上生きることが可能で、弘前公園にはその実例がある
- 園芸品種は100年前後の寿命だが、野生種は数百年から1000年以上生きる
- 日本最古の桜は山梨県の神代桜で樹齢約2000年、三春滝桜は1000年以上、淡墨桜は1500年以上
- テングス病や幹腐病などの病気が桜の寿命を大きく縮める要因となる
- ソメイヨシノは全て接ぎ木のクローンで遺伝的多様性がなく、特定の病気に一斉に弱い
- 成長が早い樹木ほど寿命が短い傾向があり、ソメイヨシノの急速な成長が短命の一因
- 都市部の桜は狭い植栽基盤や日照不足により郊外の桜より寿命が短い
- 桜は水はけが良く養分に富んだ土壌と十分な日照、良好な風通しを必要とする
- 弘前方式による管理は剪定、施肥、薬剤散布の3本柱で樹齢100年超のソメイヨシノを維持している
- 剪定後は必ず切り口に癒合剤を塗布し病原菌の侵入を防ぐことが重要
- 老木の兆候として幹の空洞化、樹皮の剥がれ、枝の枯れ込み、花付きの悪化がある
- 戦後植樹されたソメイヨシノが寿命を迎え全国で計画的な世代交代が進んでいる
- 後継品種としてテングス病に強いジンダイアケボノなどの新品種が注目されている